��101���w����ɏj100��x
2006.2/2�f��
�@���̘A�ڂ�����100����z���Ă��܂��܂����B�������Z�N�Ƃ����z��O�̒����A�ځI���j�����̎l������͒��w���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ�������r�b�N���ł��B
�@�����ŁA�X�N���b�v���Ă���o�b�N�i���o�[��ǂݕԂ��Č��܂����B
�@�A�ړ����́w���e�x�̖ڐ�����玙�����Ă݂�ƈӊO�Ȗʂ�������Ƃ��A��v�Ȃ�ł͂̎q�ǂ��Ƃ̐G�ꍇ����������������������Ă��܂����B
�@���ꂪ����w���|�Ƃ̕��e�x�̖ڐ��ɕς��A����ɉ䂪�Ƃ̎q���������L�̗l����悵�Ă��܂����B
�@�ŋ߂Ɏ����ẮA��������w��������̂��y���ݓ��L�x�Ɖ����A�玙���v�̂�����ɂقƂ�ǐG��Ă��Ȃ��ł͂���܂��B����͂���Ŗʔ�����������܂��A�ǂ�ʼn�������ɂ́A�Ȃ�̖��ɂ������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�Ƃ����킯�ŁA����͂�����Ƃ܂��߂Ɏq��Ăɂ��Ă��b�����Ă��������Ǝv���܂��B
�@�e�[�}�͎q���̐����ɂ��āB
�@�q���̐����ƕ����Ă܂��v�����̂́A�n�C�n�C�ł��āA����ׂ�n�߂āA����������Ƃ���������ł��傤�B���̍��̐�����ڂɂ���̂́A�܂��ƂɌ��I�ŋ����ł�������܂��B�N�ɂ��̃V�[���������Ă���邩�͉^����A�����҂͎����̎�ɂł���قǁB
�䂪�Ƃ̎q�������܂ꂽ���A���͓����Ă��āA���[�͈玙�x�ɒ��B�����V�[���͂��ׂď��[�̂��̂ɂȂ��Ă��܂����B��������߂��ׂ����͎�v�ƂȂ�A���̌�̑����̃V�[����ڌ����Ă��܂����B���������I�ȃV�[���͂����Ă����A����ɂ��̖ڌ��҂́A�ۈ牀��w�Z�̐搶�ɂƂ��đ����܂����B
�@�Ƃ���ŁA�������w���t�Ƃ��āA���낢��Ȑ����̃V�[�������Ă����킯�ł����A���������鐬���Ɛe�����鐬���Ƃ͂����Ԋu���肪����悤�Ɏv���Ă��܂��B
�@�����́A�݊w���E�w�����E�P�����E���ƒ��Ƃ���������ꂽ�X�p���̒��Ő������Ƃ炦�܂��B����A�����̃V�[�����Ӑ}�I�ɂ˂���Ă����킯�ł��B�t�オ����ɂ���ƁA�����͒P�����ɂ������w�����A�Ō�̎��ԂɃe�X�g�����܂��B���łł�����A�܉�ȓ��ɂł�����A�܉�łł��Ȃ�����Ƃ�����ɐ������Ƃ炦�܂��B����͂���Ō��I�Ȑ����ŁA���t�����ɐs���܂��B
���A�e�͂����ƒ����X�p���Ő������Ƃ炦�܂��B�u���̎q���e�ɂȂ������A�����̎q���ɋt�オ�苳���Ă��邩����v�Ƃ��u���̎q�����\�ɂȂ������A�Q�����肶��Ȃ��ċt�オ��o���邭�炢���N�ł��Ă��炢�����v�Ƃ����ӂ��ɁB
�@����Ȃ킯�ŁA���̘A�ڂ��l���I�Ȓ����X�p���łƂ炦�Ă��������āA�u100��͂܂��܂��ʉߓ_�B�ق�̈ꍇ�ځB�v�Ƃ������ƂŁA��������Ђ����ɁI
�@�@
��102�b�w���E�ǍD�Q�x
2006.2/11�f��
�@�q���̑̂̕ω��̑����ɂ́A�ڂ���������̂�����܂��B�ǂ��Ȃ�̂������Ƃ����ԂȂ�A�����Ȃ�̂������Ƃ����Ԃł��B
�@�t�̌��f�ł͂`���肾�������j�̎��͂��A�H�̌��f�ł͂Ȃ�Ƃb�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�i�ŋ߂̊w�Z�ł̎��͌����́A�P�E�T�Ƃ��O�E �W�Ƃ������܂���B�`�a�b�c�Ƃ������肪�o�����̂ł��B�`�͂悭������i���������P�E�O�j�A�a���b���c�ƈ����Ȃ�A�b�͂O�E�T����O�E�P���炢�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɒ��j�͂c�B�m��77�b�Q�Ɓn�j
�@����������̉����ߎ��͂����Ƃ����Ԃɗǂ��Ȃ邱�Ƃ�����Ɗ��҂��āA���j�Ǝ��͉g���[�j���O�Ɏ��g�݁A���܂����Ă��܂������A�N�������炢����܂��܂������Ȃ��l�q�B�e���r�����Ă���ƒm�炸�m�炸�̂����ɂǂ�ǂ�ڋ߂��Ă����܂��B����Ⴀ�̌����݂Ȃ��B�ق��Ƃ��܂��܂��������Ă��܂��Ɣ��f�B�d���Ȃ��ዾ����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�܂��͊�Ȃɍs���܂��B���j�̂Ƃ����l�Ɂu���ł���ȂɂȂ�܂łق��Ƃ����H�v�Ɠ{���܂��B����Ă���̂ŕ��������A�ዾ�X�Ɍ������܂��B
�@���j�قNj����������Ȃ��̂ŁA���������x��Ȃ��i�݂܂��B�u�����������Ȃ��q�Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�������Ȃ����̂��v�Ƃ��肢����ƁA�X����������Ȃ����ĒT���Ă���܂��B�u�l�͐F�������v�Ƃ������j�̌��t�ł������茈�܂�A�����Y����Ȃ����肵�܂����B�h�L�h�L�h�L�h�L�c�B�u���v�A�P�X�T�O�O�~�ł��B�v�����A���j�̂Ƃ��������I�������A�����Y�̋��������Ȃ����A����Ȃ��̂���Ȃ��Ă��������A�t���[�����������̂łȂ��Ă��������炩�B����ς菭���ł����N�Ƃ����͈̂����Ă����Ȃ��A�Ǝ������ċA���Ă��܂����B
�@����A�ዾ���o���オ���Ă��܂����B�|���Ă݂��
�u�������I�����邼���I�v
���j�̊�т̐����B���Ƃ͂����܂�̎��͌����B�ƒ��̂���Ƃ����镶���𗣂ꂽ�Ƃ��납��ǂ�ł݂��܂��B���Ɋዾ���͂����ēǂ߂Ȃ����Ƃ��m�F���܂��B30���قǂŌ������I�����A�ዾ���P�[�X�ɕЕt���܂��B�u����H�ዾ�����Ȃ��́H�v�ƕ����Ɓu�����Ċዾ�����Ă�ƕs�ւ�����B�v�Ɠ����܂��B���j���펞�ዾ�������Ă��āA�\�ꂽ��V�肵�Ă���Ƃ��ɉȂ��悤�ɋC�ɂ����Ă���̂����Ă���̂ŁA���ꂪ�ʓ|�������悤�Ɏv�����悤�ł��B�u�����Ċዾ�����Ă���悭�����Ċy�����ł���B�|������Ƃ����肷��̖ʓ|�����A�ǂ����ɂȂ������獢�邶���B�v�ƌ����Ă��������������ɗV�тɍs���Ă��܂��܂����B�������A�ዾ���p���@��ɖ\���V�呲�Ƃ�_���ĂP�X�T�O�O�~�͂������̂Ɂc�B
�@�������䂪�Ƃŗ���̏��N����l�A����������炸�\��Ă��܂��B
�@
��103�b�w���s�x
2006.2/18�f��
�@���s�ɏ��x���̂͂Ȃ�ƂȂ����т������́B���Ƃ����āA���ł�����ł����s�ɏ��������̂ł͂���܂���B�{���Ɏ����ɂƂ��ėL�v�Ȃ��̂����l���A�����Ȃ�ɍ̂肢��Ă������s�ɏ�����Ƃ�����ł��傤�B
�@�܂��A���s�ɏ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ꍇ������܂��B���̕M�����~�̒�ԁw�C���t���G���U�x�ł��傤�B
�@���s�ɓ݊��ȉ䂪�Ƃ̂��ƁA�܂����C���t���G���U�ɜ��Ȃ�Ďv���Ă����܂���A�\�h�ڎ�Ȃǂ��Ă���͂�������܂���B�������i������H�j���V�[�Y���́A�ꂳ��E���j�E���j�̎O�l�������s�ɏ���Ă��܂��܂����B
��Ԏ�͎��j�B���j�̖邩��O�f�O�f���Ă�Ǝv�����猎�j���ɔ��ǁB38�x�T���̔M���o�����a�@�ցB�����C���t���G���U�̐f�f�����������A��T�Ԃ̓��a���������ҁB�C�ǎx���ɂ��Ȃ肩�����Ă���Ƃ������ƂŁA���˓�{�̃T�[�r�X���I
��Ԏ�͒��j�B�Ηj�̒��ɔ��ǁB�������38�x�X���قǂ̔M���o���A�����ЂƂ�ł͕����Ȃ��قǃt���t�����Ă��܂����B���R�C���t���G���U�̐f�f�����������A�l���ܓ��̓��a���������ҁB�̂ǂ������Ɛ������݂����A�^�~�t���������Ěq�f�̂��܂����I
�@�O�Ԏ�͕ꂳ��B���j���Ɏq���B�̊ŕa���łɃS���S�����Ă�����A���߂��ɕꂳ�A���Ă��܂����B�u�D���������A�q���B�̂��߂ɑ����A���Ă��Ă��ꂽ��v�Ǝv���Ă�����A�u�����_�E��������a�@�A��Ă��āv�ƁB38�x�S���̔M���o���A�����ŎԂ��^�]�ł��Ȃ��Ȃ��āw������~�}�ԁx�̗v���B������ŃC���t���G���U�̐f�f�����������A�l���ܓ��̓��a���������ҁB�d�������x�݂܂������A�����e�`�w�Ŏw�����o��������Ƃ������Ƃ̎В��̂悤�ȗ×{�����ł����B
�@�����Ȃ��Ă��܂������䂪�Ƃ̓C���t���G���U�̐��Ƃł��B��C�͓b�݁A�ǂ��֍s���Ă��P�ƕ@�����މ��ƁA�[�C�[�C�Ƌꂵ�����ȑ����������Ă��鐢�E�B������������A��������Ă���A���������Ă���A�ƒQ��̐����������B���߂̓V�g�����悤�Ȃ܂ł́A�Ƃ������炢�̃i�[�X�R�[���𐿂��܂���܂����B�a�l�H�����A������܂��A���ւ�����`���A�M�𑪂�Ȃǔ��ʘZ�]�̑劈��B����Ɋ��҂��Q�Â܂�̂�҂��āA���o���E�|���E����E���ʂ��Ȃǂ������Ȃ��A�x���܂Ŕ��߂̕�����̎d���͑����̂ł����B
�����܂ł�����A���܂���}�X�N�����悤���A�����������悤�������C���t���G���U���瓦��邱�Ƃ͂ł��܂��Ɗo������߂邵������܂���B���߂Ă݂�Ȃ���������܂ł͎����������悤�A�Ɠ��ʃX�^�~�i�H���������H���{�ɓw�߂܂����B�������ł��܂��ɔ��ǂ��Ă��܂��A�̏d�̑啝�����Ƃ�������p�ɋꂵ��ł��܂��B
�@
��104�b�w��~�V�������x
2006.3/5�f��
�@����̃C���t���G���U�R�A���ŁA������ƕς�������Ƃ�����Ă݂܂����B����͎O�l�Ƃ��Ⴄ��҂ɍs���Ƃ������̂ł��B���ɈӐ}���������킯�ł͂Ȃ��A���ɉ����čs���₷���Ƃ���ɍs�����̂ł����A���ʂƂ��Ă��̍����r�ł���L�Ӌ`�ȍs���ɂȂ�܂����B
�@���j���s�����̂́u�}���K��f��ɏo�Ă��������ˁv�Ƃ����悤�ȌÐF���R�Ƃ����`��@�B���ւ����ƃX�g�[�u���ۂ�ƒu���ꂽ���Â��ҍ����B�Ō�t�E��t�E���҂��N�����炸�A���������o�����V��t����������l�ŏo�}���Ă���܂��B
���Ɋ��҂����Ȃ��̂ł����ɐf�@�ɓ���܂��B����ǂ��Ă������肵�Ă���҂ɂƂ��āw�����f�Ă����x���肪�����͉����̂ɂ��ウ���܂���B�Ђƒʂ�f�@���āu�C���t���G���U�ł��B�������C�ǎx���̏����B��͂���Ƃ�����o���܂��B���˂��Q�{�ł��Ƃ��܂��傤�B�v�Ɩ��m�Ȑf�f��������܂��B
���̘V��t�͕K�v�Ƃ���Εa�l�ɂ�����������Ƃ������̎ҁB�Ȃ�ł��͂����茾���Ă����̂ŁA�������Ȃ����ʂƂ��Ă����肪��������܂��B
���܂߂ĂP�Q�O�O�~�̐f�@���B
���˂��A���Ă��邾���ł��ɂ����Ȃ��Ƃ���������āA�������萯�l���Ƃ����Ƃ���ł��傤�B
�@�ꂳ�s�����͖̂{���͊O�Ȃ����ӂƂ����a��@�B���\����ł������̂́u���̎��ԂȂ�f�Ă��v�Ƃ���ꂽ���Ԃɍs���ƁA�قƂ�Ǒ҂����ɐf�@���Ă���܂����B
�Ǐ���ڍׂɕ����A�C���t���G���U�̔���������A���̌�̐����̒��ӂƁA�Ǐ�ʑΏ��@���w�����Ă���܂����B����Ɂu�����y�ɂ��Ăق����v�Ƃ�����]�ɉ������˂P�{�ł��āA���܂߂ĂS�O�O�O�~�̐f�@���B
���炭�����Ȃ��Ǝv����������ς��B��M�̍���܂ŏ�������O�̓���B��ʂȂ��Ƃ����݂āA�������萯�O�Ƃ����܂��傤�B
�@���j���s�����̂͂b��@�B�����͂��s���Ă������ς��̊��ҁB���̓����\�Ԃɍs�����ɂ�������炸20���قǑ҂��܂����B
�f�@�́u�C���t���G���U���Ǝv���܂����A�������܂����H�v�u���������Ǐ�ł����ǂ����܂����H�v�Ƃ������q�B��ɂ��Ă��u����͂����������\�̖�ł����A�v��܂����H�������̖�͂ǂ��ł����H�v�Ƃ�����܂����B�C���t�H�[���h�R���Z���g�����\�����ǁA�������͂Ȃ�ɂ�������Ȃ����A��������Ȃ����A��҂𗊂��čs���킯������A���m�Ȏw�����ق������̂ł��B����ł͕a�C�̕s�����ʂ����܂���B
�f�@���́A���܂߂ĂR�T�O�O�~�B��������́A�s���Ƒ҂����ԂƃA�t�^�[�t�H���[���l����ƁA����`�c�B
�ǂ̊��҂���T�Ԍ�ɂ͎���܂������A���낢��H�H�H�̈�@�߂���ł����B
�@
��105�b�w���w�֍s���N�ɇ@�x
2006.3/16�f��
�@�������̂ł��̘A�ڂ��n�܂����Ƃ��A���w�Q�N�����������j���A���̎l�����璆�w���ɂȂ�܂��B���w���ɂȂ�s������҂₢�낢�낪��������悤�ł��B
�@��ʓI�ɁA�w���w�ɍs���Ɓx�ƌ����邱�Ƃ́A
�@���Ȃ��Ƃɐ搶���ς��B����͊m���ɑ傫�ȕω��ł����A�ŋ߂͏��w�Z�ł����l���w�K�Ƃ��A�R�[�X�ʊw�K�Ƃ����̂����s���Ă��āA�����Ȑ搶�ɏK�������Ƃ�����̂ŁA�˘f�����Ƃ͖����ł��傤�B�ނ��듯���搶�Ǝl�Z����������킹�Ȃ��ł��ނ̂ŁA��ւ��E���Z�b�g�������₷���Ȃ邩������܂���B
�A�p�ꂪ�����A���Ȗ������w�E���p�E�ی��̈�E�Z�p�ƒ�Ȃǂɕς��B�m���ɉp��Ƃ������Ȃ������邱�Ƃ͂��������Ƃ̂悤�Ɏv���܂����A���Ȃ�ď�ɐV�������Ƃ��w��ł����̂ł�����������Ƃł͂Ȃ��͂��ł��B���Ȗ��͕ς�����Ƃ���ŁA���e�͎Z���E�}�H�E�̈�E�ƒ�Ȃ̉����ł�����A�܂��ς��Ȃ��ƌ����Ă������ł��傤�B
�B��������Ȃ�A�ʂ�������B����͂����ł��B�O�q�ǂ�����Ȃ�ď�ɐV�������Ƃ��w��ł����̂ł��������͓̂�����O�B���w�Z�ƂȂ��Ⴂ�͂���܂���B�ʂ����āA�p�ꂪ�����邱�Ƃł��������C���[�W������悤�ł����A������ԁA�T�ܓ��͏��w�Z�Ɠ����ł��B
�C������������B����͐����̑啔�����߂��ω��ƌ����Ă����ł��傤�B�����̗��K��A�x���ɂ܂Ŏ��銈���́A���ɉƑ��̐����܂ŕς��Ă��܂����̂ł��B�������ւ̎��g�݂��A���w�Z�����̈�Ԃ̎v���o�ɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�܂��A���w�N�̐��k�Ƃ̂������̒��ŁA�Љ����Ă邢���@��ł�����܂��B�ړI����������̂̏W�c�̖ʔ������\��������Ă��炢�����Ɗ肢�܂��B
�@�D����������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Z������������B�����̐���͒u���Ƃ��āA�Z���Ƃ����@���̃~�j�`���A�ɔ����邱�Ƃ͑�Ȃ��Ƃł��傤�B�Љ�ɏo���Ƃ��ɂ��ꂼ��̃R�~���j�e�B�[�ɂ͂��ꂼ��̃��[��������A��������炷�邱�Ƃ̑������K����킯�ł�����B����ɁA���[�����̂��̂̉��l���l������A���[����ς���Ӌ`���i���w�Ԃ̂ɂ����ɗ����܂��B�킯�̂킩��Ȃ��ςȍZ��������w�Z���Љ��邱�Ƃ�����܂����A����ɂ��Đ��k���l���邱�ƂɈӖ�������̂ł��B�i�搶�����͗��R�t�������܂����j�Z�����̂ɈӖ��͂���܂���B
�@���āA�����܂ŏ��w�Z�ƒ��w�Z�̈Ⴂ�������Ă��܂������A���͈�ԑ傫�Ȗ{���̈Ⴂ���܂������Ă��܂���B����͐e�ɂ͐�ɂ킩��Ȃ����ƂŁA�搶�ł��C�t���Ă���l�͏��Ȃ��ł��傤�B
�@����͉����H�́A����ɑ����B
�@
��106�b�w���w�֍s���N�ɇA�x
2006.3/30�f��
�@���āA�O��Ȃ����c�����܂܂́w���w�Z�ƒ��w�Z�̈�ԑ傫�ȈႢ�x�͂Ȃ�ł��傤�H����́A���w���͈�l�O�̑�l�����Ƃ������Ƃł��B�i���łɐe���q���̐e�ł͂Ȃ��A��l�̐e�����ł��j
�@����Ȃ��ƒm���Ă��A�펯�����B�d�Ԃ����āA���ꗿ�����đ�l�Ɠ���������B�g�������Ă������ꂳ��ɒǂ�������B�Ǝv�����x�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��B
���w�Z�ł́A�u�ł��邩�ȁH�ł����炢���ȁB�ł��Ȃ��Ă�����낤�ˁB�v�Ƃ����X�^���X�B���ׂĂ̂��Ƃ�搶�������Ă���܂��B���͂������A�����ʂ�A���ɉƂł̉߂������܂ŋ����Ă���܂��B����A�ۈ牀�̃o�[�W�����A�b�v�ł̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�i���w�Z�����ɂ��Ă���̂ł͂���܂���B���t�ł̃R�~���j�P�[�V�������܂��������Z�̎q���ɁA�W�c�����𑗂点��ɂ́A���ƍׂ��ɂ��낢��Ǝw�����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�ۈ牀�ƈႢ�A�����̐����̂��܂�̒��ŁA�����łȂɂ���������͕̂����̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B��Ԃƍ��C�͏��w�Z�̐搶����Ԃ��Ǝv���܂��B�j
�@���������w�́A�u�����܂ł��Ȃ��ł���Ɍ��܂��Ă�B���ʂɂ������w�͂����܂��傤�B�v�Ƃ����X�^���X�B
���́A�V�������Ƃ͋����Ă���܂����A���̊�b�ƂȂ�w�͂Ə���������̂��O��ł��B���������Ă����낤�H�Ƃ����ԓx�Ŏ��ƂɗՂ�ł͂����Ȃ��̂ł��B���w�̕�������E�ʂ������Ƃ�����̂́A���̑O�i�K���g�ɂ��Ă��炸�A�˘f���Ă��邱�Ƃ̕\���ł��B
�@�����ʂł��A�Ⴆ���H�̔z�V���@��A�|���̎d���͒m���ĂĂ�����O�B���X���[�Y�ɁA�m���ɂ��ɂ͂ǂ������炢�������A���������ōl����̂�������O�B
�@�Ƃł̐����Ȃ�Ċw�Z�������o���ׂ����Ƃł͂���܂���B�����ɐQ��Ƃ��A���ѐH�ׂ�Ƃ��A��炵�ēo�Z����Ƃ�������O�̂��ƂŁA�\��N�Ԃ̐����Ŏ����̐g�ɂ��Ă�����́B
�@�����̂��ƂɎ����I�Ɏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���́A�Љ�̃~�j�`���A�łƌ����Ă����ł��傤�B
�@���w����́A���܂ň���Ă�������}�����āA�Ԃ�����h�{��~���鎞���ƌ����Ă������ł��傤�B�y���k���A��������āA�����`�������Ă����Ƃ���ł͂Ȃ��̂ł��B�����܂ł͎����ł���ĂˁA�Ƃ����Ƃ���B
�@�ŁA���̕ӂ̂Ƃ�������͐搶�������������Ă��Ȃ��̂ł��B������搶����̗v���͍����Ȃ�A�q����ƒ�͌˘f���A���w�͌������Ƃ�����Ƃ��v���Ă���̂ł��B
�@�l�����璆�w�֍s���N�Ɂc�I���������ǂ���ɂ͈��S���Ē��w���ɂȂ�邾�낤�B�����Ƃ����Ԃ̎O�N�ԁA�\���Ɋy����ł���I
�@
��107�b�w�A���v�X�P���ځx
2006.4/21�f��
�@�O�������{�ɂȂ�܂��ƁA���悢��t�̍������Ă܂���܂��B�Ԃق���ђ��̂��A��R���X�Ƃ��Ă܂���܂��B����Ȓ��A�䂪�Ƃ͓~�^����i�H�j�̒����A���v�X�E����~�֍s���ė��܂����B
�@���Ƃ̂͂��܂�͒��j�̑��ƋL�O�ɁA�����̑c����������Ċ��ӂ̉���J���Ƃ������́B����ňꔑ���Ă�����āA�ǂ��������Ƃ���ɘA��čs���Ă��������ƍl���܂����B�����Ŏv�������̂������A���v�X�E����~�������̂ł��B
�����m�̂Ƃ������~�܂ł́A�o�X�ƃ��[�v�E�F�C�ň�N���o��܂��B����������~�ɂ̓z�e����X�g�������������Ă���̂ŁA�G�߂ɊW�Ȃ����R��̌��ł��܂��B���������͈�x�s�������Ƃ�����悤�ł����A���܂�̍��G�Ŏv���o���Ȃ��A��������͈�x���s�������Ƃ��Ȃ��B������͒��w�����������āA���[�v�E�F�C�̏�≺����͉��x���������Ƃ͂���܂����A����~�ɍ~�肽���Ƃ͂���܂���B�q���B��������̌��A�ꂳ�������m�̌o���Ƃ������Ƃł����B
�@���̓��͘[�̋�������ł�����̂������D�̐�R���a�B���t�̐��̑䂩��o�X�œo���Ă����܂��B���̃o�X���|���I�����R�����ԗփM���M���ő����Ă����܂��B�őO�Ȃɍ�����������Ǝq���B������̂͊R�̊O���B�����Ƃ��낪�����ȕ�����̓L���^�����k�ݏオ�点�Ă��܂����B
�@40���قǂŖ����炪��o�X���~��A��������̓��[�v�E�F�C�ŏオ���Ă����܂��B���Ԃɂ��Ă킸���V���̂��Ƃł����A���X�ƋG�߂͋t�߂�B�Ό���A��[���Ȃ��Ă����܂��B����~�͂�������~�B�i�����Ƃ��A�^�~�̐���~�͂����Ƃ������̂ł��傤���c�j�ϐ�͂R���[�g���B��ʂ̐ጴ������ɂ�����Ō����܂��B�{��������͂��̕x�m�R�����̌i�F�͂܂����������܂���B�}�C�i�X�W�x�̍����̐��E�A�u�}�C�i�X�W�x�Ȃ�Čo���������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ͂��Ⴎ���������ΈȊO�́A���X�Ƀ��X�g�����ɑޔ����܂����B
�������A����ŏI���Ă͕�����̖��܂�A�B���������ו�����g�їp�w����x���Ƃ�o���܂��B�����Ċ����̒��A�����S���Ō��R�Ɛጴ�ɔ�яo���܂����B
���̌�̓\���Ŋ���܂���܂��B�ʔ������`������̂��A�q���B������Ă��āA�ꏏ�Ɋ���܂���܂��B������������ꂳ����Q�����āA������J����܂����B�~�R�Ď�������Ɂu��Ȃ��̂ł�߂Ă��������v�Ƃ�����قǃA�N�e�B�u�ɂ�������\���܂����B�Ď�������́A�[�ɃX�L�[�ꂪ����̂ŁA�����ł��������ƌ����܂����A����~�ł�邩�炱�����l������Ƃ������́B�������댯�ƌ�����Ώ]����������܂���B�����ɁA������Ď����ɂނ���䂪�Ƃ̋L�O�ʐ^���B�点�ĉ��R���Ă��܂����B
�@��`�~�������˂��`�B
�@
��108�b�w���^���w�����ҁx
2006.5/3�f��
�c���c���Ǝv���Ă��܂������A�����𒅂Ă݂�Ƃ����̒��j������Ȃ�ɒ��w���̂悤�Ɍ����邩��s�v�c�ł��B����͒��w�Z�̓��w�����h�L�������g���Ă݂܂��傤�B
11��30���@���N�̓��w���́A�������ߌ�ɍs���܂����B���H���ς܂��Ă��������菉�o�Z�ł��B���o�Z�Ƃ����Ă����w�Z�͏��w�Z�ׂ̗ɂ���̂ŁA�ʊw�H�͏��w�Z�̂Ƃ��Ɠ����B10���قǂ̓����A������ƈꏏ�ɕ����܂����B���Z���Ă���ߏ��̏��w���ɉ�ƁA�����Ƃꂭ�������ɂ��Ă��܂������A�{�l�Ȃ�ɐ��ꂪ�܂����C�����������悤�ł��B
12��00���@���w�̌��ւŎ�t�ł��B���̍��ɂ͎��肶�イ�����̒m���������o�[����B�݂��ɐ����̑傫����ׂ����ă����b�N�X���[�h�B��t���ς܂��Ċe�����ɓ���܂��B
12��30���@�ی�҂͍T�����ő҂�����Ă��܂����A���̊Ԑ��k�����͊e�����ʼn��S�C���炢�낢��Ȏw�����܂��B���w���̒i��肩��A�����̒����Ȃ��̃`�F�b�N�A����̏��Ԃɕ��ԗ��K�Ȃǂ����Ă��܂��B�����āA�����������邳�����S�C�ɑ��āu���̐l���S�C�̐搶�ɂȂ�܂���悤�Ɂv�Ǝv����������ɂȂ�܂��B
13��00���@���悢����w�����n�܂�܂��B�܂��͐V��������B��g����g�����ɓ��ꂵ�܂��B���ꂳ�����ԓ������͂݁A�ʐ^���B������r�f�I���B������呛���B����ł��ߑO���ɍs��ꂽ���w�Z�̓��w���ɔ�ׂ�Ȃ�Ă��Ƃ���܂���B�܂��e���������Ă���Ă��Ƃł��傤�B���j�͓�g�B�g�����Ȃ̂őO����Z�Ԗڂ��炢�B���w�Z���w�̎��ɂ͂����납��O�Ԗڂ������̂ɁA�����������Ȃ������̂Łc�B
�@�����͕̂��ʂł��B�����E�����E�j���E���}�̌��t�ȂǁA���w���炵���l�R�Ɛi�ݖ������w�����I�����܂����B
13��50���@���j�̊w�Z�ł͈��������n�Ǝ����s���܂��B�V�C�E���̏Љ��A�Z���搶�̘b�ɑ����āA�{���ő�̃C�x���g�A�S�C���\���s���܂����B��g�͕�����Ɠ����キ�炢�̒j�̐搶�B����������̐搶�Ƃ������ƂŁA���j�I�ɂ͂Ȃ����͋C�B�u���̐搶�Ȃ�A�܂����ɋV���邱�ƂȂ��������Ă����邩�ȁB�v�Ƃ����̂�������̊��z�B
14��30���@�����ɓ����ĒS�C�̐搶�̘b���܂��B�V�������ȏ������炢�A�c��Ȕz�z�������܂��B���w�Z�ƈႢ�A��o���̏�������o�����͐��k�������Ă����Ă���܂��B���̊Ԑe�͘L���Ŗ������߂����܂��B����㋳���ɖ߂�ƁA���k�Ɛ搶�����ɒ��ǂ��Ȃ��Ă��Đe�Ƃ��Ă̓z�b�Ƃ���Ƃ���ł��B
�u�܂��܂����ȁv�����j����ڂ̊��z�B���ė�������ǂ�Ȋw�Z�����𑗂��Ă���̂��A�͂܂�����ȍ~�ɁI
�@
��109�b�w���[�_�[�x�@�@
2006.5/11�f��
�@���쏭�N���R�̉Ǝ�Áw�t�̖�R�ŗV�ڂ��I�R�؍̂�ƎR�Ă�Ղ�E�C�`�S���x�Ƃ�����Ɏ��j�ƎQ�����Ă��܂����B
�@�����Ȃ炱�������w�Z�o�R�Ŕz����r���Ȃ�āA�������Č������Ȃ��Ŏ̂ĂĂ��܂����j���A�ǂ������킯������͉ƂɋA���Ă���Ȃ�u������A�l����ɍs���Ă������H�v�ƕ����Ă��܂����B���Ă݂�ƑO�q�̈��쏭�N���R�̉Ƃ̃r���������킯�ł��B
�@���e�͖`���ɋL�����\��ǂ���̂��́B�����ł͂���܂��A�����قǂ̍��z�ł�����܂���B�Ƒ��̗\��\�Ƃ����킹�āA������肪�Ȃ������̂ŁA�Q�����邱�Ƃɂ��܂����B�i���w�ɓ��w�����Ă̒��j�́u������肵�����v�Ƃ������R�ŕs�Q���A�ꂳ������j�ɕt���Y���ĕs�Q���B�j
�@���������B���������ǂ�قǂ̐l�����Q������̂��Ǝv�����쏭�N���R�̉Ƃɂ��Ă݂�ƁA�������l���B���������قǂ̉Ƒ��ł����ς��B�Ƒ����o�͂������A�O����ŎQ���Ƃ����Ƃ�������\����܂����B
�@�܂��͔ǂ��Ƃɕ�����Ċ獇�킹�ł��B�䂪�Ƃ��������ǂ́A����E�N���{�[�C�Y�̂���l�l�Ƒ��ƁA����E�N���K�[���Y�̂���l�l�Ƒ��Ƃ̌v�\�l�̔ǁB���ȏЉ�ɑ����ČW���߂����܂��B�W�͎q������́A�e�͂��̃T�|�[�g�ł��B�q���̒��ł͎��j����ԔN��Ȃ̂Ŕǒ��ɗ����B�����v�ŏ��F����A����ȍ~���j�͂����Ɓu���[�_�[�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���H��H�ׂ��悢��t�B�[���h���[�N�ɏo���B���j�Ə���{�[�C�͂��łɈӋC���������悤�ŁA�u���[�_�[�v�u�A�C�{�[�v�ƌĂэ����Ă���ꍇ���Ȃ���R�؍̂�ɋ���ł��܂����B
�@�O���ԂقǕ�����������ƁA���x�́A���܍̂��Ă����R���Ă�Ղ�ɂ��A��ᴂŐ��������тŌܕ��݂����܂��B���[�_�[�̎w���̂��ƁA���܂ǂ��E���̗p�ӁA�H��̏����Ȃǂ��Ȃ���܂��B�o���L�x�ȃ��[�_�[�̕��̏����������āA�䂪�ǂ͏����Ɏx�x���i��ł����܂����B�i�r���A�����Ȏq�������̂����Ƃ��Ă������ڂ����ėV��ł������[�_�[���A�{�C�ʼnB��Ă��܂��A�݂�Ȃő{������Ƃ����n�v�j���O������܂������c�B�j���������ł����H�����݂�ȂŐH�ׁA��Еt�������āA�h�ɂɖ߂�܂����B
�@�h�ɓ��ł����[�_�[�͊撣��܂����B�q���������w�����ăx�b�h���C�N��������A�h�ɒ��呛�����Ă̒T������������悵���肵�Ă��܂����B
�@�������A���H�E�V�����U��E�C�`�S���Ɣǂ̎q�������𗦂��ĐϋɓI�ɍs�����܂����B
���ʂ��Ŕǃ����o�[�̕ی�҂�����u���[�_�[���肪�Ƃ��ˁv�Ɗ��ӂ����قǑ劈��ł����B
�@�Ƃł͂��܂߂̎��j������ȂɃ��[�_�[�Ƃ��Ċ撣���Ȃ�āA��������r�b�N���̓���Ԃł����B
�@
��110�b�w�t�@�[�u�����N�x
2006.5/30�f��
�@���j�̍��N�x�̏h��ɁA�u���ł����L�v�Ƃ����̂�����܂��B���ʂ̓��X�̓��L�ł͂Ȃ��A�������l�����e�[�}�̂��Ƃ��G���L���ɏ����Ă����Ƃ������̂ł��B���j���I�e�[�}�́w�����̊ώ@���L�x�ł����B�ƌ����Ă��A�ċx�݂̒��̊ώ@�L�^�݂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����Ⴄ�����������ċL�^�����Ă����Ƃ������̂ł��B�ŋ߂ł����g�����Ȃ�A�����������ɓ����o���A�����炶�イ�Ō�������悤�ɂȂ�܂������c�B
�@���������A����������炵�Ă��邱�̂�����ɖ����ώ@����قǑ����̎�ނ��������Ă���̂ł��傤���H
�@���j�������̊ώ@���L���n�߂������͎������^�I�ł����B���������j��������R���삯�������āA���炩�̍��������܂��Ă���̂����āA�u�g�߂ȏ��ɂ���Ȃɒ����Ă������ȂȂ��v�Ƌ����Ɗ��������܂����B
�@���Ƃ��ƍ������D���������̂͒��j�ł��B���w�Z��N�����牜�{��O�Y�̃t�@�[�u�������L�S�����i�ʏ�͏��w�Z���w�N�Ώۂ̖{�j��ǂ݁A���ނ������������̖��O����������m���Ă��܂����B����������ɂ��̋����́A�������̂���A�����̐��ԁ��������̕s�v�c�����R�̐_�遨�T�C�G���X�̖��͂ւƈڂ��Ă����܂����B���܂ł��Ȋw�D�����N�ł����A�������̂ɂ��Ă͂��܂获���͂Ȃ��悤�ł��B
�@����Ƒ����ď��w�Z��N�����牜�{��O�Y�̃t�@�[�u�������L��ǂݎn�߂����j�͍��������M��ԔM���Ƃ��Ȃ̂�������܂���B�N���X�ɂ�����l����炵���������N�ƁA���������悤�ɍ����M�����߂Ă���悤�ł��B�������ʂ̒��D�����N�ƈ���ĕ߂܂��Ď������Ƃɂ͋������Ȃ��A���܂��Ă��鍩��������Ɓu���킢�������ˁv�Ƃ������炢�ł��B�i���N�܂ł͎����ł������ς����������āA���Ȃ��Ă������Ƃ͂����߂����������Ƃ炵���B�j
�@�D���ȏ��ł����ƍb���ށi�J�u�g���V��N���K�^�̒��ԁj����Ԃ̂悤�ł����A�̏W�̓���⍑���Y���O���Y�ɔ�ׂč��ЂƂn���Ȋ��������邱�ƂȂǂ���A���S�������͖̂I�⒱�̂悤�ł��B����̓I�I�X�Y���o�`�̏����I�i�̒�10�p��̑啨�B��l�����Ă�������ƃr�b�N����������㕨�ł��B�j�������ÁX�Ɍ��Ă��܂����B
�I��������X�����i�Ă�ł����ނ��{���͂����ƍו�����Ă��Ė��O�����G�ł��B�����Ɂu���ꁛ���`���E�ł���B�v�Ƃ������Ɓu�Ⴄ��B�I�I�����~�~�����`���E����B�v�Ƃ��u���ɒ�������Ă��܂��܂��B
�@���N���ɒN������x�͜��t�@�[�u���M�A�Ђ��Ă����̂������Ƃ����Ԃł��B���܂ő�����������܂��A����܂ł͎������č��M���o�������ł��B�i����������ƍ���Ȃ��c�B�j
�@
2006.6/13�f��
�@�ً}���Ԕ����I�������C�ȕ����Q�����蒆�N�ɁI
�@109�b�ŏЉ���A���쏭�N���R�̉Ǝ�Áw�t�̖�R�ŗV�ڂ��I�R�؍̂�ƎR�Ă�Ղ�E�C�`�S���x�Ƃ�����ŁA����ԂłT���Ԃقǃt�B�[���h���[�N�ɕt���������������������́A��J���M�b�N�����ɂȂ��Ă��܂���T�Ԃ̔��Q�����萶����]�V�Ȃ�����܂����B
�@�ŏ��̎O���Ԃ͐Q�Ԃ肳�����Ă����͂ŗ����オ��ɂ́A�ɂ݂ɑς��Ȃ���T�������ė����オ��Ƃ�����Ԃł����B�l���ڂ��炢����́A�P�����炢�ŗ��Ă�悤�ɂȂ�܂������A���E�w�ɑS���͂����炸�A�̂��x���Ă������Ƃ��ł��Ȃ��̂ō����Ă��邱�Ƃ��ł����A����ς�Q���܂܉߂�������܂���ł����B��T�Ԃقǂł��܂藧���łȂ�Ƃ�������悤�ɂȂ�A�ӂ��[�ӂ��[�����Ȃ���H���̗p�ӂ͂ł���悤�ɂȂ�܂����B�Љ�A�ł���悤�ɂȂ�܂ŁA���̌�20�����炢������܂����B�Ⴂ���̂悤�ɂ͉��Ȃ����A�f�v���ǂ��ɂ��s���Ȃ����A�U�X�ȍ��ɂł����B
�@�����A��v�ł��镃���Q����ł��܂��ẮA�ƒ�̒����܂��܂���B����Ȏ������Ƒ��̋��͂ƒc�����K�v�Ƃ���܂��B
�@�����͒����X�ɏo�����Ă����A�x���Ȃ�܂ŋA���Ă��Ȃ��ꂳ�A�����G���������Ă����̂͗\�z���Ă͂��܂������A�ӊO�ɂ����j���悭�����Ă��ꂽ�̂ɂ̓r�b�N���ł����B
�@���N����Ƃ܂��u��������v�H�v�Ɛ��������A�X���b�p�𑵂��A���Y���K�i���ꏏ�ɍ~��Ă���܂��B���H�̋����𒍂��ł��ꂽ��A���ւ�������Ă��ꂽ��B�����͂��肬��ɓ{���Ȃ���w�����Ă��܂��x������̂ɁA�������Ǝx�x�����ēo�Z���Ă����܂��B
�@�A��������܂��u�����q�͂ǂ��H�v�ƕ����A���H��̐H�킪���ꂸ�ɂ��̂܂ܗ����ɕ����Ă���̂�����ƁA�ق��Đ���Ă���܂��B�����Ȃ��Ă����C�|�����I��点�A�����̏h������������ɕ�����̂��ɗ��ĉ����ƋC�����Ă���Ă��܂����B
�@������j�́A���w�Z�̐����̃��Y���ɂȂ��Ȃ����ꂸ�A�܂�������ɂ��܂��Ă���]�T���Ȃ���ԁB�킪������Ă���̂��ǂ����Ă����̂��킩��܂��A�����ƕς��ʐ��������Ă��܂����B�i���m�ɂ����ƁA�����͂��낢�낤�邳���������ƂȂ������Ă���̂��������ƂɁA����������Đ������Ă��܂����B�܂�����ȋ@����A���j�ɂƂ��Ă͂�����Ƃ����������ɂȂ�����������܂���B�j
�@���āA���N�������Ƃ͂������̂́A�������ɂ���������݂̉䂪�ƁA�����҂̎��j�͂ǂ��H�D���������Ƒ��͂ǂ��H����̌����Ƃ́A������̂ł��Ȃ��c�B
�@
��112�b�w�T�����x
2006.7/21�f��
���w���̏T���Ƃ����܂��ƁA����͂����������Ɍ��܂��Ă��܂��B
�����̒��j����N�x�܂ł̂悤�ɁA�Ƒ��ɕt�������ėV��ł邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂����B
�e�I�ɂ́A�x���͈ꏏ�ɉ߂����������A�Ƒ��Ƃ��Ď��g�݂������Ƃ���������܂��B���ʎ������������������̂��Ƃ��v���o���ƁA���T�������ɑł�����ł��܂����B���k�����ɂƂ��Ă��w�Z�����̒��ōł���M���X����͕̂������ŁA�y�����M�S�Ɏ��g��ł����悤�Ɏv���܂��B�ł��̂Œ��j�����Ă����Ă����̂𗊂�����������Ă������ł��B
�@���āA���S�T�x������ɂȂ��Ă���T���̕�������������ƕςȂ��ƂɂȂ��Ă���̂͂����m�ł��傤���H
�@����W�̂���[���Ƃ��납��A�u�T���̂����Œ����͕��������x�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����B�����o�Ă���̂ł��B�ł͎����͂ǂ����Ƃ����ƁA�O�q�̂Ƃ���i���j�̊w�Z�����ł͂Ȃ��A�����炭���쌧���イ�̒��w�Z�Łj�y�j�E���j�Ɠ���Ƃ��������s���Ă��܂��B�ǂ��������炭��Ȃ�ł��傤�H
�@�ȒP�ɂ����ƁA������͎Љ�̈�Ƃ������O����Ē��w�Z�̕��������s���Ă���̂ł��B�i���̂��Ƃ́A����W�̂���[���Ƃ��낾���Ēm���Ă���ɈႢ�Ȃ��ł��傤�B�j���̂����ŁA���K�����́������w�������w�Ƃ͌������A�����W���j�A�N���u�����X�|�[�c�N���u�Ȃ�Ă��ƂɂȂ��Ă��邵�A�����͕ی�҂������̎q��������}������w�������̂Ƃ��x�ǂ�����Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��邵�A�ʂĂ͈����v�悳���ی�Җ��ŏo�����ނ��Ⴍ����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��B
����W�̂���[���Ƃ���́A��������Ԃ��ׂ��ĎЉ�̈�Ɋ��S�ڍs���Ă��������ӌ�������悤�ŁA���̏ɂق�������ł���̂ł��傤���A������Ă��������Ȃ��ł����H
���w�Z�̊e��̈���́A���̘A�i���w�Z�̈�A���j�Ƃ����S���g�D�������āA���̂��ƂɊJ�Â���Ă���̂ɁA���������w�Z����藣���Ȃ�Ė������炯�ł��B���ƐӔC�̂����邱�Ƃ��A�n��ɉ�������ۓ����ɂق��Ȃ�܂���B
�@�ƁA�����Ő����r���Ă݂Ă����܂���ʂ͂���܂���B�Ȃ��Ȃ�e�w�Z�̍Z��������W�̂���[���Ƃ���̌����Ȃ肾����ł��i��X�o���ɋ����炵���j�B���ۂ̊����͖ٔF�i�����H�j���Ȃ��炨��m��˂��ƌ�������܂��B��l���炢�́u�����̊w�Z�͏T�����A�x���v�������蕔���������B�Љ�̈�ɂȂC���Ă����邩�B�����ĕ������Ŋw�Z��グ�A�n��Љ�܂ł������������Ă݂���B�v�Ƃ�����̑傫�ȍZ���͂��Ȃ��̂ł��傤���i�����������Z���͑����j�B
�@����ȍZ���̂���w�Z�Ŏ����ږ�����Ă݂��������Ȃ��B
�@
��113�b�w�q�[�}�̋x���x
2006.8/6�f��
�@�O�T�A���Ō��j���A�Ƒ��̒N�����x�݂ŁA��l�ʼn߂����Ƃ����������̌������܂����B
�@�܂���T�ڂ͕ꂳ��B�y�j���ɑ̌��w�K���������U��ւ��Ƃ��āA���j�����x�݂ɂȂ�܂����B�ꂳ��Ɠ�l�̋x���́A�̂��v���o���i�H�j�f�[�g�ł��B
�@�����͌����Ă������̂ɂ͖߂�܂���B�V���b�s���O�ɍs���Ă��A���q���B�̗m����T���Ă��܂�����B���������݂Ȃ���������ďo��͎̂d���̋�s��������c�B����ł��q�������ʼn߂��������Ԃ͂ǂ����V�N�ł���A��������������Ƃ��������ł��B����������������Ԃ��������Ă�����Ȃ��Ǝv���܂����B
�@��T�ڂ͒��j�Ƃ̋x���B���w�Z�����ɂ͊���Ă������̂́A�y�j�E���j�Ƃ����ƕ������ɂ����Ă��܂������̑����Ă������j�B�v���Ԃ�̋x���ɏ����˘f���C�����B�܂��A������҂��l�ɂȂ��Ă��āA������Ɠ�l����Ƃ����̂��Ȃ��ӎ�����̂��A���ʉ������Ȃ��x����I�����܂����B
�@���낢�남�o������V�т��Ă��܂����A�u�h�肪���邩��v�Ƃ��u�C����Ƃ��Ȃ���v�Ƃ������ĉƂʼn߂����܂����B�����͎��j�̗����ł�����蕃����ƃL���b�`�{�[����Q�[���Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂ŁA�����������Ƃ���肽���ƌ����̂��Ǝv���Ă����̂ł����A�ז��ł����C�o�������Ȃ��Ƃ�肪�����Ȃ��݂����ł��B���ǂ������͂���ꏏ�ɐH�ׂɍs���������ŁA���Ƃ͕��}�ɁA�̂�т�Ɖ߂���������ɂȂ�܂����B
�@�ΏƓI�ɂ���ł����Ƃ����قǂɐ��肾������̋x�����߂������̂��O�T�ڂ̎��j�ł����B
�@����Ԃ��獩���̏W�ɂ����킳��܂��B�F�B�ɕ����Ă����Ƃ����߂��̐X�Ɏ��]�Ԃōs���܂��B�R�ɕ�������ړI�̖�������܂ł͎��������ł��ł��܂����A���R���ăN���K�^�E�J�u�g�𗎂Ƃ��ɂ͂�͂蕃����̃p���[���K�v�Ɠ��s���肢�o���悤�ł��B�i������p���[�S�J�ŃL�b�N���܂���܂������A�c�O�Ȃ���A���̓��͂Ȃ�ɂ��߂܂��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�j
�@�����ʼnƂɖ߂�Ԃ��Ȃ��K�̎��̂�Ɍ������܂��B�����O�����u�R�ɌK�̎����Ȃ��Ă���̂������v�Ƙb���Ă����̂��o���Ă��Ẵ��N�G�X�g�B���������ς����킢�܂����B
�@���̂��Ƃ��A�v�[���E�������E�T�b�J�[�E�L���b�`�{�[���Ƌx�ފԂ��Ȃ��V�т܂���܂����B�����ėV�т����ł͂Ȃ��A�Ō�ɔӂ��э����ꏏ�ɂ��܂����B�n���o�[�O���ɒ��킵�A���܂˂���������A�������肱�˂���劈��B�������T���_�□�X�`�������������āA���j�ƕꂳ���҂��Ă��܂����B
�@�O�ҎO�l�̊y�����x���ł������A����ς�l�l�ꏏ�̂��x�݂���Ԋy�����Ȃ��B
�@
��114�b�w���̂��D�ݏĂ��x
2006.8/19�f��
�@���N�̉ẮA�L���ւ̗��s���v�悵�܂����B���w���̒��j���A�������C�ɂ����x�߂�͍̂��N���Ō�Ǝv���A���o�̌v��ł����B
�@���āA����͕����̂������A�Z���l���s�O���̌v��B�����Α�̋��s���o�����܂��B���s�w����V�����ōL���ցB�V�������̌��̎q���B�́A�z�[���ɓ�����������L�O�ʐ^���B������ԑ̂ɐG���Ă݂��肨���͂��Ⴌ�B����Ă�����g�C���T�K��O���[���Ԍ��w���A�ɂ��₩�ȓԂ��߂����L���ɒ����܂����B
�@�L���́A�����I�A��40�x�߂������ŁA���̗��s���{���ɑ�ςł����B����Ȓ��A�L���錩�w���ς܂��A���̗��s�̖ړI�̈�A�L�������D�ݏĂ���H�ׂɍs���܂��B
�@���D�ݏĂ����͂������������ɂ���܂����A���܂�̏����ɔY��ł���ɂ͂���܂���B��߂ȓX�ɔ�э��݂܂��B
�@�S�̑O�ɂ��Ԃ���A�u�������n���˂��v�u�L���x�c�͑吷���v�u�Ă�������������Ă��v�Ƃ��A���邳�����Ȃ��炨�Z����̂�����݂�q�����܂����B������i�ŁA�L���X�łȂ��̂�������܂��A�喞���̐H���ɂȂ�܂����B
�@�ߌ�͍���̗��s�̍ő�̖ړI�n�A���a�����ł��B61�N�O�Ɠ������炢�̖ҏ��̒�������A�؉A�������Ȃɂ��Ȃ��X��z�����Ȃ��猴���h�[���E�����w�k�ԗ쓃�E�����̎q�̑��E���a�̓��E�������v�҈ԗ������ĉ��܂����B�����Ă��悢�敽�a�L�O�����قɓ���܂����B
�@���w��N���Ə��w�O�N���Ƃł͊����邱�Ƃ͈Ⴄ�ł��傤���A�܂�������Ȃ����Ƃ������ł��傤�B�ł��Ⴂ���A�ߎS�Ȑ�Q��m��A���a�̋M�d����S�̂ǂ����ɗ��߂Ă��炦��Ώ\�����Ǝv���Ă��܂��B���w����A��l����́A�e�₶���̌��t���肽���z�����܂��o�܂���ł������A����̐l���o���̒��ŁA�����̌��t�Ŋ��z�������Ă���邱�ƂƎv���܂��B
�@�h�ɓ���̂�т育�т�H�ׁA��̎U���ɏo�܂����B�܂��܂��������̂́A���Ƃ͈Ⴄ�������܂��������镽�a����������A�����h�[���܂ŗ����Ƃ��̂��Ƃł����B�����߂����烉�b�p�Ƒ��ۂ̉����������Ă��܂����B�s�������Ƃ̂�����ɂ͂�������ł��傤�A�����h�[���ׂ̗͍L���s������Ȃ̂ł��B���̓��͍L���|���N���g�킪�s���Ă���A���̐���オ�肪�R��Ă��Ă����̂ł��B�����r���ɂ�������炸�A�싅�D���̕����u���Ă������H�v������邶�����ɋA���A�ꂳ��Ǝq���B��������ē��ꂵ�܂����B���t�g�őO�Ȃɂ��Ԃ���A����̕��͋C�ɍ��킹�āu�O�c�`�撣��[�v�Ƃ�����Ă��܂����B
�@�v�������ʏ[����������߂�����������͑喞���ŁA���D�ݏĂ��̍������v���o������ɂ��̂ł���܂����B
�@
��115�b�w���̂��݂��\���x
2006.8/29�f��
�@����ڂ́A�L�d�ɏ���ċ{�����������Ƃ��납��n�܂�܂��B�i�O��̑����j��������A���D�ŋ{���ɓn��܂��B
�@�{���Ƃ����Ζ��ق��݂��\���ł��傤�B�����Ȑ������ƁA�̔��X�����藐��A�ǂ̏��i�����������̂�炳���ς蕪����܂���B����͕Ђ��[����H�ׂĂ݂���Ȃ������ł��B
�@�H�ׂĂ݂܂����B���ʁA��܂����̂ӂ��̂�������Ԃ����������Ƃ������B�ς���Q�͂���ς�E�P�˂炢�̊�������܂����A���Ђ̂��͎̂��Ԃ����Ƃӂ��芴�������Ă��܂��܂��B���o�����\��̂�����͂��Ђ��Q�l�ɁI
�@���āA������悭�H�ׂ�䂪�Ƃł��A���ł���ȂɐH�ׂ܂��邱�Ƃ��ł����̂ł��傤�B����͏����I�{�������������B���X�X�ɓ���ƁA�������������[������o���A�₽�������ŗU����B�T���Ɛi�܂Ȃ������Ɏ��̓X�ɓ����Ă��܂��Ƃ����d�|���B�䂪�Ƃ͑S���Ō����ɍ��Ɉ����������Ă��܂����킯�ł��B�ł��̂ł��݂��\���ɂƂǂ܂炸�A����Ƃ�������̂�H�ׂ܂��邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�L���Ƃ�������ς色�y�B�G�ߊO��Ƃ͂����A�Ⓚ�Z�p�̔��B���������ł͔N�����܂����y��H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�X��ł����ɂ����������ďĂ���Ă��܂��ƁA����ł��H�ׂĂ��܂��܂��B���y�����ł͂��т����̂ł��łɃr�[�����c�B
�@�����Ƃ��͂���ς�A�C�X�N���[�����H�ׂ����Ȃ�܂��B�o�j�������łȂ��A����������낢��Ȏ�ނ�����A�����H�ה�ׂ����Ă��܂��܂��B�u�{������v�ȂǂƏ�����Ă���Ƃ����~�߂悤������܂���c�B
�@�������͂�͂���ς�A�i�S�тł��傤�B������X��ł����ɂ����ŗU���Ă��܂��B����H�ׂĂ���ɂ�������炸�A�t���t���ƐH���ɓ����Ă��܂��܂��B���j���[�ɏĂ����y�������Ă܂��������Ă��܂��܂��B���`�����H�ׂ��Ȃ��A�ł����������c�B
�@����ȏ�Ԃł�������300���[�g���قǂ̏��X�X����̂ɎO���Ԉȏォ�����Ă��܂��܂����B
�@����ƌ����_�Ђɒ����A���ɐZ��Гa�����w�B����ɖ�R�o�R�A�����ٌ��w�����A�h�ɓ����B
�@�h�ɓ���̂�т育�т�H�ׁA��̎U���ɏo�܂����B�܂��܂��������̂́A���Ƃ͈Ⴄ�������܂��������錵���_�Ђ܂ŗ���Ƃ����Ԑ��������Ă��܂��B�T���_���E�Z�p���̕�����͈�l�����Ɍ������ĕ����o���܂����B�G���z���邠����Œ����ɂ��ǂ蒅���K�b�c�|�[�Y�I�q���B�ɂ����܂������܂����B�i�����������̊������ɁA�݂�ȕ����Ă��ǂ蒅�����̂ŁA�������l�̗D�z���͒����͑����Ȃ������j
�@�v�������ʏ[����������߂�����������͑喞���ŁA�Ă����y�̍�����v���o������ɂ��̂ł���܂����B
�@
��116�b�w��̊⍑���i�x
2006.9/8�f��
�@�O���ڂ́A�A���D�ɏ���ċ{�����������Ƃ��납��n�܂�܂��B�i�O�X��̑����j��������R�����⍑�ɓ���܂��B
�@�⍑�Ƃ����ёы��ł��B�R���̊⍑����o�b�N�ɁA�ܒi�̔��������̎p�́A������I���ϒn�x�X�g�R�ɓ���܂��B����킴�킴�����܂ő���L�����̂��A������̋����v�]�ɂ����̂ł��B
�@�����ёы���n���āA�܂��͔��ւ����ɍs���܂��B�A�I�_�C�V���E�̃A���r�m�炵���ł����A�����ɂ����肪�������ł��B��������q��ł����܂����B���Ƀ��[�v�E�F�C�Ŋ⍑��ɍs���͂��������̂ł����A���܂�̏����Ƀ_�E���B������Ƒ����ł����H���ɓ����Ċ⍑���i�𖡂키���ƂɁB
�@�⍑���i�͑傫�ȉ��ŁA���i�ɂ��d�˂č�鉟�����i�ł����A�q�Ȃɏo�Ă���Ƃ��ɂ͎ʐ^�̂悤�Ȏp�ɂȂ��ďo�Ă��܂��B���͂��܂���i�т��ۂ��Ȃ��A�ق�̂�Â݂����Ă��Ă�����ł��H�ׂ���悤�Ȋ����B������ؖ����邩�̂悤�ɕ����O�A���j���������肵�܂����B���܂��ɓy�Y�Ɏl�������Ă��܂��܂����B
�@���s���O���ڂɂȂ�Ƃ����Ԕ��Ă��܂��B���c�̌��ʁA�⍑��̓p�X���邱�ƂɌ��肵�܂����B�߂��̕��������Ő����тɕύX�B�����100��ނ̖��������Ƃ����\�t�g�N���[�����ŗ����Ƃ�܂��B
�@�Ō�ɋёы���߂�A�͌��ɍ~��ċѐ���y���݂܂��B���̏ォ�炢���ς����������Ă������A����鐅�͂����ɂ����������ł����B�C��E���Ń`���v�`���v������肾�����̂ł����A�A�N�V�f���g�����I���j�����̒��ɓ]��ł��܂��܂����B���Ԃʂ�ɂȂ������j�͊J������܂����B�ǂ����G�ꂿ���������ƃW���u�W���u���ɓ���A��ʼnj���n�߂܂����B��܂ł����Đ����ʼnj�����j�̎p�͂Ƃ��Ă��C�����悳�����B�܂˂��ĉj�������Ƃ���ł������A���낢�뎖����l���Ď��d���܂����B����s�����Ƃ��������琅����Y�ꂸ�Ɏ����čs�������Ƃ���ł��B
�@�����A����̗��s�����낻��I���ł��B�V�⍑�w����V�����ɏ���ċ��s�ɖ߂�܂��B�V�⍑�w�ł́A�{������厖�Ɏ����Ă������݂��\���������Ă��ăV���b�N������A���Ȃ������ς��Ȃ̂ɂ���ς�w�ق�����A�q���B�͑ҍ����Ŗ��c�̑化�܂����Ă����肵�܂����B
�@�V�����̒��́A���ĐQ�ċA��̂��ȂƎv���Ă��܂������A�w�ق�H�ׂ���A�ԓ��̔��ł�������肵�Ċy�����߂����܂����B
�@�Ԕ���A�ꓯ���ʂĂĉƂɒ����܂����B���������Ȃ��炨�y�Y�̂��݂��\�����ق���܂��B���a�����⌵���_�Ђ̑��d�����v���o����܂��B�⍑���i���H�ׂĂ��܂��܂����B�ёы��̉ؗ킳���v���o����܂��B
�@�{���ɏ������s���������ǁA�{���ɖ{���Ɋy�������s�������B
�@
��117�b�w�o���Z�x
2006.9/26�f��
�@�����w�����o���Z���ɔ�Q�ɑ����Ƃ������������{�e�n�Ŕ������Ă��܂��B����͑�s�s�������ɂƂǂ܂炸�A�n���s�s�E����ɂ͓c�ɂɂ܂łɍL�����Ă���g�߂Ȗ��Ȃ̂ł��B
�@���������킯�ŁA�킪���쒬�ł����l�̎������������Ă��܂��B�K���i�H�j�ɂ����̂Ƃ���l���Ɋւ��悤�ȋ����Ȏ����͔������Ă��܂��A����Ȃ��̎���d�Ȃ��̂ł�����A���S���Ă���ꍇ�ł͂���܂���B������݂Ŗ{�C�Ŏ��g��ł��炦��Έ�Ԃ����̂ł��傤���A���ꂱ���l���Ɋւ��悤�ȋ����Ȏ����ł��N����Ȃ�����{�C�Ŏ��g�܂Ȃ��̂��������ł��B����ɂ��Ă��Ă����������Ȃ��̂ŁA�e�ƒ�Ŏ����̉Ƃ̎q���B���댯������Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�K���ɂ��䂪�Ƃł́A�����q�}�����Ă��܂��Ă��܂�����A�o���Z�Ɋ��͂����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���͊w�Z�܂ňꏏ�ɍs���i���͕�����̉^���s���������ړI�������肷��j�A�Z��܂Ō�����܂��B�G�߂̈ڂ�ς����Ƃ��ɖ��킢�A�쓹�̓`���I�ȗV�тȂǂ�`���Ȃ�����A���͂ɋC��z��Ȃ�������Ă����܂��B
�@���Z������������U���̎��Ԃ��q���̉��Z�����ɍ��킹�A���肰�Ȃ��l�q�������܂��B�܂����Z�͂������������œ�����H���Ȃ���A�Ԃ����������ċA���Ă��܂����炸���ƌ��Ă���킯�ɂ������܂���B����ł��A�ʊw�H�Ɍ��m��ʎԂ��~�܂��Ă��Ȃ����Ƃ��i�����������璆��`������Ńi���o�[���`�F�b�N���Ă����܂��B�J�����Ńp�`�����ǂ����ł��j�A�q���̂��悻�̈ʒu��c������Ƃ��A��l�̖ڂ����邱�Ƃ����`����Ƃ��A���낢���ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B
�@���̂����ɁA�q���̂��F�B�̊�▼�O�₻�ꂼ��̊W�Ȃǂ������Ă��܂��B���ɉ��Z���́A�w�Z�Œz�����l�ԊW�̒��ǂ�����ƈꏏ�ł����猩��ׂ����̂����肾������B�Q�ϓ������ɗ����Ƃ��������ł��B
�@�o���Z�������̂͂n�j�ł����A�Ԃő��}������̂͂m�f�ł��B�o���Z���厖�Ȋw�K�̎��Ԃł����A�����ɂ��킹�Ďx�x������̂��厖�Ȑ����P���ł��B���������������Ǝ��̂ɂ��Ӌ`������̂ł��B�i���̖��ɂ��Ă͂܂������������߂܂��āI�j
�@���Ă�����̂��ƁA�w����̊댯�}�b�v���z���܂����B���R�䂪�Ƃ̋ߏ����猩�Ă����킯�Łu�����A���̋߂��ɂ��ώ��ҏo�v���B�ȂɂȂɁA�w�����E���k�̓o���Z���ɂ��炵�Ȃ��i�D�Ńt���t�������Ă��钆�N�̒j�B�J�����������Ă��邱�Ƃ�����A�~�߂Ă���Ԃ̒���`�����肵�Ă���B���x�������~�܂��Ď����E���k�̕��������ƌ��Ă��邱�Ƃ�����B�x�Ȃ�قǁA�������Ȃ��v
�@�����H������Ăǂ����Ă����̂��Ƃ����I
�@
��118�b�w����T�_�x
2006.10/4�f��
�@����͖ʔ����ł���܂��B��ꂽ�S����y�ɖ����ɂ̓s�b�^���ł���܂��B
�@����ł́A����ƂЂƂ�����ɂ��Ȃ��ŁA�e���r����̓A�j���A����{�̓R�~�b�N�Ƃ����ĕ����Ă���悤�ł����A�����ł͂܂Ƃ߂āw����x�ł��������Ǝv���܂��B
�@����̑P���ɂ��Ă͊e���Ř_�����Ă��܂��̂ŏڂ��������܂��A������I�ɂ́w��{�I�ɑP�B�ߏ�Ȑێ�ɂ�鎞�Ԃ̘Q����x���ƍl���Ă��܂��B�������قǂقǂ��̗v�Ƃ������ƁB
�@�ߔN�u�Ǐ��������������i�ǂށj�ق����]�������������v�Ƃ������|�[�g�����\���ꂽ��A����Œm������_�������̂�A���앶�w�̖��扻�Ȃǖ��敜���̒���������A�����ɖ��恁�q���̂��̂Ƃ����}�����������悤�Ɏv���܂��B
�@������Ԗ���̂������������Ă���̂́A�G�̍̑��u�Ԃ̕K�R���B����̈�R�}�����̏u�ԂłȂ���Ȃ�Ȃ����R���l���邱�ƁB��ォ�瓍������Ă���Ƃ��̊G�́A���͂ǂ̂��炢���݁A��������Ƃǂꂾ������Ă��āA��ʂ͂ǂ�قǂ����Ȃނ̂��H������l���Ȃ���ǂނƂQ�y�[�W�Ōܕ��͊y���߂܂��B
�@�䂪�Ƃō��A��ԏ{�Ȗ���́i�`��������ǂ�ł킩�����l�̓c�E�j�P�����R���Ƃ�������B���쌧�ł͖����a�r�ł����������Ă��Ȃ��̂ŁA�e���r�Ō������͏��Ȃ���������܂���B�������A���Ȃ�L�����N�^�[�O�b�Y�Ȃǂɂ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�G������u�����A���ꂩ�v�Ƃ��������ł��傤�B���j���A���F�B�̉ƂŃr�f�I�������Ă��炢�C�ɓ����Ă��܂������́B�Ƃł�����ɐ�`����̂Ńr�f�I����Č��܂����B�������납�����I����ȗ��P�����u�[���������Ă���ł���܂��B
�@�䂪�ƂŃu�[���ɂȂ邽�߂ɂ͕�����ɋC�ɓ����Ă��炤���Ƃ���Ώ����ł��B�r�f�I�ɂ��Ă��{�ɂ��Ă��A�Ƃ̒��Ɏ������ނ͕̂�����̒S���Ȃ̂ŁA������̐H�w�������Ȃ����Ƃɂ͂ǂ����悤���Ȃ��̂ł��B�Ȃ̂ŕK�R�I�Ɂw������V�t�g�x�̌X��������܂��B
�@�ŋ߂̉䂪�Ƃ̃q�b�g��U��Ԃ��Ă݂�ƁA
�w�ނ�L�`�O���x�\�����w�����̈��Ǐ��B
�w�T�X�P�x�\�c�����ɖ����Ńe���r�ɂ�������Ă����B
�w�N�����������x�\���i�����i�����������D�݂��H�j���Ƃ₳�����ɂ��ӂꂽ����B
�w�J���C�O�`�x�\�{���̓J���C�`���D���Ȃ̂����A�q���B�ɂ͂܂�������Ɠ���B
�w�{�{�{�[�{�{�[�{�{�x�\�v���Ԃ�̃M���O�i���Z���X����B
�w�u���b�N�W���b�N�x�\�A�b�`�����u���P�I
�w�S���S13�x�\�u�E�E�E�B�v
�ƁA������̍D�݂���������Əo�Ă��܂��B
�@���́A�w�n�k�E���E�Ǝ��E�玙�x���A�����A�j���������悤�Ȗ���ɂȂ�Ƃ��ꂵ���ł���܂��B
�@
��119�b�w�܂���������x
2006.10/19�f���@
�@����x�m�R�ɍs���Ă��܂����i�ƌ����Ă��o�R�ɍs�����킯�ł͂Ȃ��h���C�u�Ō܍��ڂ܂ōs���������ł����j�B����ł������̂ł����A�h����ߖ�̂��ߎԂ̒��ŐQ�邱�Ƃɂ��܂����B��a��̊X�����班�����ꂽ�����̒��ԏ�ɏꏊ���߁A�����{�b�N�X�̍��Ȃ��t���t���b�g�ɂ���A���h�ȃz�e���̏o���オ��i������Ƌ����ł����j�B�Q�܂ɂ����肱��Łu���₷�݂Ȃ����v�B
�@��������N�O���A�����̕���������X�[�Ƌ߂Â��Ă��܂��B�����āE�E�E�u�g���g���g���v����@���������܂��B���|�̂��܂�ڂ��������Ă���Ɓu���������v�Ə����̂��ׂ����c�ł͂Ȃ��쑾���j�̐����B
�@�͂��H�Ƒ����J���Ă݂�ƁA�����p�̌x������l�B�u���̕ӐS���Ƃ������āB������Ȃ��i���o�[�Ȃ̂Ŋm�F�����Ă��炢�܂��B�v���̌�A�u�����ɗ����v����n�܂��āA�u��������~�܂��Ă�v�Ƃ��Ƌ��̊m�F���Ȃ���ŁA�p�g�J�[�̂���20���قǂ��낢��b����܂����B�Ō�ɂ͌�����Ƃ����悤�ŁA�u�������畗�ׂЂ��Ȃ��悤�Ɂv�ƌ����ĕ��Ƃ���܂����B�������������͂s�V���c�ꖇ�A�����̐Q�N���B�̂͗₦����A�������蕗�ׂ��Ђ��Ă��܂��܂����B�����͐Q�s���A�����B������Ŏ��̂ł��N��������ǂ������Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@����ɂ��Ă��A�S���ƊԈႦ����Ȃ�āA�т����肷��قǂ̊ԈႦ���悤�ł��B�ꏊ�����������l�������W�܂��Ă��邻���ł����A�ړI���ʂ������Ⴄ�l�������̂������ł��B�܂��A�S���Ȃ炸�Ƃ��A���q���Ȃǂ��������邹���ŕs�R�ԗ��Ȃǂɑ��Čx���S�̋����n��ł�����悤�ł��B
�@���Ƃ��ƕ�����́A���̐l���̂������ԈႦ���邱�Ƃ͑����ł��B��117�b�ŏ������s�R�҂ƊԈ��ꂽ�b�͂܂��L���ɂ��V�����Ƃ���B�Â��́A��ʎ��̂̂����l��������Ă�����A�����l�ƊԈႦ���~�}�Ԃɏ悹�čs���ꂩ�������Ƃ�����܂��B���O�Ȃ�Đ��m�ɏ����Ă��炦�邱�Ƃ̂ق������Ȃ����炢�ł��B���̌������������ԈႦ�����O�œ͂��܂�����c�B
�@����ȕ�����̊ԈႢ�͏��Ă����܂����i�H�j�A���Ă����Ȃ��ԈႦ��ꂪ�䂪�Ƃɂ��Ƃ���Ă��܂��B���j���u�ۈ牀���v�ɊԈႦ����ƌ������Ⴊ�������ł���̂ł��B�̂͏��w�O�N���̕��ϐg������⏬���߂ł͂���܂����A�̏d�͕W���I�����A�O�N���Ƃ͎v���Ȃ����ނ����������Ƃ��b���܂��B�Ȃ̂ɁA�ދ����̂��ɖ{��ǂ�ł�����A�Ƃ����Ɍv�Z�Ƃ�������ƕK���Ƃ����Ă����قǁu�ۈ牀�Ȃ̂ɂނ��������Ƃł���˂��B�v�ƖJ�߂��܂��B���`�����Ȃ��B�������c�������ƌ������Ă݂邩�H
�@
��120�b�w�y���x
2006.11/3�f��
�@�w�y���x�ǂ߂܂����H
�@�s�R����ł��������A����ɂԂ����ĒJ�ɗ����Ă��܂��܂����B���̏ォ����ꂽ�R�������Ă��ė��͓y�̒�����o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���̗����p��ς����̂��w�y���x�ł��B
�@�����w�y���x�̓��O���̂��ƂȂ̂ł��B
�@�u���O���̎p���v�������ׂĂ��������B�v�ƌ����ƁA�O�̃^�C�v�ɕ�����邻���ł��B��ڂ͂����ς肤����ł��Ȃ��B��ڂ͂Ȃ�ƂȂ����ڂ낰�Ƀl�Y�~�݂����Ȏp���v�������ԁB�O�ڂ͂�������ƃw�����b�g�E�T���O���X�ł�͂����������p���v�������ԁB����ȏ�k�����邭�炢�A���O���̎p�͂Ȃ��Ȃ��m���Ă��Ȃ��̂ł��B
�@�܂��Đ����ē����Ă���p�ƂȂ�ƁA�������Ƃ��Ȃ��l���قƂ�ǂł͂Ȃ��ł��傤���B�䂪�Ƃ͂���ȋH�L�ȑ̌�������@��Ɍb�܂�܂����B
�@�䂪�Ƃ̒�ɁA�l�X�Ȍb�������炵�Ă����w�ق����炩���_���x������̂ł����A���̔_�������O���ɍr�炳��܂���̂ł��B���E�܂̏����ꂽ�����A���O���߂���w�����ߊl�ɏ��o���܂����B�����Ă��ɐ���A�ŏI�����p���ߊl�ɐ��������̂ł��B
�@�w�G���O���̃t�@�[�X�g�C���v���b�V�����́u�����A���킢�������v�B�������j���Ă�Ŋώ@�J�n�ł��B
�@���j�ɂƂ��ď��̂Ȃ܃��O���B�i������ɂƂ��Ă����̂Ȃ܃��O���ł��B�e���r�Ȃǂœ����Ă���̂͌������Ƃ����������A�����O���Ȃ�q���̍������ς����܂������A�����ē����Ď�ɂƂ��ƂȂ�Ə��̌��ł����B�j���܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ��炢�낢��ώ@���܂����B
�u�ڂ͏������ˁB�Ȃ̎�݂������ˁv
�u�������O�����B�܂��d���ā[�ȁv
�u�@�͈ӊO�Ƃ��Ă�Ȃ��B����_�炯�[�v
�u���͂���ȉs���B����Ɋ��܂ꂽ��ɂ����낤�ȁv
�u�т����������ׂ��ׂ��ċC�����C�`�I�v
�u�����ۂ̓q�Q�݂����ŒZ���Ă��������`�v
�u�����̑����I�������������Ă����Ƃ����Ԃɂ������Ă����₤�v
�������H�Ƃ����ӌ�������܂������A����͔��ɓ���Ƃ������Ƃł�����߂܂����B�i�n���ŋ��E�n��Ŏ�̐������Ƃ�����قǎ����ɂ����̂������ł��j
�@�Ō�͊w�Z�Ɏ����čs���Ă݂�ȂɌ����邱�Ƃɂ��܂����B�N���X�ł��������Ƃ��킢�������l�C�ő呛���ɂȂ����悤�ł��B�i�搶�A�ςȂ��̎�������ł����܂���B���ȂȂ������ɉ䂪�Ƃ��痣�ꂽ�Ƃ���ɓ������Ă���Ă��������c�j
�@�ȗ��䂪�Ƃ̓��O���u�[���I�z�c�̉��Ƀ����������A�^���X�̒��g�������������A�V���c�𒅂�ɂ������������A���q�̂��т������������A������ӂ܂Ń����������c�B
�@
��121�b�w��c�E�x�@
2006.12/8�f��
�@���̓�M�B�ɏZ�݁A�܂��ď��쒬�ɕ�炷���X�̑O�Łw��c�E�x�𖼏��̂͒p���������̂ł����A���܂���Ȃ���䂪�Ƃł͍��A��u�[���Ȃ̂ł��B
�@���������́A���N�x���j�̃N���X�ł�͔|�̑̌��w�K�Ɏ��g���Ƃł��B�i��̊w�K�Ɏn�܂��āA��Ɠ��e�̒�����a�Q���̑�A���n�̍�Ƒ̌��A�����ĊԂ��Ȃ��}������n�܂ŁB�������Ԃ����Ȍ`�ł�ɐڂ��Ă��܂����B
�@����Ȋ��̒��A�H�̂�V�[�Y�������Ƌ��Ɉ�C�ɂ�u�[���ɉ����܂����B
�@�܂���\�I�Ȃ�����������낦�āA�H�ה�ׂ����Ă݂܂����B�����ӂ��E���сE�W���i�S�[���h�E�z���E�V�i�m�X�C�[�g�̌�ނł���Ă݂܂����B����ƁA�P�ƂŐH�ׂĂ������ɂ͋C�Â��Ȃ��������̓������A�N�b�L���ƕ����яオ���Ă��܂��B�����ł��܂�ڂ��������ƒp�������Ă��܂��̂ŏڍׂ͏q�ׂ܂��A����Ⴀ�A�Â��́A�_���ς��́A���̋����́A�W���[�V�[�Ȃ́A�ƌ�ܗl�̈Ⴂ������܂����B��������͂��ꂼ�ꖼ�O���āA����ނ��ċ����Ă����܂��B���̌��ʁA���̌�ނȂ���������ɔ��ʂł���悤�ɂȂ�܂����B
�@���̌�A�g�ʁE�V�i�m�S�[���h��������̒��Ԃɓ���A��������X�Ƒ����Ă����\��i�H�j�ł��B
�@�䂪�Ƃ͂��Ƃ��Ɖʕ��D���ŁA�i��34�b�Q�Ɓj�������炽������H�ׂĂ͂��܂����A��������n�߂Ă���͑�ςȃy�[�X�ł��B���Ɍ�ނ̂�𖡌����悤�Ǝv������A�Œ�ł��܌H�ׂȂ���Ȃ�܂���B�l�l�Ƒ����H����܌̂��H�ׂ�̂͂Ȃ��Ȃ���ςł��B�܂��A���ނɂ���ł́A��ނ̓����Ȃ̂��A�̂̓����Ȃ̂��킩��܂���B������ނł��H�ה�ׂĂ݂�K�v������܂��B����ɂ��̎���������H�ׂĂ���킯�ɂ͂����܂���B�����H�ׂ������A�`���o�n�߂邵�c�B���`���������ς��I
�@��N�A�䂪�Ƃŗ��s���������Ɂw�u�߂�x�Ƃ����̂�����܂��B���Ƃ́w�{�������Ƃ�̃o�^�[�u�߁x�Ƃ��������������̂ł����A���j�͒��̂�̂Ƃ��낾�����������ɋC�ɓ���A�P�Ɨ����Ƃ��ēƗ����������́B�Ȃ�̂��Ƃ͂���܂���A�������߂̃o�^�[�ŁA����ނ��ăX���C�X��������A����Ȃ肷��܂��u�߂邾���̂��̂ł��B
�@�ŁA����������Ă���������A���j���A�u�u�߂�ł������������Ă݂����B�ǂ̂���ǂ�Ȗ��ɂȂ�̂��H�ǂ̂������u�߂�ɍ����̂��H���H�Ƃ͈Ⴄ��̖��������ł���̂ł͂Ȃ����B�v�ƌ����o���܂����B
�@���[��A�m���ɋ�������e�[�}�ł͂��邪�A��������ȏ�͐H�ׂ��܂���B
�@
��122�b�w�݂͖݉����̋�x
2006.12/14�f��
�@�X�ɃW���O���x��������A�ƁX�̗����ɃC���~�l�[�V�������P�������Ƃ��悢��N���X�}�X�ł��B�f�B�i�[�ɂ�����Ƃ����Ď���s�U�Ȃ�Ăǂ��ł��傤�B
�@����s�U�Ȃ�Ă����ƁA�u���n����ςȂ̂�B���y������̂Ɏ��Ԃ������邵�A�ӂ���Ȃ�Ȃ����A���������~������ɂ���̂����đ�ςȂ���B�v�Ƃ��������������Ă������ł��B����Ɂu�݂�Ȃ̊�]�̃g�b�s���O���Ă��牽�������Ă�����Ȃ����A����ȂɐH�ׂ��Ȃ��̂�ˁB�v�Ƃ�����s���������Ă��܂��B�����ō���Љ��̂́w���ȒP�Z���t�`���I�Y�[�s�U�x�ł��B
�@�y�p�ӂ�����́z
�@�g�b�s���O������́i�`�[�Y�͕K�{���H���Ƃ͂��D�݁B�p�C�i�b�v���ȂǃN���X�}�X�����A���E��E�a�H�ނ����\������j
�@�s�U�\�[�X�i�����i�ɂ������Ȃ���B�P�`���b�v���悵�A�Ƃ�Ă��̂���E���X����E���炱�}���l�[�Y�Ȃ����܂��j
�@�����č���̃J�i���A�L�q�̔�I
�@�w���ȒP�Z���t�`���I�Y�[�s�U�x�Ȃ�Ă��������Ă������������Ƃ͂���܂���B�v����ɁA�L�q�̔�Ƀs�U�\�[�X��h���āA���̂��̍D���Ȃ��̂��悹�ăg�[�X�^�[��I�[�u���ŏĂ������Ȃ̂ł��B
�@�L�q�̔�ƕ����āA�Ȃ��H�H�H�v������������������ł��傤���A�Ƃ�ł��Ȃ��B���h�ȃ��[�}���s�U���n�ɂȂ�܂��B���ޗ��͂ǂ�����������ł����炠����O�Ƃ���������O�ł��B
�@���́w���ȒP�Z���t�`���I�Y�[�s�U�x�������̂͑O�q�̕s������������邤���A�݂�Ȃō���Ă��̏�ŐH�ׂ���Ƃ����y�����������Ƃ���ł��B�芪�����i�⊪�������ē��̂ɂ��₩���Ɖ€�Ƌ��ʂ�����̂�����܂��B������������̂�H�ׂ�̂��悵�A�N���ƌ������Ė��키���悵�A�Ńs�U�ɂ��ēx�����������悵�A�y�������Ԃ��߂����邱�Ƃ��������ł��B
�@�䂪�Ƃł͂��łɉ��x���s�U�p�[�e�B�[���J�Â���A���ꂼ��̍D�݂��͂����肵�Ă��܂����B�ꂳ��̍D�݂̓t���b�V����،n�B�P�`���b�v�\�[�X�Ƀg�}�g�E�s�[�}���E�R�[���������Ղ�悹�`�[�Y��������Ƃ��������́B���j�̍D�݂͓��n�B�n���E�\�[�Z�[�W�E�T�[�����Ȃǂ����Ղ�悹�{�����[�������_�B������̍D�݂͊C�n�B���炱�\�[�X�ɃT�[�����E�G�r���悹�A���y�������Ă�����ō��B���͎��j�B�D�݂̓`�������W�n�I�Ƃ肠�����v���������Ȏ�荇�킹���ǂ�ǂ��ł����܂��B���̂�����Ԃɂ��������ς��ɂȂ��āu���Ƃ͂�����v�̎̂ă[���t�B���̂̒m��Ȃ��g�ݍ��킹�̎c�蕨��H�ׂ邱�����̐g�ɂ��Ȃ��Ă���`�B
�@�����A���ꌋ�\���܂������I
�@
��123�b�w�Ƃ���Ă�x
2007.1/16�f��
�@���������ߖ�肪�[�������Ă���܂��āA�q��Ă���鎄���A�����ň���Ȃ��킯�ɂ͂����܂��܂��B
�@�����͂������̂́A���C�y�q��Ă�W�Ԃ��鎄�ł�����A�ǂ��ƔY��ł�����������A�u�����A���������l�������ł���v�ƋC���y�ɂȂ���x�̂��̂ł��B�����h�̂����ߘ_������]�̕��͓ǂݔ���Ă��������B
�@���āA�܂������߂��ĉ����l���܂��傤�B�����猻��ł͂����߂��w��Q�҂��s���Ɋ��������Ɓx�ƒ�`���Ă��܂��B���Q�ґ��̈ӎ���A�q�ϓI�Ȏ����͈�؉�����Ȃ��̂ł��B������ĂȂςł���ˁB���œ|�ꂽ������������u���v�ł����v�ƕ����N��������u�N��肾�Ǝv���Ĕn���ɂ�����āA�s������v�Ǝv�������߂ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�w�Z�Ȃǂł����߃A���P�[�g���Ƃ��Ă����Ԃ��c���ł��Ȃ��̂͂��̂����肪�������ȂƎv���܂��B��Q�҂ɂƂ��Ă��A�����ߍs�ׂ���菜���Ăق����̂ł͂Ȃ��A���Q�҂̈ӎ����Ăق����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����c�B
�@����ɐl�Ԃ̐S�قǕs�v�c�Ȃ��̂͂Ȃ��A���ӂ�w�i�ɂ����P�ӂƂ��A�P�ӂ��܂��ӂƂ����G�Ȃ��̂�����̂ŁA����Łu����͂����߁A����͈Ⴄ�v�ƊȒP�ɔ��f�ł��Ȃ��̂����̖��̓���Ƃ���ł��B����p�x���猩��Ɗm���ɂ����߂����ǁA���_��ւ���Ƃ����Ƃ���͂����A�Ƃ������Ƃ������̂ł��B��A�\�ň���I�Ȍ����������A����͂Ђǂ��Ƃ�����͂��������Ƃ����͔̂��Ɋ낤�����f�Ȃ̂ł��B
�@�ŁA�������瓱����錋�_�́u�����߂͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�����߂ɖ��m�Ȕ������Ȃ��ȏ�A������菜���A���������ׂ����̔������Ȃ��̂ł�����B�ߏ�Ɏ�菜���ΎЉ���������s���Ȃ����A�ߏ�ɋ��������߂��������܂��B�ʂɖ�肪�N���������ɔ��f���u�����Ă�����������܂���B
�@�ł́A�ƒ�ʼn����ł��邩�B����Ȃ��ȏ�A�����߂Ȃ��q�E�����߂��Ȃ��q����Ă邱�Ƃ͂ނ�ł��B�ł���̂͂����߂ɋ����q�E�����߂��Ă����v�Ȏq����Ă邱�Ƃł��B�}�����A����Ӗ��݊��ɁA�u���������߂��Ă�H����͂Ȃ����`�B���v���v�A�Ȃ���Ȃ����āv�ƐS�̒ꂩ��i����ׂ����ł͐�_���j�������w�S�̑����l�ԁx�Ɉ�Ă邱�Ƃ���ł��B�Ƒ����J�̑����Ɋ�Â������X�̒b�B���d�v�ł��B�����Ă��̉Ƒ����J�̑��������͑傫�ȃ|�C���g�������肷��̂ł��B
�@�����ŁA�䂪�Ƃ̎q���B�����Ă݂܂��ƁA�Ƒ��̋ɑ����J�ƁA������̌������b�B�̂������ŁA���ɐS�������炿�܂����B�������ŋ߂ł͉��ɂł��u����͂Ȃ����`�B���v���v�B�͂��͂��͂��v�ōς܂��Ă��܂��X�����B
�u���T�e�X�g�ł���H�v
�u����͂Ȃ����`�B�v
�u�e�X�g�ł����H�v
�u���v���v�B�v
�u�_���́H�v
�u�`�b�`�L�`�[�₪�ȁB�v�u�c�B�v
�@����A�㔼�ɑ����I
�y�Ƃ���Ă�z�e���O�T�ȂǁA���V�����܂ފC�����ςėn�����A���ɗ����ė�₵�ł߂��H�i�B�Ȃ�����̃^�C�g���ɂȂ��Ă��邩�͊����ŏ����Ƃ킩��܂��B
�@
��124�b�w�����߂�H�x�@
2007.1/24�f��
�@�u�����߂�H�v�Ƃ͍������\�N�قǑO�ɘA�ڊJ�n���ꂽ�����炵�݂����Ƃ����l�̖���w�ڂ̂ڂ́x�̌��܂蕶��̈�B���������������Ă��킢���u�����߂�H�v�ƌ����̂����s��܂������A�����́u�����߂�v�͂��킢���Ȃ��ł��ˁB�i�O��̑����j
�@�����߂̍�����Ȃ��ӎ��́A��Q�҂ɂ����Ă����Q�҂ɂ����Ă��A�A�шӎ��i�A�ъ��j�Ƒa�O�ӎ��i�a�O���j���ƍl���܂��B�A�шӎ��Ƒa�O�ӎ��͂����Z�b�g�Ō���܂��B
�@�����߂邱�Ƃɂ���ĒN����a�O���邩�Ǝv���A�����߂邱�Ƃɂ���ĘA�ъ������߂邱�Ƃ�����܂��B�����߂��đa�O�������������Ǝv���A�����߂��邱�Ƃɂ���ĘA�ъ��������邱�Ƃ�����̂ł��B�����ƕςȂӂ��Ɏv���܂������l�����͑�^�ʖځB������u�v���Ђǂ����Ƃ����Ă��܂����v�Ƃ������Ȃ̌��t��A�����炢���߂��Ă��A���Q�҂ƈꏏ�ɍs�����Ă��܂�����Q�҂̋C�����͂��̕��G���ɂ���̂ł��B
�@��ʓI�ɘA�ъ��Ƒa�O�����̊W�łƂ炦�邱�Ƃ������̂ł����A���ꂪ�����ߖ��̗����Ɣ����������Ă���̂��Ǝv���܂��B�����Ă����ߖo�ł̌��������ɂ���Ǝv���܂��B
�@�A�ъ��Ƒa�O������̊W�łƂ炦�܂��傤�B��������A�������̔��Ȃ̌��t���Q�҂̋C���������������ł���ł��傤�B�����Ėo�łւ̃X���[�K���w�A�тȂ��W�c�ɑa�O�Ȃ��x���������͂��ł��B
�@�w�A�тȂ��W�c�ɑa�O�Ȃ��x�Ȃ�Ƃ����Ƃ������̂悤�Ɉ���������̂Ȃ��₽�����t�B�ł����A���ꂱ���������ߖo�łւ̍ŒZ�����Ȃ̂ł��B
�@�������������w�Z�̓��������ĂȂ�Ȃ̂ł��傤�B�e���c�̓s���ŁA���܂��ܓ������ɏZ�݁A���܂��ܓ����N�̎l������O���̊Ԃɐ��܂ꂽ�����̂��Ƃł͂���܂��B����Ȋȗ��R�ł��܂��ܓ����g�ɂȂ����҂��A�����A�шӎ��������Ē��ǂ�����Ă������Ƃ̕����s�v�c�ł��B�u���ǂ����悤�I�v�Ȃ�Ĉӎ��͎������u������ׂ邱�ƂɂȂ����̂������̉��B�O�N�Ԃ�����������Ă�������v�ŏ\���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����Ȃ��Ƃ�������w�Z�����藧����Ȃ����A�Ǝv���邩������܂��A�����w�Z�̃N���X�Ƃ����̂́A���̒��x�̐����P���̏ꂾ�Ɗ�����Ă݂���ǂ��ł��傤�B���������炢���߂����Ԃ��F��Ƒ呛�����Ă������̗͂��A�����Ɣ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����Ă��̕��A������A�Љ����A��Ȃǂ̋��ʂ̖ړI�������ďW�܂������ԂƁA�����A�ъ�����Ă�悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�l���������ςł͂Ȃ��A�����͗͂�����Ƃ���A�����͌y�������Ă悢�Ƃ���B�����������Ƃ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�����܂��B
�@�@
��125�b�w�叼�x
2007.2/3�f��
�@������j��A�Ƃɖ叼������ꂽ���Ƃ͂���܂���ł����B������̏o�g�n�̋��s�͒��A�ꕶ�����ł����A�ǂ����Ă��|����l���Ȃ̂Ɂw�J�h�}�c�x�Ƃ������O���ǂ��������Ȃ��ď��������Ƃ��Ȃ������̂ł��B���������N���߂Ė叼������܂����B
�@���������́A�N���Ɏ��j�ƎQ���������쏭�N���R�̉Ǝ�Â̖叼����̌��ł����B
�@�叼�����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA���삪�ǂ������ӂ��ɂȂ��Ă���̂��������Ƃ�����܂���ł������A�܂��č����ȂǑS���m��܂���B���j�ƈꏏ�ɑS���̃[������̑̌��ƂȂ�܂����B
�@�����������̂́A����30�����قǂ̂��́i�ߏ��̓X�Ō�����2500�~���炢�́j�ŁA����ɍ��킹�āw���V�R�f�ށx�̂��̂ł����B
�@�܂��g�����܂��B���Ƃ����Ă����a15�����قǂ̒|��邾���ł��B�i���a15�����Ƃ����܂����A���ی���ƈ�ʐl�ɂ͗p�ӂł��Ȃ��悤�Ȃ����������I���N�ȍ~���삷��ɂ́A���̒|�E�������͑�p�i�̓��肪���ƂȂ肻���ł��B�j
�@���ɗ��Ă�|�O�{���܂��B���������낦�A���������킹�A����̊p�x�����킹�i��{����ĕЕ��Ђ�����Ԃ����炤�܂����������ł����A�t���|�ʼn��N�������̂Ń_���j�A�\�ʂ������Ȃ��悤�ɒ��J�ɐ��Ă����܂��B�ꂽ��O�{�܂Ƃ߂Ă���܂��B
�@���̎O�{�|��g�̒��ɓ���A���X�y�[�X�ɐ肭������[���l�߂ČŒ肵�܂��B���̎��M�`�M�`�ɋl�߂��A��Ԃ��c���Œ肷��ƁA�Ō�̏�����̎}������₷���Ȃ�Ƃ������_������܂��B
�@�ł����Ԃ�������̂��E�҂݂ł��B���a15�����̘g�Ɋ����̂ł�����45�����ȏ�̑E���K�v�ł��B�҂ݕ�����ޏЉ�Ă��炢�܂����B��͂��₷�Ɠ������@�ŕ҂ނ����ŁA����Ȃ�ꖇ20�����炢�łł��܂��B������͓�����g���Ă�����Ɠ������@�ŕ҂ނ����ŁA���ꂾ�Ɠňꎞ�Ԃقǂ�����܂��B�䂪�Ƃ͏��̌��̂���������ɒ��킵�܂����B�ŏ�������Ԃǂ�܂������A����Ă���ƁA���j�Ɠ�l�Łu��������ăz�C�A�����������ăz�C�v�Ƃ��̂��Ȃ��炢�����Y���ł͂��ǂ�܂����B50���قǂŕ҂݂�����܂����B
�@�҂݂��������E��������Ŋ���������A���Ƃ͔h��ɏ������ł��B����}���܂���A��V�����̂����Ղ�����Ƃ�������܂��B��̖c��~�������āA���悢��t�炵���Ȃ�܂��B���ƒn��ɂ���Ă��₷����������A���A���������A�Z����Y������H�q����������肷��悤�ł��B
�@�����i���ʐ^�̂��́B���蕨�Ȃ݂̗��h�Ȃ��̂��ł��܂����B
�@���̖叼���䂪�Ƃ̌��ւŁA��N�Ԃ�̕��������Ă����ō��ł��B
�@
��126�b�w�����厩�R�x
2007.2/25�f��
�@����Ƒ��œ����ɍs���@�����܂����B�������������܂ōs���̂�����A�p�������ł͂��������Ȃ��B�O���ꔑ���ē����V�т���悵�܂����B
�@�����̂ǂ��ɍs���Ă݂������ƕ����Ă݂�ƁA���j�͑����Ɂu�p���_�I�v�Ɠ����܂����B���j�͏��w�Z�̏C�w���s�œ����ɍs�������Ƃ�����̂ŁA���ʂǂ����ɍs�������Ƃ�����]�͂���܂���ł������A�u�������������Ȋw�����قŁA�Z�����Ă�����茩���Ȃ���������A������x�s���Ă݂����v�ƁB�����ō���̌��w�n�͏��Ɍ���B
�@�Ƒ��l�l�ňړ��ƂȂ�Ǝ��Ɨp�Ԃ̕��������B�������͈�{���ŊȒP�ł����A��s�������H�ƁA�s����ʓ��͂����Ⴒ���Ⴕ�Ă��Ă͂����茾���Ĉꌩ����ɉ^�]�͖����B�������J�[�i�r�̕t���Ă��Ȃ��䂪�Ƃ̎Ԃł̓J�[����i�r������ł��B���C�Łu���̃S�g�`���E�̐M���ʼnE�܂��āv�Ƃ����߂���J�[����i�r���w��k���i�������܂��j�̂��Ƃ��ȁx�Ɨ������ĉ^�]���Ă����܂��B���Z���ɏo�����l���Ԃ����ē��������������B�{���ɔ��܂����B
�@�ꌎ���{���Ƃ����̂ɓ����͂ۂ����ۂ��B��������������ɂ͂������V�C�B�܂��̓p���_�ɂɈ꒼���B�ꂳ��ƁA���j�̃C���[�W�ł́w�p���_�͂����Ƃ��Ă��Ėʔ����Ȃ������x�B�����炭�C�w���s�ő�l���ŋl�ߊ|�����̂Ńp���_�����Ă����̂ł��傤�B���̒��ł́w�p���_�͂܂߂ɓ����ăT�[�r�X���_�L���ȓ����x�B����������蒷���Ԍ��Ă���̂ł����V�[���ɂ߂��荇���Ă���̂ł��傤�B���̓��͌�ҁB�����̍������V�����V���H�ׂ���A��������Ĕw���������Ă��ꂽ��B�ꂳ��ƒ��j�����ł��܂����B
�@���̌�A�����������ЂƉ�肵�āA�ߌ�͍����Ȋw�����قɈړ����܂����B
�@�����Ȋw�����ق͓��{�ق��������������̂́A���ׂĂ����Ă���ƂƂ��Ă�����ł͉�肫��܂���B���ꂼ��ɋ������قȂ邱�Ƃł�����A�W���ꏊ�Ǝ��Ԃ����߂Ċe�����R���w�Ƃ��܂����B
�@���j�͏C�w���s�ł͂������ł��Ȃ������̌��R�[�i�[�Ɉ꒼���B�قƂ�ǂ̎��Ԃ������Ŕ�₵�܂����B���j�͐������A���ł������̃R�[�i�[�Ɍ������܂��B�����������R�[�i�[�͎��j�̖��������قǂł͂Ȃ��A�قǂȂ������R�[�i�[�ֈړ����Ă����܂����B�������ŕ�����ꂽ�ꂳ��̓��E���W�ŋx�e�B�ځ[���Ɠ������̃J�o��Ԃł����B������̓~���[�W�A���V���b�v���₩������A���j��ǂ��������肵�Ă������܂����B
�@�Ō�Ɏl�l������āw����L��x�ő呛���B�َ��ԂŒǂ��o�����܂ō����⓮���̐������\���Ɋy���݂܂����B
�@�������悭�l���Ă݂���A�Ȃ�ł킴�킴�����܂ōs���Ď��R�����\���Ă��ł��傤�H
�@
��127�b�w���x
2007.3/6�f��
�@�܂���������
�w�������@�{���ؓ��@���������x
�@����͎��j���w�Z�ŁA�o��i����j�̊w�K���Ԃɍ������i�ł��B�C�������Ƃ��Ă��f���ɕ\������Ă��邱�Ƃ�A�g�����h�Ɖp��Ŏ����̂��Ƃ������g�J�E�i�b�n�v�j�h���|���ɂȂ��Ă���i�H�j�_�Ȃǂ��]�����ꂽ�̂��A�哇�����o����ŕ\������܂����B
�@�ŁA���̐���ɑf���ɕ\������Ă���悤�ɁA�䂪�Ƃ͓��D���ł��B
�@������̏o�g�n�̊��ł́A���Ƃ��������̂��Ƃ�����킵�A�͓ؓ��A���͂�������ƌĂт܂��B�i���œ��܂�Ƃ��킸�܂�ƌ����̂͂������������I�w�i����ł��j�������䂪�ƂŌ������Ƃ͊����ł͂Ȃ��A�،{�����A���̑��̂ł��B�����Ăǂ̓����݂�ȑ�D���Ȃ̂ł��B
�@�����͌����Ă��䂪�Ƃ̂��Ƃł�����A�����ȓ����Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B�i�撣���Ĕ������Ƃ���ŃO����200�~�܂łł��B����ł����������J�S�ɓ����Ƃ��ɂ͎肪�k������̂ł��B�j�ł����炻��قǃr�r�b���肠�肪������K�v�͂Ȃ��̂ł����A�Ȃ����H��ɓ���������Ƃ��炭����オ��܂��B
�@���̎�ނɂ͂���قǂ������܂���i�Ȃ����ł�����j�B�������̂͒������@�ł��B���낢��Ȍo����A��Ԃ��܂��͉̂��R�V���E�ł����Ă������́B���̎�ނɂ���ēS���������A�t���C�p�����������A�O�������������̈Ⴂ�����邭�炢�B���Ƃ͏Ă������ɂ������̂�����肪����܂��B��������D���ȕ�����̉e�����A�����ă��A�����D�݁B�X�|���T�[���ŃX�e�[�L�Ƃ��H�ׂɍs���ƁA��̎��j�ł����u�Ă������̓��A�ŁB�\�[�X�͉��R�V���E�ƃo�^�[�ɂ��Ă��������B�v�ƒ������܂��B
�@����Ȃɓ��D���ȉ䂪�ƂȂ̂ɂ��ւ�炸�A���܂ŋ������ɍs�������Ƃ��Ȃ����ƂɋC�Â��܂����i������͎Ⴂ�������Ԃ�s�����j�B�����̗A�����������ŁA��������}�C�i�X�̃C���[�W�����������炩�A���ɓߒn���ɋ����������Ȃ������Ȃ̂��B�Ƃō�����背�g���g��H�ׂ���͂��Ă����̂ɁA�Ȃ����������ɍs�������Ƃ��Ȃ������̂ł��B����ł͓��D���̖���������I�����s���Ă��܂����B
�@�X�ɓ���ƕ��ʂ̃��X�g�����̂悤�ɂ܂����j���[���J���܂��B���������������Ȃ����Ƃ��m�F���A�u�����O�A�吷��v�ƒ������܂��B�K�c�K�c�H���āA���j�͑吷�̂����ɂ���ɂ�����t������肵�܂��B���������ς��ɂȂ背�W�֍s���ƂȂ�Ƃ��̃n���o�[�K�[������������ł͂���܂��I�H�א���̉䂪�ƌ�p�B����I
�@�ɂ킩�ɋ������t�@���ɂȂ����q���B�́A���Ƃ��邲�ƂɁu���ꁛ�������狍�����t�H�ׂ��邼�B�v�Ɓg�P�����h�Ƃ����ʉݒP�ʂ�����ĕ�炵�Ă��܂��B
�@
��128�b�w�����ň��x
2007.3/18�f��
�@�O��A���j��́w�������@�ؓ��{���@���������x�Ƃ���������I�������܂������A���͓��X�o��E������Ђ˂��Ă���̂͒��j�Ȃ̂ł���܂��B
�@��N�l�����������A���L����ɔo��E���������Ă��܂��B���ЂƂ��͗͂Ɍ����钷�j�ɁA���w�Z�̍��͖������L�Ƃ������앶�������悤�ɂ����Ă��܂����B�ł����A���w�ɓ��w���A�h��ɕ����ɖZ�����Ȃ��Ă��Ă��܂蕉�S�ɂȂ��Ă͂����Ȃ��ƁA�����̎��Ԃłł���o��E�������点�邱�Ƃɂ����̂ł��B
�@�{���o��E��������ĒZ���Ԃłق��ق�������̂ł͂Ȃ��̂ł����A������Ԃ��Ȃ����ƂƁA���C�̒��ł������Ȃ���ł��l�����邱�Ƃ��v���A�앶��肩�Ȃ��y�Ȃ��̂Ƃ����Ă����ł��傤�B��������قǁw�Ђ˂�x�Ə����܂������A���j�͎��ۂɂ͂قƂ�ǂЂ˂��Ă��܂���B�X�g���[�g�ŁA��������������炻�������ł��B���Ȃ��d�ˁA�Ђ˂�܂���̂��o��̖ʔ����Ȃ̂ɁA���̕ӂ͂܂������킩��Ȃ��悤�ł��B
�@�������܂����Ƃ�����������N�Ԃ�B���������ł��B�i���Y�ꂽ��������������܂����c�j�����猩�Ԃ��Ă݂�Ɨ��h�ȓ��L�ɂȂ��Ă��܂��B���A�����͂���ς�o��E����B���ꂾ���ǂ�ł��u���̓����ĉ������������������H�v�Ƃ��A�u������Ăǂ������Ӗ��H�v�Ƃ������̂����\����܂��B������{�l�ł����킩��Ȃ����Ƃ�����̂ł�����A����̂��̂ɂ́H�H�H�̘A���ł��B�����ŕ����A������Y���āA����̋�W�Ɏd���ďグ�邱�Ƃɂ��܂����B
�@�w�Z�̌v��\��A���j�̐����̋L�^�i���w�Z�ł����A�����݂����Ȃ��́j�̊��z���A�Ƒ��̗\��\�ȂǂƂ����킹�ĉ�ǂ��Ă����܂��B���̂������łقƂ�ǂ̎������������܂����B
�@��N����C�ɓǂ�ł݂�ƁA���̐������Ă��Ȃ��x�������悭�킩��܂����B�Ȃ��ɂ͔o��E����Ƃ͌������w���Z�ҎU�����H�x���Ǝv������̂�A���R�������X�ɂƌ��������Ȃ�悤�Ȃ��̂�����܂��B
�@������360�������ƁA����Ȃ�Ɂu�����I�v�Ǝv�킹��̂�����܂��B�������Љ���Ă��������܂��B
�@���߂Ęn�̂�ɍs���ĉr�ށ@�@�@�@�@�w���тƂ��ɐA����ΎG���Ɂx
�@��������x�������Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�w�˂ނ��ڂ������������Ȃ��玩�]�ԂŁx
�@�ՊC�w�K����ڂ͉J�@�@�@�@�@�@�@�@�w�J�ӂ��ĊC�ɓ��ꂸ�C�J�����x
�@�v���Ԃ�̕��������ꂵ���ā@�@�@�@�w���v�݂ăA�b�Ƃ��ǂ낭�R���ԁx
�@��A�������瓪�ɂŃ_�E���@�@�@�@�@�w���ɂ���䂭�N����N���ɂ���x
�@�O���̑�Ⴊ�����ā@�@�@�@�@�@�@�@�w���������邩�܂��炴�����肷�ׂ�x
�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂶ�Ⴝ���̐e���̎�������c�B
�@
��129�b�w�g�ւ��x
2007.4/4�f��
�@���j�̏��w�Z�ł͎O�N������l�N���ɐi������Ƃ��A���j�̒��w�Z�ł͈�N�������N���ɐi������Ƃ��ɃN���X�ւ����s���܂��B
�@������̏o�g�n���s�ł́A���w�Z�͎O�N�i�����ƌܔN�i�����̓��A���w�Z�ł͖��N�N���X�ւ�������܂����i���͒m��܂��j�B���ꂪ���ʂ��Ǝv���Ă��܂�������A�킽�������쌧�����ɂȂ����Ƃ��ɂ͂����Ԃ�˘f���܂����B�����A�O�N�ԃN���X�ւ��Ȃ����嗬�̒��w�Z�̋����������̂ŁA���ɂт����肵�܂����B�����Ő������ɂ��钆�w���ƎO�N�Ԃ������ƈꏏ���Ȃ�āA�ӔC���傫�����܂��B���k�ɂ������Ď�e�����傫������悤�Ɏv���܂��B�����āA���w����̎v���o�͂����Ɠ����搶�Ƃ̎v���o�Ȃ�ł�����B�܂��N���X���C�g�ɂ��Ă��������Ƃ�������Ǝv���܂��B�E�}�������z����Ȃ��z�B�D�e�������e������S���̂ł��B�������w������߂����邩�ǂ������A��x����̃N���X�Ґ��Ō��܂��Ă��܂��܂��B
�@�w�O�N�Ԃ�������w���ł���x�̂��悢�ƈ̂�����͌����܂����A���Q�̂ق��������̂́A�����N���X�ւ��������Ă�������ؖ����Ă���ł��傤�B���������������玄���N���X�ւ����咣���Ă�����������܂���ł����B�Ȃ��ɂ́u�����͒��쌧���v�Ɠ{����鋳���܂ł������炢�ŁA�g�z�z�ł����B
�@���������猩��Ɩ��N�N���X�ւ�������ƁA�u�����͈�N�ԁB�v�����Ă��B�v�Ɨ����オ�肪�����A�����������̐�含������̂ł��B��含�Ƃ́A�Ⴆ�w���w����ɐ����Ɗw�K�̏K����t��������̂����܂��搶�͖��N��N���̒S�C�x�A�w�i�H�w���ɒ������搶�͖��N�O�N���̒S�C�x�Ƃ�����B�w�Z���ł̎d�����v���t�F�b�V���i���Ȃ̂ł��B���k���ی�҂����S���ĔC�������������܂����B
�@���k�����猩��ƁA����Ȃ��Ƃ́u��N�䖝��������v�����A�������Ƃ́u���̃`�����X���Ȃ��v�ƒZ���X�p���Ŋ��������邱�Ƃ��ł���̂ł��B���Z�b�g�ƃX�p�[�g�������₷����������܂��B
�@���w�Z�ł͕�����������̂Ő��k���m���̂Ȃ��肪�����Ȃ�܂��B�N���X���u�Ă�������������ɂȂ�̂ŁA�ǂ����Ă��S�C�̔�r�E�i��߂��s���܂��B���̏�Ŏ������ɒS�C����鐶�k���������ŁA�����Ȃ��Ǝw�����킦�鐶�k������킯�ł��B�m��ʂ͒S�C����Ȃ�A�ł��B
�@���āA�䂪�Ƃł͎��j���N���X�ւ����������Ă��܂����B��قNj��S�n�̂����N���X�������̂ł��傤�B�S�C�̐搶���]�C����ƕ�����A�N���X�̂��ʂ���������Ƃ��ɂ́u�����͂��Ȃ��������ǎ₵�������v�ƌ����Ă��܂����B
�@�����l������͂ǂ�ȃN���X�ɂȂ邩�H�y���ݔ����A�s�������B
�@
��130�b�w�����ė����x
2007.4/18�f��
�@�����ė����������Ď����E���k�̂��Ƃł͂���܂���B�搶�̂��Ƃł��B�搶�̂��Ƃ������Č��C�⎩�Ȍ��r��ς߂Ƃ������Ƃł͂���܂���B�l���ٓ��̘b���ł��B
�@�搶�́A���쌧�ɍ̗p����s��������C������ĐE�ꂪ���܂�܂��B�ł��̂Ŗ{���Ȃ�s��������ψ����u�����搶���~�~���w�Z�̐E���Ƃ��Č}�������v�Ƃ����\��������A������ψ�������F����Ƃ����i���ŕ��C�悪���܂�͂��Ȃ̂ł����A���ۂ͂����ł͂���܂���B�ڍׂɂ��Ă͎��̂悤�ȉ����[���m��R������܂��A�ȒP�Ɍ����ƁA�n��̍Z�����W�܂��Đ搶��������荇���i���邢�͉����t�������j�̂ł��B
�@���̏W��ɐ旧���Ċe�Z�Ő搶���̊�]�����������Ȃ��܂��B�Z����Ƒ��A�擾�Ƌ��̓s���ŁA��]���Ă����i��������Ă����킯�ł͂Ȃ��j�̂ł����A���̏�ł悭������䎌���u�����ė����v�Ȃ̂ł��B
�@�w�����ė����x�������Ӗ��Œʖ�Ɓu���낢��Ȍo����ς�ŗ��Ȃ����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�R�ԕ��̊w�Z�Łw�����ė����x�Ƃ����Ύ��͓s�s���̊w�Z�ɍs���Ƃ������ƁB���l���̊w�Z�Łw�����ė����x�Ƃ����Ύ��͑�l���̊w�Z�ɍs���Ƃ������ƁB���w�N�̐搶�Ɂw�����ė����x�Ƃ����Ύ��͒�w�N��S������Ƃ������ƁB������̋t������A�܂�͍��܂ł̊��̔��̌o�������Ȃ����Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�@�����ǂ�Łu�搶������όo����ς܂Ȃ���ȁB�����Z�p�҂����ǐ͉̂c�Ƃ���������v�Ɗ��S�����Ƃ��ƈႤ�B�����Ⴄ���Ƃ����ƁA��ʎЉ�Ōo����ςނƂ��́A���K������n�܂�A���ς݂��o�����Ĉ�l�O�̎d����^������̂ł����A�搶�̏ꍇ�͂����Ȃ��l�O�̎d������n�܂�̂ł��B����܂Ŏ����d�������Ă����l�ɁA�����Ȃ�ƈꌬ���Ă�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł��B
�@�搶�ɂƂ��Ă͌˘f���͂�����̂̂܂������ł��傤�B����̋��������̂Ȃɂ������̔삵�ɂȂ�ł��傤����B�ł��S�����ꂽ�����E���k�ɂƂ��Ă͂����ɂ��Ȃ�܂���B���������Ԓ��̊H�ƂȂ�A�삵�ɂ���Ă͂��܂�܂���B
�@�O���Ő搶�̐�含�ɂ��ď����܂������A���́w�����ė����x��݂炸�ʖ�Ɓu���������g�ɕt������含�Ɣ\�͂��ł��邾���������ɂ������ւ̔z�u�����v�ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@����႟�A�V�������̂ق������܂������搶��A�ǂ�ȂƂ���ł��\�͂̂���搶�����܂����A�����������܂��͂����܂���B������͘Z�T������ʂ͔��T���炢�ɐS���Ă����܂��傤�B
�@�����A�l�������q���E���ߏ�̒S���ɂȂ�ꂽ�搶�A�O�C�n�͂ǂ�Ȋw�Z�ł����H
�@
��131�b�w��������V�g�x
2007.5/9�f��
�@129�b�ŏ����܂����悤�ɁA���N�x���j�E���j�Ƃ��ɃN���X�ւ�������܂����B�N���X�ւ��̂������N�̏t�̍P��s���Ƃ����A�ƒ�K��ł��B�i���������ΈȑO�̓N���X�ւ��ȂNJW�Ȃ��A���N�ƒ�K����Ă���܂�����ˁB20�N�قǂ܂����珙�X�Ɍ����Ă��āA���ł̓N���X�ւ��̂������N�E�g�����̂��̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�j
�@�܂��䂪�Ƃɂ���ė���͎̂��j�̒S�C�̐搶�B���t���n�ɕ��C���Ă����搶�ŁA�����ɂ͕s����B�������䂪�Ƃ͏����̈�ԁB������Ƃ���ȗ\�������܂��B
�@�r���S�`�I�\�莞�Ԃ�10�������Ă��搶�͌���܂���B���k���Ԃ�15�������Ȃ��̂Ɂc�B���j�Ɠ�l�ő傫�Ȓʂ�ɏo�ĒT���Ă݂܂����A�搶���ǂ�ȎԂɏ���Ă���̂��킩��Ȃ��̂ł��������Ă邱�Ƃ����ł��܂���B�i���͋����̍��A�ƒ�K��ʒm�̒��ɕK���w��Ԃ��ĂȂ��������{�b�N�X�Ŏf���܂��x�Ƃ������Ă��܂����B�j
�@���Ԑ�ԍۂɁA�搶�����낤�낵�Ă������j���������琂ł��܂������A�Ƃ܂ł̓�������ɍ��k�͎n�܂�A�Ƃɂ�����ƕK�v�ŏ����̊m�F�������Đ搶�͋����Ă����܂����B�O�N�Ԃň�x�����̉ƒ�K��Ȃ̂ɂ�����Ǝ₵�������ł��B
�@������A���x�͒��j�̒S�C�̐搶������Ă��܂��B��N���瓖�n�ɕ��C���Ă��܂����A�S�C�����͍̂����߂āB�܂�ƒ�K������߂āB�ł��Ȃ��т̍ŏI�Ƃ������Ƃň��S�B
�@���j�̂Ƃ��ɒ���A���\�������Ԃ��璷�j�ɒ�@�ɍs�����܂��B����ς�搶���ǂ�ȎԂɏ���Ă��邩�킩��Ȃ��̂ł����A�O�K��悩�珇�H�𐄑����đ҂������܂����B�������Ő搶����킷���Ƃ��Ȃ��A�����̒x��ō��k���J�n�ł��܂����B
�@����A���Ԃ��Ō�Ƃ������Ƃŕꂳ������k�ɎQ���ł��A���e�ł��}���ł��܂����B�ꂳ��͉ƒ�K�⏉�̌��B�����͎�ڑ҂����߂Ď{�����ɂ܂��ْ��C���B�����͂����ǂ��蕃�������Ă����܂����A�����o���Ȃǂ���Ă݂����Ƃ������Ƃł��C�����܂����B
�@���Ē��j�̒S�C�͏����B���܂⏗���̒��w�S�C�����Ȃ��͂Ȃ��Ȃ�܂������A����ł��������ق��ł��傤�B����ɉ䂪�Ƃł͒��j�E���j�ʂ��ď��߂Ă̏����S�C�ŁA�����ɔ��������̂����j�ł����B���k���Ă���ƁA���j����������̂����ɗ��܂��B��q�̌��Ԃ���A���邢�͐Q�]��Ŏ��p����B���Ȃ���E�҂̂��Ƃ����Ă���܂����B
�@�ƒ�K��͗���搶����ςł����}����ƒ����ςł��B���k���e�͂������d�v�ōő�̑�ς��ł����A�K���������҂Ƃ��āA����Ȃ�Ɏ���̂Ȃ��悤�ɂ���̂���ςł��B�����ĂȂɂ��A�G�ߊO��̑�|������ԑ�ςł��B����ϖ��N�͂���ǂ��Ȃ��`�B
�@�@
��132�b�w���ߏ��厩�R�x
2007.5/20�f��
�@�䂪�Ƃ�����Ƃ���́A�s��Ƃ͓��ꌾ���܂��A�R�ł��X�ł��Ȃ��A�܂��ăW�����O���Ȃǂł͂���܂���B�ʎ����Ɛ��c�̓_�݂���Z��n�ł���܂��B����ȏꏊ�ɂ�������炸�A�䂪�Ƃ̎���͖쐶�����̕�ɂł��B
�@���n�Ɉ����z���Ă��Ĉȗ��A��ԓ���ݐ[���쐶�����́w�L�W�x�ł��B�䂪�Ƃ̒�Œ������݁A�����c��ڂ̒���舕����Ă����܂��B�G�߂ɂ���Ă̓��X��Ƒ���A��Ă����肵�܂��B���H�̔������Ŏ��̈ڂ낢���f���o���A�N������o���C�̂����Ȃ���ł��B�q���B���������������́A��Ŕ��œ��H�ł悭�ǂ��������������Ă��܂����i�������q���B������I�ɒǂ������邾���ł����j�B���H���ܑ�����Ă��Ȃ��������͍����������グ�A�A�����J���R�~�b�N�̃��[�h�����i�[���Ȃ���ɋ삯�Ă����p�͈����ł����B
�@���݈�Ԓ��ǂ��Ȃ̂́w���O���x�ł��B����ق����肩�����^���҂ł����A���i���d�|���ĕߊl���Ă݂�ƂƂĂ����킢����ł��B�i��120�b�Q���j���i�~�݈ȗ����ł�10�C�قǂɏo��A���̂��тɎq���B�ɂ��킢�����Ă��܂��B�������S���ʂ̌̂ł����A�ǂ����������ہX�Ƒ������啨�ň��炵�������炠��Ⴕ�܂���B���d�ɉ䂪�Ƃ��痣�ꂽ�Ƃ���ɕ��������Ă��������Ă���܂��B
�@�ŋߒ��ԓ��肵���̂́w�l�Y�~�x�ł��B���O���߂��ɂ������Ă����N�}�l�Y�~�ŁA�ǂ���烂�O���̌���q���Ĉړ����Ă����悤�ł��B�������Ƀl�Y�~�͂��낢���肪���肻���Ȃ̂ŁA���킢���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�������𑖂�������A�����������Ă����킯�ł͂���܂���̂ŁA�����͉��ւɉ����������ɂ����Ă��������܂����B
�@�w�n�N�r�V���x�͓���I�ɖڌ�����܂��B��������ɂ܂œ��荞��ŗ���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�L�ł�����̂��ȂƎv���ċ߂Â��Ă����Ƃ����Ƒ��a�ɉB���悤�ȃV���C�Ȃ�B���͋��\�炵���̂ł���܂肨�t�������������Ȃ������c�B
�@���\�ς�����Ƃ���ł́A�w�L�c�l�x���o�v���܂��B��s���Ȃ��������āA�Ȃ��Ȃ��o����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����A�Ԃ̃��C�g�ɑ����Ē������F�̐K�����Ƃ炵�o�����V�[���͂�����ƌ��z�I�ł�������܂��B�܂��~�̒��ɁA�����̐ጴ�ɐ^����ɏo�đ��Ղƕ����c���Ă����̂���̂�����̂ł��B
�@���ꂩ��̋G�߁A�Ă̕����Ƃ��āw�J�b�R�E�x�����̓d���ɗ��܂��B����ȑ傫�������A�ׂ��d���ɂ悭�~�܂��Ɗ��S���Ȃ���ώ@���܂��B���̂������Ŕh��ɖ��Ă����̂ł��邳�������炠��Ⴕ�܂���B
�@�������A��Ԃ��邳���͉̂Ƃ̒��́w�쐶���ǂ��x�ł��B���܂����Ă���̂��V��ł���̂��B���ނ�������Ɨ��������Đ������Ă��ꂥ�c�B
�@
��133�b�w�������c�x
2007.5/30�f��
�@���N���璷�쌧�ɂ��v���싅���ł��������ŁB�ł��ɓߒJ�܂ł͂Ȃ��Ȃ����Ă���Ȃ��̂ŁA����オ���Ă�̂��ǂ����s���Ƃ��܂���Ȃ��B
�@�M�Z�Ƃ�������Ă�����Ƃǂ����Ă��k�M�̃C���[�W�ɂȂ��āA�M�B���Ă����ƒ��M��A�z���Ă��܂��͎̂������ł��傤���B�ɓߒJ��z�N����ɂ͓�M�B�Ƃ�����������Ԃł��傤���B�w��M�B�O�����Z���[�Y�x����A�����������Ȃ�I
�@�O�U�肪�����Ȃ����̂́A���ꂩ�珑���{�ƃv���싅�A�킪��_�^�C�K�[�X���s�U���ɂ߂Ă��邩��ł���܂��B
�@��_�^�C�K�[�X�Ƃ����A�����ɂ킽���ėD���������A���Ƃ��Đ���ɉh���ɂ߁A�܂���������ɂ��Ƃ����p�^�[�����J��Ԃ��܂��B�O��D��������Ǝ������s����Ƃ��A�l��D��������Ɛ�l�ɂȂ��Ƃ��`���Ɍ���Ă���قǂł��B
�@�ł��̂ł���������N�E��N�D�����Ă��ǂ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B��A�s���炢�w�ցx�ł�����܂���B�ł��A��N�Ɉ�x�A�n������킴�킴�b�q���܂ʼn����ɍs���������炢�͏����Ăق����Ɗ肤�̂��ґ�ł��傤���B
�@�䂪�Ƃ͈�N�Ɉ�x�A�n������킴�킴�b�q���܂ʼn����ɍs���Ă��܂��B���N�ŌܔN�ڂɂȂ�܂����A�ߋ��l��͎O���ꕪ���B�s�s�_�b���ǂ��܂ŐL���邩�A�����ɂ��͂�����܂��B
�@����͉��l��̃`�P�b�g�����܂����B���O�Y����̃��[�e�[�V�������͂����A�K���Ԑ��ł��B�����O����̐���オ��͂����ǂ���B�����̈z�������S���Ă��܂�����A�Ō�́A�����́w�Z�b���낵�x�܂ł̃y�[�X�z���������ł��B���Ƃ͍�_�^�C�K�[�X�������Ă���邾���ł��B
�@�������܂܂Ȃ�Ȃ��̂��O�ԃV�[�c�ł��B�䂪�Ƃ����ɍs�������͂��Ƃ��Ƃ��u���[�L�ɂȂ�A���̓�������t���C�ƕ��E�ł�A�����܂��B�䂪�ƂƑ������悭�A�ߋ��l�N�łR�{�ۑłT�œ_�̞w�R�I��͓�R�����c�B�O�]�O�̂܂ܕ��D����ɓ˓����܂��B
�@�s���I���A���E���Ƀ_���_���Ǝ��_���A���Ǘ땕�����B�Ȃ�ɂ��������Ȃ��������I�����܂����B�u���Ԃ��`�v�Ƃ����̂ă[���t���҂�����̎����ł����A�������Ƃ���ŋ����Ԃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��ƂȂ����A��܂��B�������A�蓹�͒����₵�����ߑ��̐s���Ȃ����̂�ł��B�q���B���ꏏ�ł�����A�ǂ����œۂ�ŗJ�����炵�Ƃ����킯�ɂ������܂���B
�@���āA���߂Ĕs��������q���B�͎��ȏ�ɂ�������B�ł����̂�������̌������A���j�́u���삪�����Ȃ������v���ƁA���j�́u�t�@�[���{�[�������炦�Ȃ������v���ƁA�Ƃ����̂��Ȃ�Ƃ������������ȂƂ���ł��B
�@�ƁA�������ƂŃV�[�Y���͂܂��܂������A������߂��ɂ�����ĉ������悤�B�撣���_�^�C�K�[�X�I
�@
��134�b�w��`���x
2007.6/16�f��
�@�q�����̂��傫���Ȃ��Ă��܂��ƁA�ƂɋA���Ă��ăS���S�����Ă����Ă͎ז��ɂȂ��Ďd��������܂���B�����͓����Ă��炢�܂��傤�B
�@�䂪�Ƃł͂������N���O���炻�ꂼ��Ɍ��܂����C��������U���Ă��܂��B���j�ɂ͒����͂�̂��������ƁA�[�H��̐H��B���j�ɂ͂����C���ۂ����Ă��܂��B
�@���������̒��̒��j�̒��H���ɂ��ẮA�J�X�x�ƒ��ł��B���w�̓o�Z�����������A�݂�Ȃ̒��H������Ă���ƁA�Ԃɍ���Ȃ��i�������͗�߂Ă��܂��j����ł��B����ł������̕��ƁA���o�̓��̕ꂳ��̂������Ƃ�����Ă��܂��B���w���j�q�Ƃ��Ă͂悭����Ă���ƕ]�����Ă����ł��傤�B
�@�ނ��낢�������ɂȂ��Ă���̂́A�[�H��̐H��ł��B�H��w�H�x�݁x�Ə̂��ăS���S�����Ă݂���A�e���r�ӏ܂́w���̃R�[�i�[���I�������x���ň�����������A�Y�ꂽ�t�������ĐQ�Ă��܂�����ƁA�Ȃ�Ƃ��T�{�낤�Ƃ��Ă��܂��B�ł�������ɂ���ȏ��H���ʂ���͂����Ȃ��A���Ǔ{���Ă�炳�ꂽ��A�����Ǝd���𑝂₳��Ă��܂����ƂɂȂ����肵�Ă��܂��B���̂���͂����Ԓ���Ă��Ă͂��܂����A����ł������炪�����݂���ƃT�{�낤�Ƃ���̂ŋC�������܂���B
�@���j�̂����C�|���̓T�{��킯�ɂ͂����܂���B�����K���d�����҂��Ă��܂��B�䂪�Ƃ̃��C�t�X�^�C�����炢���āA�����܂łɓ�l�͓������ς܂��Ă��������B���j�����Z���Ă���A�h����I��点�A���̌�ɂ����C�����Ă���Ƃ�����ƊԂɍ����܂���B���Z��h��̑O�ɏI��点�Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B���ł͂����ԏK���ɂȂ��ĖY�ꂸ�ɂ���Ă����悤�ɂȂ�܂������A�ȑO�͖���������ɋ}������Ă��܂����B���̂���ł͂���ɐi�����āA���o�Z�O�ɏI��点����A�S���̓������̂����ɍς܂��Ă������Ƃ��o�Ă��܂����B
�@���k���ߏ��̐l�̘b�ł́A�������܂����d��������Ƃ����ƒ�͂��܂�Ȃ��l�ŁA�����������Ȃ��Ă������Ă����q���Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ����Ȃ������ł��B���������Ӗ��ł͉䂪�Ƃ̎q�������͊撣���Ă���̂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�ł����Ƃ��ẮA���܂�������`������������ǁA�����ŋC�t���āA���ׂ����ƁE������ق����������Ƃ��p�b�ƌ�������悤�ɂȂ��Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�C�������Ƃ������A�����������Ƃ������A��ǂ߂�Ƃ������A�����Ӗ��Ől�̊�F���f����Ƃ������B
�@���j�E���j�Ƃ��ɂ��ꂩ��܂��܂��Z�����A�ƒ�w�K�╔���Ȃǂ��ׂ����Ƃ������Ă��܂��B����������ς�ƒ낪�����̊�{�A�������蓭���Ă��炢�܂���[�B
�@
��135�b�w�݂͖݉����̏E�x
2007.6/26�f��
�@�Z���ɓ���A�V�N�x�̎d���̖Z����������ƈ�i���������ł��傤���B�_�Ƃł͋t�Ɉ�ԖZ���������ł��傤���B�܂��ǂ���ɂ��Ă��A������ł�����ƈꕞ�A�����ł����݂܂��傤�B
�@����䂪�Ƃ����킵�����藿���́A�Ȃ�Ƃ����B�Β��̎蝆�݂Ɏ��g�݂܂����B
�@���������͕ꂳ��̋��ތ����B�w�Z�ł����E�݂����āA��N�͋Ǝ҂ɐ������˗����Ă���̂ł����A���N�̓y�j�Q�ϓ��Ɂw�Ƒ��ƈꏏ�ɐ�����Ɓx����悵�܂����B���R�ꂳ��͏�����B�w�Z�ɂ��o���ҕs�݂Ƃ������ƂŁA�䂪�Ƃł̋��ތ����Ƒ�����܂����B
�@������A�����O�o����߂�ƁA�Ȃɂ��ł��L���B�����Ύ��ł��ƕ����ɔ�э��ނƁA���X�̒��F���t����O�ɁA�ꂳ��R�Ƃ��Ă��܂����B
�u���������܂��ł��Ȃ��́B�������������Ƃ���H�v
����킯����܂��A������������Ⴀ�����܂��ł��B�Ƒ��ʼn��Ƃ����܂��傤�B
�@������̏o�g�́A�w�����̂ӂ邳�Ɓx���s�{�F���s�A���X�����H��̊Ԃ̓����w�Z�ɒʂ��Ă��܂����B�������̋L�����ĂыN�����āi��������C���^�[�l�b�g�ł����ׂ܂����j�ꓯ�Ɏw�����܂��B
�@�u�܂��͏������B�����Ȃ�z�b�g�v���[�g�ʼn��߂Ă͂�����B�v�ꂳ��Ɏ菇�̒��������߂܂��B�u���t������Ȃ�A�F���ς��܂ʼn��M�B���������낻���ɂ���ƐL�����ɂȂ�B�������Ȃ��ƃE�[�������ɂȂ����܂��B�v
�@�u��������������}���ŗ�p�B�v���j�ɂ�����ł��������Ē��t���J���܂��B�u�����ł������萅�C������Ƃ��Ȃ��Ɩ����o�Ȃ��B�t���m���������Ȃ��Ȃ�܂Ŋ撣�邼�B�v
�@�u�������������ԓ�����݂��B�v�z�b�g�v���[�g�������ቷ�ʼn��߂Ē��t�𝆂݂܂��B�q���B�ɉΏ��̒��ӂ𑣂��A���݂̎�قǂ��B�u��������Ē��t����������r��Ȃ���A�������Ђ˂�o���B�����Ă܂��J���Đ�����������ɝ��ށB���̍H���������̖������߂�̂��B�v
�@�u���悢��d�グ�̊������B�v�ꂳ��ɒ��Ӑ[�����x���Ď������Ȃ���z�b�g�v���[�g�ʼn��M�B�u�܂����A������ȁB�ł���Ώł����ȁB�ł����Ƃ������̓�̕����B�ł��L�������Ȃ��߂Ȃ����B�v
�@���悻�ꎞ�ԁA�Β��̊����I���������B
�@�����A�L���I���������I�ǂ��������Ƃ��A����ł͐����Ƃ͂����Ȃ��A���⎸�s���I�����P��̔��ȉ�`�B
�@����������Ȃ������B�����Ƃ���Ȃ荁�藧�܂ŏ����Ȃ��ẮB���݂��s�\�����B�����Ə��ʂ��A�m���ɐ������Ђ˂�o���Ȃ��ẮB���������r���[���B�w��ŝ���ӂ���قNJ��������Ȃ���B�����A�����`������B
�@�ʂ����ĉ䂪�Ƃ��ꕞ�ł���̂͂��H
�@
��136�b�w�����܂��x
2007.7/3�f��
�@������O�\�N�قǑO�ł��傤���A�{�E�����O�u�[��������܂��āA�e�n�Ƀj���L�j���L�ƃ{�E�����O�ꂪ�ł��܂����B�������Z���̍��܂ł͂��̃j���L�j���L�������ς��c���Ă��āA�x������ی�ɂ悭�ʂ������̂ł��B�ł��A�����Ŏ�������Ă����̂̓{�E�����O�ł͂Ȃ��r�����[�h�ł����B
�@��\�N�قǑO�ɂ̓g���N���[�Y�̃n�X���[�Q�̉e���Ńr�����[�h�u�[��������Ă����킯�ł����A����ȑO�Ɋw�F�Ɠ��X�{�E�����O��ŃL���E���Ă���܂����i�v�[���o�[�ł͂Ȃ��A�����܂ł��{�E�����O��ł��j�B
�@����Ȃ�����A�e���r�Ō����̂ł��傤�A�q���B���u�r�����[�h������Ă݂����v�ƌ����o�����̂ł��B�p�C�I�j�A�Ƃ��Ă͂ق��Ă����܂���B�����s���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�@�Ƃ͌������̂́A���܂ǂ��r�����[�h�䂪����̂��A�Ȃ��̂�炳���ς�킩��܂���B�v�[���o�[�I�ȓX�͉���������悤�ł����A�����w�����V�ׂ�悤�Ȗ��N�Ȏ��Ԃɉc�Ƃ��Ă��܂���B�܂��q���ƗV�Ԃ̂ɁA����O��͍���܂��B�ƂȂ�Ƃ���ς�{�E�����O��ɂ������Ă݂邵������܂���B�����̌��ʁA�ꌬ�̃{�E�����O��Ƀr�����[�h�䂪�ݒu����Ă��邱�Ƃ��킩��A�x����҂��ďo�����Ă����܂����B
�@�z���Ƃ���r�����[�h��̓K���K���A�䂪�Ƃ̑ݐ؏�ԁB������Ƃ��炢�̃}�i�[�ᔽ�����������Ė��Ȃ��ł��B�܂��͕�����̖͔͉��Z�ƊȒP�ȍu�K��B�ȒP�Ƀ��[�������������炳�����ƃQ�[���ɓ˓����܂��B
�@���j�ɂƂ��ăr�����[�h��͂܂��������܂����B���V���i��̕��ʕ��j�ɒ��ڍ���������ƁA�N�b�V�����i��̑��ʕ��̐���オ�����Ƃ���j���ז��ɂȂ��ăL���E�������܂���B�N�b�V�����Ɏ��u���ƃ{�[���܂ʼn����Ȃ��Ȃ��q�b�g���܂���B���傤���Ȃ����J�j�J���u���b�W�i��̓͂��Ȃ��Ƃ��Ɏg���⏕���j���g���܂����A�u������͂قƂ�ǎg��Ȃ��̂ɁA�l�����g���Ă����������v�ƌ�����܂��B
�@���j�ɂƂ��ăr�����[�h�ׂ͍������܂����B�~���̒P�ʂő_�������A���m�ȃV���b�g�ƃN�b�V�������v�Z���邱�Ƃ��ʓ|�������Ďd�����Ȃ��悤�ł��B�u���[���炢�炷��v�Ƌ�s���肱�ڂ��Ă��܂����B
�@���������킯�ŁA���j�͂������C���������悤�ł����A���j�͂��C���X�B�ƂɋA���Ă���ƐV�����ׂ��ۂ߂ăL���E�����A�i�{�[�����Ńr�����[�h������A�S���{�[�����ė��K���J�n���܂����B�����āu�܂����T�s�����ˁB�v
�@���������Ȃ��Ă͂Ƃ��Ƃ�t��������������܂���B�����畃������D���Ȃ̂ł�����ɖ��B�ꂳ�����������ŁA�i���j���������ł��Ȃ����Ɂj�{�E�����O��ɂ������ƒʂ��Ă��܂��B
�@
��137�b�w�H�͍���ɂ���x
2007.7/18�f��
�@����Ƃ����͉̂����Ɖe�����₷�����̂ł������܂��āA�܂��ăO��������Ȃł��ƁA�����ǂ�ł��邾���Ń��_�����炾��A���Ȃ����O�`�A�u����̂������͂���Ō��܂�v�Ȃ�Ďv���Ă��܂��킯�ł��B
�@�O��������Ɛ\���܂��ƁA�Â��́w��l�����x����n�܂�܂��āA��u�[���������N�������w��������ځx�A���������w�~�X�^�[�����q�x�A���V�s���摍�{�R�w�N�b�L���O�p�p�x�Ȃǂ��܂��������܂����A�䂪�Ƃ��p�B�́w���̂ق����x�Ƃ�������ł������܂��B
�@�薼���炨�悻�z���͂��Ǝv���܂����A���Ƃ��Ɠە��q�����ŁA��l���E��ԏ@�B����y��F�B�Ƃ̎�̗l�q���`����Ă��܂��B���̒��ŁA�ە��q�̐S����A�������D�~�������ς��o�Ă���̂ł��B�ŁA�䂪�Ƃ̎q���B�́A��������H�̒m���������ς��d����Ă���̂ł��B�������D�~�Ȃ̂ł����瓖�R���S�͂��܂݁i���̍�j�ł��B�q���炵�����킢�炵�����j���[�ł͂Ȃ��A�����������a�����j���[�ɓ��ꍞ��ł���̂ł��B
�@������̉�b�B�u�킳���Ă������������ˁB�����ł�����Ă݂悤��v�u���Ή��ň��k�L���ė���ł݂����ˁv�u�₫�Ƃ���Ă��܂��̂��Ȃ��v�u���瓤�̂���Ă����Ă����ł�����H�v�u���������ĕ�����H�ׂ����Ƃ���H�v�u�z���͓��k���{��Ȃ�ł���v�u���V���X���H�ׂĂ݂��`���v�Ƃ����悤�ȉ�b�����풃�тɔ�ь����Ă��܂��B
�@�m���Ɏ�l���w���[���x���������݂Ȃ���A���܂����ɍ���܂�ł���̂�ǂ�A�m��Ȃ����́i�H�ׂ����ƂȂ����́j�����ɂ����������Ɍ����܂��B���H�ׂĂ݂��`���Ƃ����̂��悭������܂��B�i���Ȃ��̖����ǂނ��тɁA�r�[�����݂��`���Ɨ}���悤�̂Ȃ�����ɋ���Ă��܂��܂��j
�@�H�Ɋւ���m�����ە��q���ł�����A�u���̂��n�i�^�����m���I�v�u�n�i�^�����Ă��̂��������Ē��̂��Ƃł���v�Ƃ��u�i�}�R�̐��Ԃ́c�v�u�����R�m���^�̂��Ƃł���v�Ƃ��u�r�[���c���́H�������烂�c�ς̂Ƃ��g���Ƃ��炩���ł����v�Ƃ��u�r�[���A�����Ȃ��ˁA�����Ɛ���ĂȂ���Ȃ��́v�Ƃ����������ɂ����Ă��܂��܂��B�l�O�ł���ȂƂ�����ꂽ��A�Ƃłǂ�ȋ�������Ă�̂������܂�Ă��܂��܂��B
�@13�ƂX�ŋ������c�E�ɂȂ��Ă��܂����q���B�ł����A���ۂɋ��������j���[������Ă݂�Ɣ����͐^����ɕ�����܂��B���j�͂Ђƒʂ蒧�킵�Ă݂āA�u����͂�����ˁv�Ƃ��u��l�̐H������͕������v�Ƃ��꒚�O�Ɍ����܂����A���j�͂قƂ�ǎ�������u�s�C���Ȃ��̂��c�v�Ƃ������Ă��܂��B
�@����Ȃ킪�܂܌����Ă�ƈ�l�O�̓ە��q�ɂȂ�I�i�Ȃ��ł������c�j
�@
��138�b�w����ł̂��x
2007.8/5�f��
�@���쌧�Ńv���X�|�[�c������@��Ƃ����̂͂��܂葽���Ȃ��A���������ɓߒn��ɂ������ẮA���O�̊O���Ă��炢�ɑa���Ȃ��̂ł���܂��B����ȂȂ��A���ɂ���Ă��܂����M�Z�O�����Z���[�Y�I
�@����䂪�Ƃ��ϐ킵���̂͂V��21���A�ΐV���A���r���b�N�X��B�U���̔ѓc���c����ł͐ΐ�~���I���X�^�[�Y�ɉ������A������ʼn��ʑ���ɉ������Ă������̂ƐM����������ցB
�@���ʂ͊F�����m�̂Ƃ���W�\�X�̎S�s�ł����B�_����������ƁA�͍��̎����Őɔs�ł́H�Ƃ��v���ɂȂ邩������܂��A���e�I�ɖ��c�ł��e���ȕ������ł����B���̂��e���Ȏ����ɓ{��S���Ȃ̂��䂪�Ƃ̒��j�ł��B
�@�w�Z�̕������Ŗ싅���ɏ������钷�j�B���K�������̃t�H�[���[�V������J�o�[�����O�̓��������܂�ɂ������̂������˂����������ϐ�Ɉ�������o�����̂ł��B���A�����̂��Ƃ͒I�ɏグ�ăO�����Z���[�Y�ɂ͌��������������܂��B�i�m���Ƀ~�X��A�s�p�ӂŖ����ʂȃv���[�������A�����w���̂���{�ƂȂ�ׂ������͏��Ȃ������̂ł����c�j�v���Ȃ̂ł�����A�������𓊂�����A�����֑ł��Ԃ�����A�������߂����肷��̂͂�����܂��B�����Ɓu����̓v���[���[�Ƃ��Č��K��Ȃ���v�Ƃ����v���[�������Ăق��������Ǝv���̂͒��j�����ł͂���܂��܂��B�u���ꂶ�Ⴄ���̊w�Z�̏㋉���̂ق��������v�Ƃ������j�̌��t�ɂ����Ȃ�������܂���B�i���̏ꍇ�́g�����h�͏����������珟�Ă�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A��{�ƂȂ镔���������Ƃ������Ɓj
�@�ŁA��������O�����Z���[�Y�𑼎R�̐Ƃ��āA���j�̓������悭�Ȃ������Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��Ƃ��낪�l�߂̊Â��Ƃ���ł��B
�@���̎����ϐ����Ԋy���݂ɂ��Ă����͎̂��͎��j�B���������A�O���[�u�Ў�ɗE��Ŏ��������肵���ނ̖ړI�́w�t�@�[���{�[���L���b�`�x������B�������e���A���s���ǂ����ł��悭�A�����Ђ�����Ƀt�@�[���{�[����ǂ������܂��B�������͏�O�ւ̑ŋ���ǂ����ߋ��ꂩ��o�āA�����������ɑҋ@���܂��B����ȓw�͂ɂ�������炸�A�t�@�[���{�[���L���b�`�͂Ȃ炸�A��������s�����ɃQ�[���Z�b�g���}���܂����B
�@������́A�����������ɍs�����̂ɃO�����Z���[�Y�������Ďc�O�������Ƃ������Ƃ͂���܂����A�z�[���������T�{������ꂽ��A�I��T�C���{�[�����L���b�`�ł�����Ƃ܂��܂��Ȗ����x�ł����B���]�����킹�Ă��炤�Ȃ�A�i�ɂ��₩�ȉ����������͂Ȃ����j�o�b�g�̊���������A����̘r�̕��艹��A�x���`�̖쎟����������悤�ȐÂ��Ȗ싅���������B�������y���ނ�Ȃ��āA�싅�𖡂킢�����Ȃ��B
�@
��139�b�w�K���o���[�x
2007.8/28�f��
�@�ċx�݂͖Z�����B�ƂŎq�ǂ��ƗV��A�C�Ŏq�ǂ��ƗV��A�R�Ŏq�ǂ��ƗV��c�B
�@���N�̃L�����v�͂�����Ǝ���������āA�e���g���ł͂Ȃ��o���K���[�ɔ��܂��Ă݂܂����B����K�ꂽ�̂͊����Ð�s�A�[�X�L�����v��B���Ð�s�Ƃ͂������̂́A�ؑ]�̗����i���ؑ]�Ƃ������������{���ɂ���ƍ���m��܂����j�A���쌧�������Əo�������̏��ł��B
�@�L�����v��͗[�X�R�̒����ɂ��Ȃ�傫���K�͂œW�J���Ă��܂��B�o���K���[���������������сA�����w�Z�̗ъԊw�K�ɗ��������B�������܂��ċx�ݏ����Ƃ������Ƃ������Ă��A���p�҂̓|�c�|�c�B���������猩����Ƃ���ɂ͈�Ƒ��������Ȃ��悤�ȐÂ����ł����B
�@���āA����̓e���g���ł͂Ȃ��̂ŁA�H���ɏd���������܂��B�e�[�}���w�q���B���A��ᴂł��т𐆂���悤�ɂȂ�x�ɐݒ肵�A���j���[�͂��т��Ȃ��Ǝn�܂�Ȃ��J���[���C�X�Ɍ��肵�܂����B
�@�u��������Ă݂�v�Ƃ܂铊�����Ă��ł���͂�����܂���A�e�Ƃ��Ă�������Ǝw�����܂��B�u���߃`�����`�����Ȃ��p�b�p�A�W���E�W���E����������Ђ��āA�Ԏq�����Ă��ӂ����ȁv�Ƃ������t���炢�͎q���B���m���Ă��܂����A�ǂ��܂ł����߂ŁA�ǂ̂��炢���p�b�p���킩��܂���B�ɂ������炷���ɕ����Ă���̂ɃW���E�W���E����Ȃ��̂��A���Ђ������Ƃ��H�ׂ���̂��A�ȂǂȂǎq���B�ɂ͂܂��܂����̌��Ȃ��Ƃ���ł��B
�u�����Ȃ苭�ɂ�������ǂ��Ȃ�H�v
�u�ꂾ���ł���v
�u�������ᴑS�̂ɔM�����܂ł����߂��B�ӂ��̐^��G���Ċm���߂�v
�u�W���E�W���E�����Ă��A�܂��H�v
�u�悭����A�܂������C���������Ă邾��B�܂�܂��Ă������z���������ĂȂ����Ă��Ƃ��v
�u�����I�����y�������Ȃ�������B�����C����R�Q�ɕς�����u�Ԃ��I�v
�u����ԔM���̂͂ǂ����H�v
�u��v
�u������ꂩ��͂����Ă�邱�ƂŔ�ᴓ����������v
�@�ƁA�����ӂ��Ƀe�N�j�b�N�����łȂ��A�����l���闝�R�Ə؋��������Ă����܂��B���R�Ə؋���̌��̒��ɍ��荞��ł��̂���Ȃ̂ł��B�������邱�ƂŁA�ɉ����ėՋ@���ςɑΏ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B���ꂪ������Ƃ������ƂŁA�e�N�j�b�N������`����̂́u��点���v�����ŋ��������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�ŁA�݂����蕃����̎w�������q���B�A�r���������̂͗����̔ѐ����B����ȂɗD�����Ȃ�������͖ق��Č��Ă��܂��B����ƁA�Z���l�ł����Ȃ��狦�͂��ĉ��Ƃ������グ�܂��B
�@�����I���܂��B�����Ƌ��F�`����I�i�Â��H�j
�@
��140�b�w�Ă̐������x
2007.9/2�f��
�@�ċx�݂͖Z�����B�ƂŎq�ǂ��ƗV��A�C�Ŏq�ǂ��ƗV��A�R�Ŏq�ǂ��ƗV��c�B
�@�ċx�݂Ƃ����ƁA�Ȃɂ��Ɛ������ɐG�ꍇ�����Ƃ����������ł�����܂��B���������N�͂��܂葽���̐������Ƃ͐G�ꍇ���܂���ł����B���̂��Ɍ��\��ې[���G�ꍇ�����Ƃ��ł��܂����B
�@�ЂƂ̓Z�~�B���j�̉ċx�݂̎��R�������w�Z�~�̉H���̊ώ@�x����������ł��B
�@�[���A�߂��̉ʎ����ɗc���T���ɏo�����܂��B�ڂ̍����ӂ�𒍈Ӑ[�����Ă����ƁA�̂��̂��ƒn��ɏo�Ă����c�������܂��B������Ȃ��߂܂��ĉƂ̒��̎~�܂�Ɏ~�܂点��Ώ��������B���Ƃ͂Ђ�����ώ@�ł��B
�@�ߌ�X���߂��A�H�����n�܂�܂����B����ƃA�����ƌ��Ă���ԁA30���قǂő̂��S���o�Ă��܂����B�ӊO�ɂ������Ȃ��ώ@�I�����A�Ǝv�����Ƃ��낪�������炪���������B�H���L�сA�F�������ꂽ�A�u���[�~�F�i���F�j�ɂȂ����̂́A�����T������B�������Ɏ��j�̓_�E�����ĐQ�Ă��܂��A�Ō�͕������l�ł̊ώ@�B10���Ԉȏ��������Ĉ������N���Ă����Z�~�́A���h�Ȑ����ɂȂ�A�閾���ƂƂ��ɊO�ɔ�ы����Ă����܂����B
�@�ӂ��ڂ̓T���V���E�E�I�ł��B�V�тɍs�����Ƃ���k�J�Łi������ɂ��ꏊ�͕��������Ă��������܂��j
�u�����̕ӂȂl��邩�Ȃ��H�v
�u�l�����Ⴂ���Ȃ����ǁA���̕ӂɏZ��ł�̂̓T���V���E�E�I���炢���Ȃ��v�ƌ����Ȃ���T���Ă�����\�z�ʂ�o�Ă����̂��ʐ^�̃T���V���E�E�I�ł��B�̒��T�p�قǂ̂��킢����ŁA���߂Č����ꂳ��́u���킢���v�ƘA�Ă��Ă��܂����B���j�Ǝ��j���������ɋ�����������ꂽ�炵���A���낢��Ɗώ@���Ă��܂����B���Ɏ��j�́w�T���V���E�E�I�̖��O�̂����́A�R���̂ɂ��������邩��x�Ƃ������Ƃ�m���Ă���A����ɂɂ����ł���܂����B�����Ă��̌��ʁu���L�������v�ƌ��_�t���܂����B
�@�ώ@�タ���Ɠ������Ă��܂������A�L���Ȏ��R�ɐG�ꂽ�����͒����c���Ă��܂����B
�@�O�ڂ̓C���i�ł��B�Ă̍P��A�����ł̋��̂��݂ǂ�B�����Ȃ�j�W�}�X�������Ƃ���ł����A���N�͂ǂ������킯���C���i�������ς��B
�@���j�͂�����l�ŕ߂܂�����悤�ɂȂ����̂ŁA�ق��Ă����Ă��ǂ�ǂ�߂܂��Ă��܂��B���j�͂܂������܂ł͂����܂���B������̋��͂āA�����Ƃ���ɒǂ�����ł����ĕ߂܂��܂��B�����߂܂��āA���肰�Ȃ��߂�₷���Ƃ���ɂ����Ă����̂́A�{�l�̃v���C�h�������Ȃ��悤�ł��߂Ȃ����ł��B����Ȃ킯�Ō��\�����Ԃɂ킽���ăC���i�Ƃ�肠���Ă��܂����B
�@�������Ƃ�����ȉāB�����Ȗ��ƐG�ꍇ���Đ������Ă��ꂽ���ȁH
�@
��141�b�w�o�C�V�N���x
2007.9/28�f��
�@�ŋ߁A���j���₯�Ɂw�G�R�x�ɓ��ꍞ��ł��܂��B���������͊w�Z�ŃS�~�����{�݂̌��w�E�w�K���������ƁB����Ď���|����̓S�~���ł����B��������₪�Ēn�����ւƔ��W���A�G�l���M�[����A���Ԍn�ɂ��Ă���ƌ��͐s���Ȃ��悤�ł��B
�@�����̃K�\�����̍����ɂ͕����܂��B�����Ē��쌧�̓K�\�������i�̍����ł͑S�����w�Ƃ̂��ƁB������Ƃ��o�����̂��тɁA�u��km����������K�\������́��~���B���ꂪ�������ȁE�H�ׂ�ꂽ�ȁB�v�ƒQ���̂��K���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�ƌ������Ƃ��ӂ܂��܂��āA�䂪�Ƃł͎��]�Ԃ𑽗p���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�@���Ƃ��ƕ������]�ԍD���Ƃ������Ƃ�����A���j�E���j�Ƃ��Ɏ��]�Ԃ��悭���p�����Ă��܂��B�Â��͑O�̃x�r�[�V�[�g�Ɏ��j�A������̃`���C���h�`�F�A�[�ɒ��j���悹�ۈ牀�ɒʂ��Ă������ォ��i��11�b�Q�Ɓj�A���ꂼ��̎������K���o�āi��45�b�E��64�b�Q�Ɓj�A���j�ɂ������ẮA�V����͌��܂ł̃T�C�N�����O�ɏo�����邵�܂i��91�b�Q�Ɓj�B�i�ߍ��A�W�c�łقǂ̋��������]�Ԃő��j���邱�Ƃ����x���V���L���ɂȂ��Ă��܂����A����Ȃ��ƍ�����L���ɂȂ邱�Ƃ��H�Ƌ^�⎋����䂪�Ƃł��B�j�Ȃ��ѓc�{���V�����X����U�������Ȃ��̂��s�v�c�Ȃ��炢�ł��B�i�܂��A�������]�Ԃ��D���Ȃ����ŁA�w�r�[�ȃ��[�X�ɂ̂߂肱�ޗ\��͍��̂Ƃ��날��܂���B�j
�@���ł́A�������͂ł��邾�����]�Ԃōs���܂��B�����Ɏ��Ԃ�������̂��B��̌��_�ł����A�n���ɗD�����A�K�\��������[���B�������A�����ɓ��镪�������������Ȃ��̂ŁA�K�R�I�ɔ������̗ʂ������Ă����܂��B���܂��Ɍ��N�E�̗͍��ɂ�����Ĉ�Ύl���I���]�ԃo���U�[�C�I
�@�����āA���N�̃j���[�J�}�[�́w�܂肽���ݎ��]�ԁx�B�܂肽���ݎ��]�ԂƂ����Ă��A26�C���`�̊O���U�i�ϑ��Ƃ������\�����^�C�v�B������Ԃ̉ב�ɐςݍ��݁A���{�S���������������ő���܂���܂��B
�@�ƁA�����Ƃ����������ł����A���Ԃ͂��Ȃ�Ⴂ�܂��B���]�Ԃ������ďo�����Ă��A���]�Ԃő��邱�Ƃ����C���̖ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA���{�S���������������ł�������A���傢�̂�Ɏg���Ă��邾���ł��B�ނ���A�킸���ȋ���������̂��ʓ|�ɂȂ��Ă��܂��Ď��]�Ԃ�������Ȃ��A�ƌ����̂�����ł��傤�B
�@�ł������]�Ԃ̈�ԗǂ��Ƃ���͂��̎�y���E�����ȂƂ���ł͂Ȃ����Ƃ��v���킯�ł��B���������������]�ԍD���ɂȂ����̂��A�Ԃ�d�Ԃɏ��̂��ʓ|����������Ƃ������R�B������Ǝ���ۂ����������܂����A��{�X�^���X�͖ʓ|�������̂����₾����B
�@�Ƃ���ƁA�Ƒ��݂�Ȃ�ʓ|��������Ɉ�������ł���Ă��Ƃ��H���A����͂�����Ȃ��c�B
��142�b�w��������炢�́x
2007.10/10�f��
�@�H�̍s�y�E�X�|�[�c�V�[�Y�����}���܂��āA�y���݂̈�ɂ��ٓ����������܂��傤�B
�@�䂪�Ƃł͂��ٓ������ޗp�ӂ���Ă��܂��B��́A���쎞�Ԗ�ꎞ�ԁA�ʂ�L���ɂQ�`�R�ٓ̕����ɕ����Đ�����w�ꂳ��ٓ��x�B������͐��쎞�Ԗ�T���A�ʂ�E�h�{�o�����X�����D���������ٓ����ɋl�ߍ��ށw������ٓ��x�ł��B�ꂳ��ٓ��́A��ɍs���֘A�̐��̓��ɗp�����A���ٓ����J�������Ɂu�킟�I�v�Ƃ�����т����������ꍇ���p�B�ł��B������ٓ��͂Ɛ\���܂��ƁA�H�����Ԃ��������Ƃꂸ�A���킽���������̓��̃��V�݂����Ȃ��́B�ٓ����J���O�Ɂu�Ӂ[�v�ƈꑧ���悤�ȏꍇ���p�B�ł��B
�@���O�̂Ƃ���ꂳ��ٓ��͕ꂳ�A������ٓ��͕������̂ł����A���g�̈Ⴂ�͈�T�ɕ����ʓ|�������艮�ŁA�ꂳ�^�ʖڂ�����Ƃ������R�����ł͂���܂���B��l�̐�����ɑ傫����������Ă���̂ł��B
�@�ꂳ��ɂƂ��Ă��ٓ��Ƃ����̂́A�܂��ɍs���Ȃǂ̐��̓��ɐH�ׂ���̂ŁA�u�킟�I�v�Ƃ�����тƂƂ��ɊW���J������̂������̂ł��B�܂��A���̎q���L�́w���ٓ����J�x��w�����������������x�����Ċy���ނ��̂Ȃ̂ł��B
�@���s�o�g�̕�����́A���w�Z����ٓ��ɂȂ�A�H������̍��Z����������H�ׂĂ����̂��ٓ��B�܂�A���̓��̃��V�݂����Ȃ��́B�ٓ����I���đ����������̍s���Ɉڂ�A����Ȃ��̂������̂ł��B
�@���R�A�H�ׂĂ������ٓ��̒��g��������͂��ł��B�ꂳ��̕ꂳ��i�������j�����ĔN�ɐ���̂��ƂȂ玞�Ԃ���Ԃ������Ă������Ƃ��\�z����܂��B�N�ɐ����A�Â��������������������Ă�����̂�H�ׂĂ����ꂳ��ɂƂ��Ă��ٓ��Ƃ͎��R�Ƃ����������̂ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B
�@������̕ꂳ��i�������j�͂����͂����Ȃ������͂��ł��B���������Z�������Ԃɑ吷��ٓ̕������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�Â��������Ⓙ�����H�ނ��g���Ȃ�Ė����Ɍ��܂��Ă��܂��B���q����̔����́w���������E�܂����x�ł͂Ȃ��w���Ȃ��E���傤�ǂ����x����Ȃ̂ł�����A���V�ɋ߂Â��Ă����̂͂�����܂��ł��傤�B
�@�����������j�̂�����ނ̂��ٓ����q���B�̓`���C�X���܂��B�܂��s���̂Ƃ��������ٓ���H�ׂȂ����j�͕ꂳ��ٓ����`���C�X���܂��B���j���s���̎��͕ꂳ��ٓ����`���C�X���܂����A�����Ȃǂł͕�����ٓ����`���C�X���܂��B�u�H�א���ɂȂ��Ď����ʂ����߂�悤�ɂȂ������v�Ƃ���Ӗ����������v���Ă����̂ł����A�����������ٓ���I�ԗ��R���Ĝ��R�I�I
�@�u�ꂳ��ɂ���܂�ʓ|���������Ȃ����A������q�}���������c�B�v
�@
��143�b�w�P���`���[�x
2007.11/6�f��
�@���j�����A��ԔM�S�Ɏ��g��ł���̂́w���{47�s���{�����e�x�B���̂��Ƃ͂Ȃ��A���{���̌����ƌ������ݒn���A�n�悲�ƂɊo����Ƃ��������̂��̂ł��B
�@���������̓`���V�ɓ����Ă����w���ӂ�ŗ�������{�n�}�x�Ƃ������̂������ƁB�ʂ�Ă����v�ȑf�ނɒn�}���v�����g����Ă���A�����ʼn��߂�ƌ����ƁA�������ݒn���\�������Ƃ������̂ł��B�����������͑債�ċ������Ȃ������ɂ������߂邾���������̂ł����A���������w���́w���ӂ�ŗ����鐢�E�n�}�x�Ń��[���b�p�̍�����S���o���A�݂�ȂɎ������n�߂Ă���A�����S�ɉ������̂��җ�Ɋo�������܂����B
�@����܂ł̓J���X�̍s���������̂��A�Ȃ��Ȃ����C����o�Ă��܂���B�o�Ă����Ƃ���u�����́����n�����o�������B���o���āI�v�Ƃ���I�ڂ��܂��B��T�Ԃقǂňꉞ�S���o���Ă��܂����悤�ŁA���ł͒n�}�Ȃ��ł����悻�̈ʒu�W�܂ŕ������Ă���悤�ł��B�����Ă���Ɋ����������ׂ��A��z�c�ɓ����Ă���w���{�n���N�C�Y�x��10��قǏo�肵�Ȃ��ƁA�e��Q�����Ȃ��Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@����Ȕw�i�̉��A�������ݒn�ɋ�����������������ԂŁA���j�͊w�Z�̎Љ�w�Œ���s�ɍs���Ă��܂����B
�@���w��́A���쌧���E�P�����E�m�g�j�����Z���^�[�B���̑��A�ԑ�����I�����s�b�N�{�݂⌧�s�̎{�݂߂�Ƃ����R�[�X�B�i���j�͂Ƃ��Ă��y���݂ɍs���ė��܂������A����2003�N�̑P������J���̐܁A�Ƒ��݂�Ȃł��̃R�[�X�ɍs���܂����B�����܍̎��j�̋L���ɂ͂Ȃ��悤�ŁA�������ŐV�N�ȋC�����ōs�����݂����ł��B�j
�@�w�K�I�Ƀ��C���͒��쌧���ł��傤�B���������傤�nj��c��Ƃ������ƂƁA�m�����L���l����n���Ȑl�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�����q���B�̋����͍��ЂƂB�ً}�h�ЃZ���^�[�̊��C���y�Y�b�ŏo�����炢�ŁA���Ƃ́c�ł����B
�@��Ԉ�ې[�������̂͑P�����̌���d���肾�����悤�ł��B�O������u�G��Ȃ�������ǂ����悤�B�ǂ�Ȍ`�̌��Ȃ́H�v�ƃh�L�h�L�ŁA�A���Ă���Ȃ�u�G�ꂽ��A�^���Â������A���������B�v�Ƌ����C���ɘb���Ă���܂����B���y�Y�ɎU�Ǝ������h�q������������Ƃ��ƂĂ����ꂵ�������݂����ł��B
�@�m�g�j�����Z���^�[�̎v���o�͂���ς�i���j�̎����l�j�N���}�L�[�ł����B�u���[�o�b�N�̑O�ɐ����̗F�B�����������������������ƂȂǁA���ꂵ�����ɘb���Ă���܂����B�吨�̐l���Z���������āA����ƕ������o���オ�邱�Ƃɂ��т����肵���悤�ł����B
�@�n�}�Ŋo���āA�����������čs�������s�߂���͗L�Ӌ`�������݂����ł��B����������[���b�p���o�����̂Łc�H
�@
��144�b�w����x
2007.11/22�f��
�@���쌧��M�_�Ǝ�����̈�ʌ��J�Ƃ����̂ɍs���ė��܂����B�ꂳ��͎d�����Z�����A���j�͒��ԃe�X�g�O���O�A�Ƃ������ƂŎQ���҂͕�����Ǝ��j�̓�l�����ł����B
�@���쌧��M�_�Ǝ�����Ƃ����A���́w�쐅�x�A�������́w�T�}�[�v�����Z�X�x���J�������Ƃ���Ƃ������ƂŁA����Ӗ���ϐg�߂Ȏ{�݂Ƃ������܂��B�n�}��ł����X�����s�c�ɂ���A���n����͑�ϐg�߂ȂƂ���ɂȂ�܂��B�������A��������ʂ�߂������ŗ�����������Ƃ͂Ȃ��A����̈�ʌ��J�ŏ��߂ĖK��邱�ƂƂȂ�܂����B
�@�ߑO�\��������J�Ȃ̂�10���ɂ��킹�ďo�����܂����B���������̂�10��10�����A���łɒ��ԏ�͂����ς��A��Ɏ�ɑ����i�Ȃǂ��Ԃ炳�����l�ł������������Ă��܂��B�o�x�ꂽ���ɂ݂��܂������A�撅500�l�̃n�[�u�c�����炦�����A�撅100�g�̃R���j���N���̌��ɂ��\�����߂܂����B
�@����̑_���́A��ԕ�����ꉟ���w�R���j���N���̌��x�A��Ԏ��j����ҁw�_�Y�����H�x�A�O�ԁw����������w�x�ł����B���H�R�[�i�[�ƁA�R���j���N��肪��s�������߁A������w����n�߂܂����B�������\��������A�ޏ�U����������Œ��쌧��M�_�Ǝ����ꂪ�w�쌎�x�Ƃ��������J�����Ă������Ƃ�m��܂����B�쐅�Ɠ�����z����ł����Z���̐��Ƃ������Ƃ��A�����ÁX�I�������H�R�[�i�[�Ŗ������܂����B���������ڂ����Ɛԗ��̒��Ԃ�����A������ƕ��G�Ȗ��킢�ł����B���j���E�͐ԗ��́w�����Â��x�B�L�����Â������悤�ŁA�Â݁E�H���̃o�����X�ō��B����̔̔����҂��������ł��B�����E�͂���ς胊���S�w�V�i�m�X�C�[�g�x�B����͔̍|�_�Ƃ̑����Ɋ��҂������ł��B
�@�������ɂȂ�l���݂��r��Ă��܂����B���悢��R���j���N���ɓ˓����܂����B�R���j���N���͕���������̌��A���N���N�ŊJ�n�ł��B�܂��͐����𐅂ƈꏏ�Ƀ~�L�T�[�ɂ����܂��B���S�ɂ��Ȃꂽ�Ƃ���œ�ɓ���āA���������Ȃ��狭�ʼn��߂܂��B������Ǝ��j�ł���邪��鍬���č����č����ăl�o���Ă�����A���_���J���V�E�����n�t�i�v����ɏ��ΊD�t�j�𓊓��I����ɓ�l�ō����č����č�����B�l�o�l�o���v���v���ɕς���Ă�����A��߂Ȃ������ɋ����p�b�N�Ɉڂ������܂��B���ł͂����܂łŏI���A���Ƃ͉ƂɋA���ė�߂Ă���B
�@���H�Ŗ����A�R���j���N�ƃn�[�u�c�ł��y�Y�����ς��A�喞���ŋA���Ă��܂����B
�@�����A�R���j���N���͎d�グ�ɁB���������Ă䂪���Đ��ɐZ���ăA�N�����ł��B���j���}���ɐ������ɑ劈��A�����������܂����B���R�ӌ�т̈�i�ɁB
�@���҂ƕs���ň��
�u���`���܂��A��i�I�v
�@
��145�b�w�����X�g�x
2007.12/9�f��
�@���쌧���ɂ��e�[�}�p�[�N������������܂����A����͂��̒��́u�M�B���K�_�ƌ����@�`�����̐X�v�ɍs���Ă��܂����B
�@���̓��͒��j��������蕔���ł��炸�A���J���~�莟�j�ɂƂ��Ĕ��ɑދ��ȓ��ł����B�u�ǂ����V�тɂ�������`�v�Ƃ������N�G�X�g�ɉ����s�����Ƃɂ����̂̓`�����̐X�ł����B
�@���̓`�����̐X�ɂ͎��N�O�Ɉ�x�s�������Ƃ������i���j�͊o���ĂȂ��j�A���̎��̂��Ƃ��v���o���A�u���ЂƂʔ����Ȃ����Ǎs���Ă݂邩�v�Ƃ����Ȃ�����ꂵ�܂����B
�@�x���ł���ɂ�������炸�A���̓��͒�����̏��J�̂��������ɂ��q�����܂肨�炸�A�i�������`�����̐X�͉J�V���͓��ꗿ�������ɂȂ�܂��B�J�オ��̒����o�|���Ă����̂��x�X�g�H�j�����ȂƂ���𑶕��Ɋ��\���邱�Ƃ��ł��܂����B���낢��Ȃ��X�ɓ����āA���H�E������������A�V���L����݂����ԁi�������J�ŔG��Ă���j�B
�@�҂����Ԃ��Ȃ��̂ŁA�����̌��R�[�i�[�Ŋy����ł݂悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B������̓\�[�Z�[�W��������Ă݂����Ǝ咣���A���j�̓A�C�X�N���[���������Ă݂����Ǝ咣���A�ꂳ��͋��̓����̌������Ă݂����Ǝ咣���܂����B�ǂ�����͓I�ł����A����肾���͎��Ԃ̓s�������킸�f�O�B�\�[�Z�[�W�ƃA�C�X�N���[������邱�Ƃɂ��܂����B
�@�\�[�Z�[�W���͌��t�Ō����ƂƂĂ��ȒP�B�r�҂��̓ؓ��ɒ������ƂȂ������ĒO�O�ɍ�����B�\�[�Z�[�W�K���ɋl�߂�B�r���̒[���ă����ɂȂ�Ȃ��悤�ɓ������������B�K���ȑ傫���ɂ˂���B䥂ł�B�H�ׂ�B
�@�ł�����Ă݂�Ƃ��ꂪ�Ƃ��Ă��ʔ����I�r�҂����̓~���`�ƈႢ�A���������v�`�v�`���Ă��Ă��ɐS�n�悢�B�\�[�Z�[�W�K���ɋl�߂�̂��͂����ł̓_���A�c�q��Ɍł߂������Œ��J�ɋl�߂Ȃ��Ƃ��܂������܂���B�r���ɋl�߂�̂́A��C������Ȃ��悤�ɁA���ψ�ɓ�������悤�ɁA�����o���W�Ɨr���L���W���������킹�Ă��Ȃ��Ƃ��܂������܂���B�˂���̂��K�ȑ傫���ɁA�₳�����˂����Ă����Ȃ��Ɨr�����j��Ă��܂��܂��B������Ǝ��j�������|�������A���͂��Č����Ɋ������܂����B�i���܂ł����ȑ̌���������Ă��܂������A���͂��K�v�ȓx�����ł��Ȃ��ʂɃ����N�C������ł��傤�j
�@20���قǂ������䥂łĐH�ׂ��\�[�Z�[�W�͎��ɂ������������B�ۛ��ڂ���ō��܂ŐH�ׂ��ǂ̃\�[�Z�[�W�������ł����B����͖��t���Ȃǂ��C���ł������A���������Ƃ�������������ōD���ɂ���Ă����Ƃ���Ɋy���߂�ł��傤�B
�@�u���ЂƂv�Ƃ������Ă��܂������A���ɗL�Ӌ`�Ȉ�����߂����܂����B���ꗿ�����Ȃ̂������ł��˂��B
�@
��146�b�w�Ȃ����x
2007.12/15�f��
�@������ˑR�ꂳ�u����Ă����H�ׂ��`���v�Ƒ����o���܂����B�����Ă݂Ă��ʂɗ��R�₫���������������킯�ł͂Ȃ������ł��B��͎c��܂����A�����͕ꂳ��̗v���ɉ�������Ă���B
�@����������Ă��̍����Ȃm�������Ⴀ��܂���B�����������̐l���j�����Ă��Ȃ�Ĉ���H�ׂ����Ƃ�����܂���B�q���B�ɂ͖��m�̐H�ו��ł��B����̓v���ɗ��邵������܂���B
�@�����q���B�ɒ������˗��A�^�E���y�[�W�ł���Ă��������B����܂���ł����B���D�ݏĂ��Ō����B�X�܂͂�������܂����A����Ă�������Ă��邩�͍L���̃y�[�W�ɂȂ��̂ł킩�������Ⴀ��܂���B��������Ƃ�������ɂȂ�܂����B
�@�ŁA������B�ѓc�X���ɔ������ɏo�|���A�X�������낤��Ƃ��Ă���܂�����w����Ă��x�̂̂ڂ蔭���I�u�ꂳ��I���ꂠ��I�v�Ƌ����܂����A���̕ꂳ��̓n�e�i��B����������A�����Ō����o�������Ƃ��Y��Ă����̂����炭�����āu��������Ă��A�������H�ׂ��������A������`�I�v�Ƃ������ƂŌ���X�B
�@���X�l�C�i���o�[�����𒍕��������B��������Ă��Ă��ꂽ�X������ɍ������ڍׂɕ����āA���悢����H�J�n�B�܂��͌����������ؕꂳ��̒���ł��B�ŏ��ɌŌ`��������S�ɏ悹�A���Ăł���������悤�ɍL���Ȃ���Ă��܂��B�ׂ����Ȃ��Ă���Ȃ肵�Ă�����h�[�i�b�c��̓y���z���A���̒��ɉt�����������ӂ�Ȃ��悤�ɓ����B�O�c�O�c������S�̂𝘝a���ďo��������B���Ƃ͂��̂��̂��A�����Ȃ��Ăʼn����t���ďĂ��Ȃ��炱��������ĐH�ׂĂ������Ă���B
�@�v���Ă����قǓ������Ȃ������̂ŁA���Ɠ�i�������āA������Ǝ��j�ň���������Ċ��������܂����B
�@���������Ȃ�����Ȃɂ��H�ɏW���ł��Ȃ��B���p�̂��Ă��������āA����ȏ����Ȃ���Ώ��������ŋC�ɂȂ��Ă��������Ȃ��̂ł��B���߂��ɂ�����Ƒ傫�����Ăł���Ă݂��Ƃ���A���̂͂��܂����܂����A���Ă��M���Ȃ�߂��āA���ɉ^���A�O���Ώ��������ɂȂ�܂����B�Ȃ��Ȃ����܂����Ƃ��������Ƃ�����߂܂����B
�@����Ȃ��Ƃ������Ȃ�����A�O�l�O���H�ׂ�Ƃ������ӂ������Ă���B�����C�ɐH�ׂ��Ȃ��Ԃ�A���Ԃ�������A������薞���������邭�炢�ł��B���X�����G���čs���ł������Ȑ����ł����̂ŁA���܂ł����������Ȃ��A�X���o�Ă��܂����B
�@�q���̂��Ꮙ�̌��̊��z�́u�������������B���nj��̒����y���Ώ����ۂ���B�v�m���ɓ���قǃq���q�����Ă܂����B
�@
��147�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�P���̏́x
2008.1/6�f��
�@�앧�v�����@���X��12�����Ƃ����{�������m�ł��傤���H�s�[�^�[���C���Ƃ����p���l�̒����ŁA���E���ɓ앧�u�[���������炵������ł��B
�@���̒��̂V���̏͂Ɂw�y�^���N�x�Ƃ����X�|�[�c�̂��Ƃ�������Ă��܂��B�ڕW���Ɍ������ēS���𓊂��āC�߂Â�����������̋��Z�ł����A���̖ʔ����Ƃ������猾�t�ł͐s�����܂���B�ŁA�䂪�Ƃ͂��̃y�^���N�ɂ͂܂��Ă��܂��܂����B
�@���������͎O�N�O�̔шɋ���t�H�[�����Ƃ����Ƃ���Œ��j���̌��������Ƃł����B���̌�A���̌����ق̍u���Ȃǂɉ��x���Q�����Ă��������ɁA�Ƒ��݂�Ȃɖʔ������`���B�͂��݂ŎQ���������̑��ŁA�ѓc�̓��D�̏O�ɂ��܂��Ă��܂��A�ȗ��y�^���N�������𑗂��Ă��܂��B
�@�t�����X�Ő��܂ꂽ�y�^���N�Ƃ������Z�́A���̗��j���̂��܂�2007�N�ł��傤��100�N���������Ă��炸�A���{�ɓ����Ă����̂͂킸��20�N�قǑO�̂��ƁB�}�C�i�[�X�|�[�c�̈���o���A���Z�l�����Ȃ��̂ł��B���������Z�̖ʔ����͔��ɐ[���ŁA�͂܂肾�����甲���o���Ȃ����͖��_�ł��B
�@����Ȗʔ������Z�ł�����A�n���K�͂ŕ��y���Ă���A���E�I�茠�Ȃǂ�����I�ɊJ�Â���Ă��܂��B���N�̉Ăɂ̓W���j�A���E�I�茠���z�K�s�ŊJ�Â���A���j�����Ə����ő�\����������ƂȂǒn�����ŕ��ꂽ�肵�Ă��܂����̂ŁA���L���ɂ���������������邩������܂���B�n���K�͂̑�������Ă��Ƃ́A�������嗤�K�͂̑�������킯�ł��B�����ł��A�A�W�A���ł��B
�@�A�W�A���ɏo�ꂷ����{��\��I�Ԃɂ������āA����͌l�I�l��J����܂����B�i���܂ł́A�I�l�����J���Ă��̗D���G�L�b�v�i�`�[���̂��Ɓj����\�ɂȂ�����A�ē������ȃ����o�[���W�߂đ�\�ɂ�����A����ނ�̂����ɏ���ɑ�\�Ɩ�����ĎQ�������肵�Ă܂����B�j�����Ă��̑I�l��ɉ䂪�Ƃ�����A���E��E���j�̂R�����G���g���[�����̂ł��B
�@�܂��́A�����n��I�l��ɒ���ł��B���͉�炪�z�[���O���E���h�ѓc�s�㋽�q153���ˉ��e�����i�R�[�g�̂��Ɓj�ł��B��ʂU���݂̂����S���ŏI�I�l��ɏo��ł��Ȃ�������B�ꂳ��ƒ��j�͎c�O�Ȃ���I�O�ɒ����̂́A�Ȃ�ƕ�����͂���ǂ��܈ʂōŏI�I�l��o�ꌠ�l���I�Ƒ��̊��҂������ɂ�����Ƃ̂�������܂��B
�@���{��\�W���̍��𑈂��S���ŏI�I�l��́A�z�K�s�E�z�K�X�^�W�A���ׂ̗̉��ł����Ȃ��܂����B�S���e�n��������������Ҏ҂ǂ����W�܂邱�̑I�l��A�S����Ŋ��炵���l�����������ς����܂��B���������ΊJ�������Ē��킷�閳���̕�������Ђ����Ƃ�Ȃ��匒���B�����ĂȂ�ƂȂ�Ǝ��ʁA��12���P������S���ɂ����āA�^�C�����E�X�p���u���ŊJ�Â����A�W�A���ɓ��{��\�Ƃ��ďo�ꌈ��I
�@�����A�W�A���ł̕����͂����ɁI���͔����H���b�L�������ꂽ�H�^�C�����I�s�ƂƂ��Ɏ���ɑ����I
�@
�@��148�b�w��M�}�c�J���@���P�Q�����E�Q���̏́x
2008.1/25�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O��̑����B
�@���ē��{��\�ɑI�o����A�^�C�����ɍs�����ƂɂȂ����Ƃ͂����A�����ȒP�ɍs���Ă��邱�Ƃ͂ł��܂���B�p�X�|�[�g�̎擾����͂��߂Ȃ���Ȃ�܂���B����10�N���O�Ƀp�X�|�[�g�̊�������A�C�O�ɍs���\��ȂǂȂ�����������͋}���Ŏ葱�������Ȃ���Ȃ�܂���B��\���肩��o���܂łP�������Ȃ��̂ł������}���ł��B�C���^�[�l�b�g�ŕK�v���ނ��m�F���A����ŏ��ނs���Ă��炢�A�������ɂŎ葱�������܂��B�p�X�|�[�g���s�܂Ŗ�10���A�{������́u���������ԍ��������Ȃ��ƍq�����Ȃ��v�Ƃ₢�̂₢�̂̍Ñ��B
�@�Ƃł͉������Ȃ���Ȃ�܂���B�u�^�C�͋C����30�x���邭�炢������A����Ƃ���������āA����͂���Ȃ����A�ł���`�܂ł͊������B����Ȃ̌��n�Ŕ���������ȁB�v�Ƃ��ׂ��Ă��ĂӂƁu�����A�X�[�c�P�[�X�Ȃ������I�v�Ƃɂ����ꂩ��̊C�O�����ɂȂ�̂ł����B
�@�o�������ƕ��s���čL���ɂ����߂܂��B�y�^���N�͂Ȃ�Ƃ����Ă��}�C�i�[�X�|�[�c�B�����̐l�ɂ��̑��݂Ɩʔ������킩���Ăق������A�������������ۑ��ɏo�ꂷ�邱�Ƃ����������ɏ����ł��n��ɐZ���ł���Ƃ����܂��B
�@�M�B����͂��ߒn��e���ɑ�\����̋L�����f�ڂ��Ă��������A�ѓc�s����\�h�K�₵�A������L���ɂ��Ă��������܂����B�i���쒬�ݏZ�̎����ѓc�s����\�h�K�₵���̂́A��������������������Ă���N���u���ѓc�s�����_�ɂ��Ă��邩��j
�@�����č������̌��Ƃ��ă��W�I�o���ɂ��L��������܂����B�������e�l���X�e�[�V��������ɂ����b�ɂȂ�܂����B
�@�ߋ��ɂ͓��X�A�����E�̈�قŔM�ق�U�邢�A�ѓc������٥�ɓߕ�����قōu�߂�����A���ɓߋ����قŐ�������������ł����A���W�I�o���͏��̌��B������ƃh�L�h�L�ŕ����ǂ������܂����B���W�I�ǂ̕��݂͂�ȖZ�������B���������ɋǓ�������낫��댩�Ă��邤���ɁA�ł����킹�����������ɖ{�ԊJ�n�B
�@�n�܂��Ă��܂��܂��ْ����邱�Ƃ��Ȃ��A�y�������b�ł��܂����B�ł��A���t�Ŗ��͂�`����̂͂Ȃ��Ȃ�����B���ƈꎞ�Ԃ��炢����ׂ点�Ă��炦������Ɩ��͂���ꂽ�̂Ɂc�B
�@�����A���悢��o���I�p�X�|�[�g���q���X�[�c�P�[�X���Ԃɍ������B�L���������肾�B���c�W���̂��ߊ��삩�炠�����ŐV�h�ցA���c�G�N�X�v���X�ŋ�`�ցB�ł�����w�ł��łɖ��q�ɂȂ��Ă��܂����I�ʂ����ă^�C�܂ōs��������̂��H�������ɏo��ł���̂��H�s�����c������ɑ����B�@�@
�@
��149�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�R���̏́x
�@2008.2/9�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X��̑����B
�@����w�ȍ~�A�V�h����c�Ɩ����܂���Ȃ�����A��`�łȂ�Ƃ����̃����o�[�����ƍ����B��`�������낤�낵����A�Ō�̓��{�H�𖡂������A�Y�ꕨ���ɑ������肵�Ȃ��炠�킽���������Ԃ��Ԃ��܂����B
�@������o������10���ԁA����Ɣ�s�@�ɓ���ł��B��s���Ԃ͂V���ԁB�������Q�čs�������Ƃ���ł����A���������n�����̌ߌ�10���߂��i�����̓}�C�i�X�Q���ԁA�܂���{���Ԃ̐[��12���߂��j�Ȃ̂Ŕ�s�@�ŐQ�Ă��܂��ƌ������ɂ��ĐQ���Ȃ��Ȃ�A�����ڂ��ɂȂ肻���Ȃ̂Ŋ撣���ċN���Ă����܂��B
�@�����킽�������o�Ă����̂ŐV�����ǂ�ł��Ȃ��Ƌ@���œǂ݂܂��B���Q�����{��ǂ�A�p�Y������������B�@���H�ł͑������^�C�Ɏv�����͂��A�^�C�r�[��������A�^�C�J���[��H�ׂ��肵�܂��B�i�C�g�t���C�g�Ȃ̂Ōi�F�͊y���߂܂��A���ƂĂ������������܂����B�܂����n��ʂ�ƁA�X�̓��肪���炿��ƂȂ�Ƃ����z�I�ł��B���C�o�܂��ƃG�R�m�~�[�nj�Q�\�h�̑̑����Q��قǂ����Ȃ��A�Q��ڂ��I��鍠�����ƂȂ�܂����B
�@��Ƃ������Ƃ�����w�����I�x�Ƃ����قǂł͂���܂��A�z�e���܂ł̑��}�o�X�͗�[���K���K���������܂��B�ނ��늦���o�X�ɂQ���ԗh���A����Ƒ����̃X�p���u���ɓ����B�h����̃N�t�@���X�p���z�e���̃x�b�h�ɓ��邱�Ƃ��ł����̂́A���t�̕ς�����ߑO�Q���߂��̂��Ƃł����B
�@�����X�����܂����N�t�@���X�p���z�e���Ƃ����h�ɂ́A���n�ł͍������]�[�g�z�e���Ȃ̂ł����A�����͂����݂����Ȓl�i�B�������z�e���Ȃ̂ŁA�����̑I�肽�������܂��Ă��܂��B������������z�e�����O��T�����A���Ȃ�傫�Ȃ��Ƃ��m�F�B�ߏ��ɃR���r�j������A�؍ݒ������Ԃ��b�ɂȂ�܂����B
�@�����͊J��p�[�e�B�[�Ƒg�ݍ��킹���I�����A����܂ł͗��K�����܂��B�z�e�����玎�����܂ŎԂ�10���قǁB�^�N�V�[�ňړ����܂������ꂪ�悭�e���r�Ō���悤�ȃg���b�N�ɍ��Ȃ������悤�ȏ�蕨�B�����ɐ�����Ȃ��玞��100km�ȏ�łԂ�����܂��B
�@���ɒ������瑁�����K�ł��B�Ȃ�Ƃ����Ă�����͓��{��\�Ƃ��ăy�^���N�̎����ɗ����̂ł�����A�����͎���킯�ɂ͂����܂���B�e�����̏�Ԃ�c�����A�����̒��q��`�[�����C�g�ƍ����m�F���Ă����܂��B�y�^���N�̓����^���ʂ������p���d�v�ȃX�|�[�c�ł��B��������̖{�Ԃɔ����ėJ���͂Ȃ����Ă����������̂ł��B�T���Ԃقǂ݂����蓊������ł��̓��̗��K�͏I�����܂����B
�@�[������͊J��p�[�e�B�[�Ƒg�ݍ��킹���I��B�ΐ푊������܂�A�����ւ̓��u���݂Ȃ��点�Ȃ�����p�[�e�B�[�ł͑傢�Ƀn�W�P�܂��B
�@�����A���悢�斾���͎����I�C����������ɑ����B
�@�@
��150�b�w��M�}�c�J���@���P�Q�����E�S���̏́x
2008.2/26�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X��̑����B
�@���悢����n�܂�܂��B�J��͌ߑO�W������B�ꎞ�Ԉȏ�O�ɉ��ɓ�����K�Ȃǂ����܂��B
�@�������͋C��35�x�ɒB����^�C�����̉��V�̉��A���A���Ȃ������~���̉��O�ł�����A�Ȃ�ɂ����Ȃ��Ă������炾��B�̒��̈ێ����d�v�ɂȂ�܂��B
�@�y�^���N�Ƃ����ƂȂ�ƂȂ��w�j���[�X�|�[�c��V�l�����y�X�|�[�c�x�Ǝv��ꂪ���ł����A���E�I�Ɍ���Ǝ�҂��K���Ɏ��g�ރQ�[���ł��B�^���ʂ͌������Ȃ����߁A�m���ɍ���҂܂Ŋy���߂܂����A�{�i�I�Ȏ����ɂ͋Z�p��̗ͥ���_�͂������Ă��Ȃ��Ǝ��g�߂܂���B�ꎎ���ꎞ�Ԃقǂł�����A����l�������키�ƃt���t���ɂȂ邭�炢�ł��B
�@�J��͎��ɉ₩�B�^�C�炵���A�ԉ┚�|������ł����Ɩ苿���A�A�W�A�e������̑I����}���܂��B�I��̂ق��̓����b�N�X�B�J��s�������ڂɏ���ɋL�O�B�e������A������ׂ肵����܂��Ƃɂ����炩�B���{�̋���W�̐l�Ȃ�ؗ��Ăē{��܂���悤�ȃZ�����j�[�ł����B
�@�J���͂܂��V���[�e�B���O�R���e�X�g�������Ȃ��܂��B�V���[�e�B���O�Ƃ́A�y�^���N�̓����Z�p�̈�ŁA����̋��Ɏ����ڂԂ��Ēe��������ƁB�ŁA���̋Z�p�����������̂��V���[�e�B���O�R���e�X�g�ł��i�v���싅�I�[���X�^�[�Q�[���̃z�[�������������C���[�W���Ă��炤�Ƃ������j�B�e�`�[������w�e�B�[���[�x�Ƃ����e��������̑I���l���o�ꂵ���_�������܂��B���́w�~�����[�x�Ƃ����e��������A�w�|�����e�x�Ƃ�����W������Ƃ������ł����Ȃ̂ŃV���[�e�B���O�R���e�X�g�͉����ł����B
�@�V���[�e�B���O�R���e�X�g���I��莎���J�n�\���11���B���������ۂɂ͌ߌ�P���ɂȂ��Ă��܂��n�܂�܂���B�y�^���N�͓�t�����X���˂̃X�|�[�c�B�앧�̔��ɂ����炩�ȁi���������ȁj���i���A���̂܂������܂�Ă���̂ŁA���^�c�����ɂ��������B���E�I�茠�����Ď��Ԓʂ�ɐi�s���邱�Ƃ͂���܂���B���̓����\�I�O���������������Ȃ̂ɏI�������͌ߌ�X�����B���Ȃ݂ɂX���I���Ȃ�A�\��ɋ߂��ق��B���t���܂����ł����Ȃ��邱�Ƃ�����ł��B
�@�ߌ�P��30���A����Ǝ������̎������n�܂�܂����B���̃G�L�b�v�͑��̂l�����e�B�[���[�A�����~�����[�A���̂x���Ɣѓc�̂j�����|�����e�Ƃ����\���B�O�l��g�̎����Ȃ̂Ő헪��x���Ƃj�������ŏo�ꂵ�܂��B
�@�\�I��ꎎ���̓J���{�W�A��B�J���{�W�A�͐�قǂ̃V���[�e�B���O�łR�ʂɂȂ����e�B�[���[�̂��鋭�����B�ʂ����Ď����ɂȂ�̂��H�y�����������̂��H�h�L�h�L������ɑ����B
�@
��151�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�T���̏́x
2008.3/9�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X�X��̑����B
�@�\�I����͗D�����̈�p�J���{�W�A�B���{���牓�H�͂���荞��ŁA����Ǝ����J�n�ł��B
�@�������ɃA�W�A���A�Ƃ����ٔ��������͋C�͂���܂���B�������Ƌ��Z�������₩�ȕ��͋C�Ŏ����͂����Ȃ��܂��B���������ꂼ��ɍ����\���ĎQ�����Ă���̂ł�����A�W�������^���������J��L�����܂��B�������̎������͐k���܂����B
�@��ꃁ�[�k�i�Z�b�g�Ɠ��`�j�͂��݂��|�����e�i�j�e�B�[���i�e������j�����߂�����11���𓊂��I���A���肪�Q�_�̏B�c��͎��̈ꋅ�̂݁B�ْ������W�����|�����e�B�����Ƀr���b�g�i�ڕW���j�Ƀs�^���Ɗ����{�G�L�b�v�搧�I�u���I���E�ɏo�Ă����������킦�邼�B�䓙�̃��x�����n���ɂ�������Ȃ��I�v�Ǝv�����̂͂����܂ŁB����̃e�B�[���̐��x��������A�J���[�Ƃ����A�G�̋���e����������������̋������̏�Ƀs�^�b�Ǝc��Ƃ����ŏ㋉�̓�����A������A���邸��Ǝ��_�B�I����Ă݂�P�\13�́w�X�~�C�`�x�̊��s�ł����B
�@�y�^���N�͂R�l��g�A�e���Q���i�e�G�L�b�v�U���j���v12���̓����łЂƃ��[�k���I���ł��B���[�k���J��Ԃ��Ȃ��烁�[�k���Ƃɓ��_���v�Z���A���v13�_�ɐ�ɒB�����G�L�b�v�̏����ɂȂ�܂��B�i�Љ�̈�Ȃǂł͎��Ԑ����ł����Ȃ��邱�Ƃ�����܂����A����ł͖��͔����ł��B�_�����������ꂽ�肾���łȂ��A�傫����邽�߂̔��ł�A����������邽�߂̋]�łȂǂ̍��̖�������̂ł��B�t���R�[�X�����Ԑ����ŐH�ׂ�悤�Ȗ��C�Ȃ��͂��Ђ�߂Ăق������̂ł��B�j�Ђƃ��[�k�ł̍ō��_�͂U�_�ł�����A�R�_�Ƃ����Α�ʓ����_�ł��B�Ȃ̂ɉ�X�͂S�_�T�_�Ƃ������_�����A�قږ���R��ԂłЂ˂��Ă��܂����Ƃ������Ƃł��B
�@�������ɂ���ł͂܂����ƍ�����蒼���A�����o�[������ւ��ĐS�@��]�\�I����ɗՂ݂܂����B
�@�\�I����̑���̓}���[�V�A�B�}���[�V�A�͕��ϔN�20�قǂ̔��ɎႢ�G�L�b�v�B�i�����A�قƂ�ǂ̃G�L�b�v�����ϔN��20��ł����B�����ŔN���Ƃ����悤�ȘV��G�L�b�v�̂ق����������B���{�̂����ЂƃG�L�b�v��10����܂ޕ��ϔN��30�قǂł�����A�����ɉ䂪�G�L�b�v�������������������z���ɓ�Ȃ��Ƃ���ł��傤�B�j�Ⴓ�ɂ�����ōU�߂����Ƃ���ł����A���Z���͌������̂ق��������B�h�V���_�ŔN���ɏ����������Ă����Ƃ͎v���܂���B�C���ƍ��������ē��邵������܂���B
�@�䂪�G�L�b�v�ɏ��@�͂���̂��H����Ƃ��Q��ł��܂��̂��H�n���n��������ɑ����B
�@�@
��152�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�U���̏́x
2008.3/19�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X�X�X��̑����B
�@�\�I����͔��ɎႢ�}���[�V�A�B����ɕ����Ă����X�͂���������킯�ɂ͂����܂���B
�@�Ƃ͂������̂̎��͍��͂�����Ƃ����������B�����Ƃ����ԂɂP�\�T�Ɨ�����Ă��܂��܂����B�����������ʼn�X�Ƀy�^���N�̐_���~��Ă��܂����B�|�����e�ƃJ���[���A���Ō��܂�A�P���[�k�łȂ�ƂU�_�I�ő�t�]�B���̂܂܈�C�ɁA�Ǝv���܂������y�^���N�̐_�͑��X�ɋ����Ă��܂��܂����B
�@���̂P���[�k�ł��ׂĂ��o�����Ă��܂�����X�͔����k�̂悤�ɂȂ�A���̌�̓Y���Y���Ǝ��_���d�ˁA�V�\13�Ŕs��Ă��܂��܂����B
�@����ŗ\�I�e�u���b�N��ʂQ�`�[�����i�o�ł��錈���g�[�i�����g�̓����₽��Ă��܂��܂����B���A����ŃA�W�A���ׂĂ��I����Ă��܂����킯�ł͂���܂���B�\�I�������P�����c���Ă��܂����A�����g�[�i�����g�ɐi�߂Ȃ������`�[�����m�Ő키�l�C�V�����Y�J�b�v�Ƃ��������c���Ă��܂��B
�@���āA����̃A�W�A���ɂ́A�^�C������J���{�W�A��}���[�V�A��x�g�i������I�X��V���K�|�[�����p�������I�[�X�g�����A�A�����ē��{��10�������Q�����܂����B�e���Q�G�L�b�v�A��������I�X��I�[�X�g�����A�͂P�G�L�b�v�A���v�P�V�G�L�b�v�ł����Ȃ��܂����B�\�I�͂S�g�ɕ�����A��ʂQ�G�L�b�v�������g�[�i�����g�ցB�����g�[�i�����g�Ɏc��Ȃ������G�L�b�v�ƁA�����g�[�i�����g����s�ރG�L�b�v�ɂ���āA�l�C�V�����Y�J�b�v�������Ȃ��܂��B���̃l�C�V�����Y�J�b�v�������g�[�i�����g�ɗ�炸���x���̍����������W�J����܂��B��X�ɂƂ��Ă͗\�I���낤���A�l�C�V�����Y�J�b�v���낤���A����C�������Ȃ������������ɂȂ�܂��B����A�͂����茾���ƈꏟ�ł���Α�����ɒl����قǂȂ̂ł��B
�@�Ȃ�Ƃ��ꏟ���I�ƁA�܂�������蒼���A�����o�[������ւ��ė\�I�O���ɗՂ݂܂����B
�@�\�I�O���̑���͑�p�i���E�I�ɂ͑�k�A�������̓`���C�j�[�Y�^�C�y�C�Ƃ���Ȃ��ƒʂ��܂���j�B�����������ɖ��邢�G�L�b�v�ŁA�����c���Ƃ��Ă��ɂ��₩�B�Á`���`�}�`�}�ƁA��ꕨ�ɐG��悤�Ȃ������y�^���N��������{�����̑��ł͌����Ȃ������炩���Ŏ����͐i�݂܂��B
�@���̂����炩���ɂ̂܂ꂽ���A�䂪�G�L�b�v�͌����ނȂ����T�\13�Ŋ��s���܂����B�������P���[�k���Ƃ̐킢�͐ڐ�Ɏ������߁A��X�Ƃ��Ă͂�����x�育�����̂��鎎���ɂȂ�܂����B
�@�������̎育�����͖{���������̂��H�����̃l�C�V�����Y�J�b�v�Ŕߊ�̏����͂��߂�̂��H�����ƂƂ��Ɍ��ꂽ��̑�Q�ɏP���Ȃ��玟��ɑ����B
�@�@
��153�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�V���̏́x
2008.4/12�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X�X�X�X��̑����B
�@�A�W�A�����ŏI���B�\�I�˔j�ł��Ȃ�������X�́A�l�C�V�����Y�J�b�v�ɉ��܂��B���Z�J�n�͌ߑO�W��30���Ȃ̂ł����A�g�[�i�����g����s�폟�̂��߂��炭�͎��Ԃ����Ă��܂��܂��B
�@���K�ɂ����������O���Ă����̂ŁA���߂ɒ��H��H�ׂĉp�C��{���܂��B
�@���̐H���ł����A���ٓ����o��킯�ł͂���܂���B���X�g����������킯�ł�����܂���B�������̈�p�ɓ��݂̉��䑺������A�����ōD���Ȃ��̂����炢�i����������ł�����I��h�c�����Ζ����ł��炦�܂��j�A�x���`�ɍ����ĐH�ׂ�̂ł��B���s�ԑg�ɏЉ�ꂻ���ȓT�^�I�ȉ���ł�����A���{�ꥐ��^�����̃^�C�����ł��B���ɂ͂ǂ̗����������������H�y�������H���Ă��܂������A�h���̂����Ȑl��A�������ǂ����Ă������Ȑl�͂炻���ł����B�����͌����Ă����ɐH�ׂ���̂͂Ȃ����A�l��������Ƃ���Ȃ�Ɋ���ĐH�ׂ���悤�ɂȂ�݂����ł��B���Ȃ������v�ŁA�������璼�ڃS�N�S�N����ł܂����B�B��H�ׂ��Ȃ������̂́A���ɓ����O����h���������錃�h�t�J�u�߂����ł����B
�@�����������炦���ł����Ƃ���Ńl�C�V�����Y�J�b�v�ł��B�����̂������炩�ΐ푊��́A�O������������̃`���C�j�[�Y�^�C�y�C�G�L�b�v�B��������ɕ�����킯�ɂ͂����܂���B�C�������܂����Ď����ɗՂ݂܂��B
�@���̎����͓��������ɜ߂��ꂽ�悤�ɐ�D���̎����e�B�[���[�ɂȂ�K���������܂��B�O���ɂȂ�ƂȂ��育�����������Ă����䂪�G�L�b�v�́A�K���ł��炢���Ă����܂��B�u�Ȃ�Ƃ��ꏟ���I�v�̔M���v���ŐϋɓI�Ɏd�|���Ă����܂��B�����M���v���ɉ����悤�ƁA�̂�ɂ̂��Đ�D�����ێ����܂��B�����A�����̂��Ă��ꂽ�͖̂��������ł͂���܂���ł����B�O���̑ΐ퓯�l�A�`���C�j�[�Y�^�C�y�C�̓G�L�b�v�������c���Ƃ��Ă����邭�ɂ��₩�B���̕��͋C�������̂��Ă���܂��B���̂�����ɋC�Â����̂����{�����c�����邭�ɂ��₩�ɉ������Ă���܂��B��������z�C�ȃp�t�H�[�}���X�ʼn����܂��B����Ȃ���ȂŁA�������͈ȏ�̗͂����A���������v���[���o�邽�тɁA�G�����������тƂ���������ł͂��肦�Ȃ��悤�Ȑ���オ��B���t�͈Ⴆ�ǂ������X�|�[�c����������̂��J�Ɋ����������͐i��ł����܂��B
�@���������ʂ͔��A�U�\13�Ŕs��Ă��܂��܂����B����ʼn�X�̃A�W�A���͏I���B�Ǝv���Ƒ�ԈႢ�I�y�^���N���̖ʔ����Ƃ���A��������������������ς�����܂��B
�@�����H�ǂ��������ƁH���܂ł��́H�Ɠ���c������ɑ����B
�@
��154�b�w��M�}�c�J���@���P�Q�����E�W���̏́x
2008.4/27�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X�X�X�X�X��̑����B
�@�A�W�A���̗\�I��˔j�ł����A�l�C�V�����Y�J�b�v�ɂ��s��A��X�̌�����͏I����Ă��܂��܂����B�������A���܂ŏ����Ă����悤�Ƀy�^���N�̑��Ƃ����͔̂��ɂ����炩�ŁA���Ԃ��̂�т�ƊJ�Â���܂��B�����Ŏ��R�Ƌ��Ԃ������ł��邱�ƂƂȂ�A���̊Ԃɖ�ǎ����������ς��s���܂��B�����\���Ō����Ǝ����O�̒����Ƃ������Ƃł��傤���A���ۂ̎����Ƃ͂���܂肩�����͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��}�}����܂��B
�@�y�^���N�ɂ̓V���O����_�u���X��g���v���ƎO��ނ̎����`��������A���̂Ƃ��W�܂����l���Ŏ����`����ς��邱�Ƃ��ł��܂��B����̃A�W�A��������̓g���v���ł����A��ǎ����ɂ���Ȑ���͂���܂���B�ɂ����ɂ��Ă���I����������琺�������A��l�Ȃ�V���O���ŁA��l�Ȃ�_�u���X�ŁA�O�l�Ȃ�g���v���Ŏ��������܂��B�����Ă��̐��_�͐��E���ʂ̂��̂ł�����A���肩����ǂ�ǂ�U���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@����ȏł����玄���A���I�X�E�����E�I�[�X�g�����A�̕������Ǝ����������Ă��������܂����B�����Ă����ł͂���Ȃ�ɏ����������A�w�^�C�����������ςȂ��I�s�x�͖Ƃꂽ�̂ł����B
�@�����{��̂ق��͉�X�̊֗^���Ȃ����Ői�݁A�^�C�^�C�̒j�q�������A�^�C�x�g�i���̏��q�������A�]�Ƌ����Ŋϐ킵�A�u����͂������ɗ����Ă݂���v�ƌ��ӂ��V���ɕ\�������ڂɏĂ��t���Ă��܂����B
�@�������I���������̌�A����ɐ���ȃt�@�C�i���p�[�e�B�[���҂��Ă��܂��B���{�`�[���͓`���I�ɂ��������p�[�e�B�[�ňÂ������悤�ł����A����̃`�[���̓n�W�P�܂���w�W���|���k�[�{�[�x��傢�Ɍ��`���Ă܂���܂����B
�@�t�@�C�i���p�[�e�B�[�͊��S�Ȃ�w�m�[�T�C�h�x�ł��B�S���O�܂ł͊���m��Ȃ������A�W�A�e���̑I�肽���A�����ԑO�܂ŕK���Ő���Ă�������Ƙa�C�\�X�A�C�A�C���炢�ɒ��ǂ��y���݂܂��B�Ȃ��ɂ̓p�[�e�B�[�p�Ƀh���X�A�b�v���ċC�������ĎQ������I�肪�����肵�Ď����Ƃ͈Ⴄ�₩��������܂��B
�@�p�[�e�B�[���́A�����������������Ȃ�Ă������Ȃ��Ƃ͂��܂���B���⎎����Z�p�k�`������悤�Ȑl����l�����܂���B�S���̋��m�̊ԕ����v���Ԃ�ɏo������悤�Șa�₩���Ɛ���オ��ł��B�̂�����x������L�O�i�̌�����������B�A�h���X�����������āA�𗬂𑱂��Ă������Ƃ���l�������������܂����B����ȑf�G�Ȓ��ԂƐ��E���łȂ����Ă���y�^���N���A�܂����������D���ɂȂ銴���̃p�[�e�B�[�ł����B
�@���`�y���������B���Ƃ͋A�邾���A�����������A�ꂽ�̂��H����ɑ����B
�@
�@
��155�b�w��M�}�c�J���@��12�����E�X���̏́x
2008.5/13�f��
�@�y�^���N�^�C�I�s�͑O�X�X�X�X�X�X�X��̑����B
�@�A�W�A���̍s��ꂽ�X�p���u���Ƃ����X�́A�o���R�N����A���^���Ɍ���������������ɉ������Ƃ���ɂ���X�ł��B�A���̔�s�@����ւ��������ߎ��Ԃɗ]�T�̂������������́A�A���^����Ղ̌����ɌJ��o�����Ƃɂ��܂����B
�@�A���^���܂ōs�����͂����ł����A�܂������̍s�������������ό��Ȃ̂ŗ\���m��������܂���B�ǂ������ǂ��낾���킩��Ȃ��̂łƂ肠�����E���E�����܂��B��������ł�������傫�Ȍ������͂ЂƂƂ��茩�܂������A�����Ƃ����Ƃ���������ς�����܂����B�A����K�C�h�u�b�N�Ō�����w�����ɕ����ꂽ��������Ԃ̌��ǂ���x�Ə����Ă���܂������A�������Ă��܂����B�ł��t�ɁA�ւ�Ȏs��̂܂��Ȃ��ǂ���A��H�̍�Ə�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł��܂����B�����ĊO���l�i�^�C�l�ȊO�j�̊ό��q���܂��������Ȃ��悤�ȉ���ŁA���낢��H�ׂ�����肵���̂ł����B
�@����Ɏ��Ԃ����������߁A�o���R�N�Ŕ����������邱�Ƃɂ��܂����B������܂������̍s�������������ł��B���Ƃ��o�U�[���Ƃ������y�Y�����X�֍s���A�w�f�B�X�J�E���g�I�x�w���A���A�I�x�ƘA�Ă��Ȃ��甃���������Ă��܂����B
�@�X�p���u���ɔ�ׂ�ƃo���R�N�͂�͂蕨���������A25�~�������~�l�����E�H�[�^�[��35�~�ɁB50�~�������L�[�z���_�[��150�~�ɂȂ��Ă܂����i�ł��w�f�B�X�J�E���g�I�x�w���A���A�I�x�œ������炢�̒l�i�ɂȂ�܂��j�B���͓��ʔ������̗\�������܂���B�Ƒ��ɂs�V���c�ƃL�[�z���_�[�����炢�B�̂�т菤�X�X���E���E�����Ȃ���A���̑I�肽���̔��������������`������i�f�B�X�J�E���g�I���A���A�I�W�j���Ă������܂����B
�@������ۓI�������y�^���N�^�C�I�s�����悢��I���ł��B�A���ւ�22��35�����̃^�C�q��B���c�����͗����A�U��15���̗\��B���x�͂�������Q�Ă��邵������܂���B��������ɏo���ꂽ�@���H���������ƕ��炰�A���c�̃^�C�r�[������t����ł��x�݂Ȃ����B
�@�Q�ڂ���Ő��c�����A�W�����p�[�𒅍��݂܂����������������܂��B�ו����������A����Ƃ��ɐ���Ă��������o�[�Ɖ��U�ł��B���c�ɂ����悤�ȋC�����܂����A����\�I��̋��G�ɂ��Ȃ郁���o�[�ł��B�����ɕ��̒T�荇�������Ȃ���̉�c���ƂȂ�܂����B
�@�A�H�͐V�h���獂���o�X�ň�C�ɏ���ցB�{���Ƀ^�C�I�s���I����Ă��܂��܂����B�����������ł̂�т肵�Ă���ɂ͂���܂���B�^�C�œ������𑽂̂��̒��Ԃ����ɐ������`���Ȃ���Ȃ�܂���B�����ĂȂɂ��A�܂����ɏo����悤�Ɋ撣��Ȃ���Ȃ�܂���B���b�V���[�I
�@
��156�b�w���̓a���x
2008.5/29�f��
�@���E���̐l�C���c�Ƃ����H�^�J���d�J�I�s���|�`���B�������n���ł���ȏ�̐l�C���ւ�̂��A�悵���ƐV�쌀�B�Ƃ����킯�ł��̏t�A�A�Ȃ����˂܂��ĂȂ�O�����h�Ԍ��ɍs���Ă��܂����B
�@�����Ȃ�O�����h�Ԍ��ɍs���͎̂��͂Q��ځB���N�O�̉āA�����Ɏq���B��a���A�ꂳ��ƃf�[�g�����Ƃ��Ɂu�t�r�i�H�v�u�����œ���Ȃ��v�A�u�_�ˎU��H�v�u�������ă_�E���v�A�u�����Ŋy���߂�Ƃ���H�v�u�Ȃ�O�����h�Ԍ��I�v�Ƃ������ƂŎv�������ďo�����A�����ȂŌ������Ƃ�����܂����B
�@���̏��Ɋ���Ă��镃����ł������悵���Ƃ͏��̌��B�e���r�Ƃ͂���Ⴄ�Տꊴ�ɑ唚�ł�������A�ꂳ��ɂ������Ă͕����悶���ċꂵ�����Ă��܂����B�������������낢�̌������Ўq�������ɂ������Ă�肽���Ƃ������Ƃō���Ƒ�������Ă����ƍ��Ȃ��Ƃ��Ă̊ӏ܂ɂȂ�܂����B
�@�܂��͐V�쌀����n�܂�܂�(�ʏ�͂܂����ˁE����E��p������A���̌�V�쌀�Ȃ̂ł����A���̓��͏t�x�ݓ��ʂS������Ƃ������Ƃŏ��Ԃ�����ւ���Ă��܂���)�B���Ȃ��݂̏�����씨�A��̉�▢�m�₷���̌J��o���M���O�ɑ���I�I�N���Ȃ����Ă邾���ŏ��Ă��܂��B�����͗������̂Ȃ����j���A�H������悤�ɐg�����o���唚���J��Ԃ��Ă��܂��B�����čŌ�ɂق��Ƃ�����▭�̉��Z�ɁA�ꎞ�Ԃ������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă����܂����B
�@�㔼�̖��˂ł́A�v�����O�E�₷��Ƃ����E�j����}�E�J�E�X�{�^���E����ƁE�璹�Ȃǂ��o��B������͘b�p�ȍI�݂ȃJ�E�X�{�^�������肪������ł����A�q���B�͐璹�ő唚�B�ꂳ��͂v�����O�ɂ����Ă��܂����B�㔼�������Ƃ����ԂɈꎞ�Ԕ����߂��A�܂𗬂��Ȃ���Ȃ�O�����h�Ԍ������Ƃɂ��邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�����A���������H��������̊X�ɗ�����₩��Ȃ�����������ł��H�ׂ�A�Ƃ������ƂɂȂ蓹�ږx�ɌJ��o���܂��i�Ȃ�O�����h�Ԍ��Ɠ��ږx�̓A�[�P�[�h�����A�����ĂT���j�B����ɓ��ږx�ɗ�����ł�����A�b��́w����������l�`�x�Ƃ������J�j�̊ŔƂ��A�D���_�C�u�ł��Ȃ��ݓ��ږx���Ƃ��A�O���R�̑�Ŕ����Ȃ���Ȃ�܂���i�����S�����Ă������ĂT���B�ʐ^�B�e�̑҂����Ԃ̂ق����������炢�ł��j�B
�@�������ЂƂƂ���I���A�L�O�B�e���ς܂��A����͑�㖼���������ŐH��������B�������A���ږx���E���E�����Ȃ��炽���Ă��E���ΏĂ��E�悵���Ɛl�`�Ă������ς��H�ׂĂ������߂Ȃ��Ȃ��H���i�݂܂���B�ʂ̈Ӗ��ŐH��������Ă��܂��������́u���̉��[������ׂ��v�ƃ��x���W�𐾂��ċA��܂����B
�@�@
��157�b�w�u�b�u�[�x
2008.6/14�f��
�@�q���̍��Ƀ}�j�A�b�N�ɂȂ�A��ނ▼�O�������قNjL�����Ă�����̂Ƃ����ƁA�d�ԁE�ԁE���b�̎O���Ԃ���������ł��傤�B
�@�䂪�Ƃ̎q�������͍��܂œ��ɂǂ�ɂ��͂܂邱�ƂȂ��i�����Q�[���L�����N�^�[�ɋ������������悤�ł����A�}�j�A�b�N�Ƃ����قǂł͂���܂���ł����j���a�ȓ��X�������Ă����̂ł����A�ܔN���̎��j�������ɂ��Ă������Ԃɋ����������n�߂܂����B�������s�n�x�n�s�`�Ԍ���ŁB
�@�����w�����������̂��ƒ�Ȃ�A���̕ӂ�܂œǂ�Ŏ����ԃ}�j�A�b�N�̌����������邩�Ǝv���܂��B�����͔шɒn���ł͍P��́w���C�n���ւ̎Љ�w�x�ɂ���܂��B
�@���C�n���ւ̎Љ�w�͔шɂ̑����̏��w�Z�ŌܔN�����Ɏ��{�����s���ŁA�C�Ȃ����̎q�������ɊC��̌������邱�ƁA���N�̏C�w���s�̍s���P���E�h���P���i�ŋ߂͔����Ƃ��Ȃ�Ȃ����{�Z�������Ă��܂������j�A����ɂ͒n��̎Y�ƂƂ��ċߗׂ̈��m���̎����ԎY�Ƃ����w���Ă���A�Ƃ����ړI������܂��B�w�K�Ƃ��čs���킯�ł�����A���O�w�K����������Ƃ����Ȃ��A���O�w�K�̖ڋʂ��s�n�x�n�s�`�����ԂȂ̂ł��B
�@�s�n�x�n�s�`������̃A�v���[�`���ϋɓI�ł��B���O�w�K�̂��߂̎�������q�悵�Ă��ꂽ��A�z�[���y�[�W�������ɗ������₷�����̂�p�ӂ��Ă���Ă��܂��B���w�ꏊ�ɂ��Ă��A�����ԍH�ꂾ���łȂ��A�@�B���̗��j�⎩���ԎY�Ƃ̑S�̑�����������ƌ����Ă����H�v���Ȃ���Ă��܂��B����ŁA���R�Ǝq�������̋����S���s�n�x�n�s�`�ԂɌ������Ă����킯�ł��B
�@�s�n�x�n�s�`������炤�����̒��ɂ́A�Ԗ��ꗗ�i�S�Ԏ킪�ԗ�����Ă���킯�ł͂���܂��j�ɂȂ����g�����v�J�[�h�����Ă���A���j�͂����M�S�Ɍ��Ċo���Ă��܂����悤�ł��B�o���Ă��܂��Ǝ��͎��ۂɌ��Ă݂����Ȃ���̂ł��B
�@�O�o���鎞�ɂ̓g�����v�������Ă����A���ԏ�œ��H��Ŏ��X�ɂs�n�x�n�s�`�Ԃ������A�Ԗ���Ԗ��̗R���Ȃǂ�������Ă���܂��B���܂Ƀg�����v�ɍڂ��Ă��Ȃ��Ԃ��������肷��ƁA�q�ׂɃ`�F�b�N�����Ă��܂��B
�@���āA���j�͎Ԏ�`�F�b�N��i�߂Ă����ɏ]���đ傫�ȋ^�₪�킢�Ă����悤�ł��B����͍����̔��䐔�̖�50�����߂�͂��̂s�n�x�n�s�`�Ȃ̂ɁA���j�ɂ��Ƃs�n�x�n�s�`�Ԃ͂���Ȃɑ����ĂȂ��Ƃ����̂ł��B�ނ��덑���̔��䐔�̊�������18�������Ȃ����Y�����Ԃ̂ق��������Ƃ����̂ł��B���[��Ȃ��ł��傤�H���쌧�ɂ͌y�����Ԃ��������炩�Ȃ��H�ł����Y�̌y�͂���ȑ����Ȃ����Ȃ��B�̔��X�������̂��Ȃ��H
�@�H�H�H���ɂ͕�����܂��`��B�搶���Ѝ���̊w�K�ʼn������Ă���Ă��������B
�@�@
��158�b�w�Ђ�������x
2008.6/28�f��
�@���j���A���C���ʎЉ�w�ɍs�����b�͑O�����܂������A���̒��Ŏ��j���̌��̒�����肪�s���܂����B
�@�C�ɁA�R�ɁA��Ɋl�������߂Ċ��ŏo�����Ă����䂪�ƂȂ̂ɁA�ǂ������킯�����܂Œ������ɂ͍s�������Ƃ�����܂���ł����B�w���x�Ƃ͌������̂̂��܂�A�N�e�B�u�łȂ��A���N���N�������Ȃ����Ƃ����ЂƂ����̂킢�Ă��Ȃ��Ƃ���ł��傤���B����ɂ͂قƂ�ǂ̊����ł́A�������Ɂw�A�T���T���x���s���A�O���Y�̊L����ł���Ƃ������킳�̂������B�����ĉ����X�Ŕ������ق����f�R�����Ƃ������Ƃ��傫�ȗv���ł��傤�B
�@���݁A�������̑���́A��l1200�~���x�i���w���ȉ����z�j�ŁA�̂��Ă����ʂ͂R�`�T�s�قǁB�L�̂������A��ɂ͂���ɒlj����������Ƃ��������悤�ł��B�䂪�Ƃ��Ƒ��S�l�ŏo�������Ƃ���ƁA4200�~�ŃA�T��20�s�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���A����͂������c�B�A�T����4200�~�̏o��Ƃ����͔̂��ɑ傫���B��邨���i������ɍs���āA�L�H�ו���ł����̂��炢�Ŏ��܂�ł��傤�B����ɃA�T��20�s�Ƃ����̂��ƂĂ��Ȃ��ʂł��B������H��ɂ�����A�T���̎�������500�����x�ł�����A��J��������������H�ׂĂ��܂��Ȃ��Ȃ�Ȃ��I�������č̂��������Ȃ����Ǝv���邩������܂��䂪�Ƃł͂���͖����B����Ȃ���Ȃł����ƒ������ɍs�����Ǝv��Ȃ������̂ł��傤�B
�@�b�����j�̒������ɖ߂��܂��傤�B�O���ɂ́u�ڂ������̂�Ȃ�������ǂ����悤�v�Ƃ��u�g�ɗ����ꂽ��A���Ă����Ȃ��v�Ƃ��ςȐS�z���肵�Ă��܂������A�Ă�����Y�ނ��Ղ��B�Ƃ��Ă��y���������悤�œK�ʁi600�����x�j�̃A�T�������y�Y�Ɏ����ċA���Ă��Ă���܂����B
�@���j�������������Ă����͓̂�m���r�[�`�����h�̂��̊����ŁA�i���j�ɂ͓����ł����j�����̃A�T���͔��ɏ������B�S���闷�s�Ǝ҂ɕ����ƁA�u�������͍̂�ɂ������Đ������Ȃ��A�`����������ł���v�Ƌ����Ă���܂����B�i���Ȃ݂ɁA�������̏ꏊ�Œ����������Ă����ߗׂ̊w�Z�̊l���́A�ہX�Ƒ傫���ʂ��P�s�ȏ゠��܂����B�j�����A���j�̊w�Z�����āA���Ԃ�s���̓s���ł����ɂȂ��������ŁA�������������͂���܂���B���j���y�������ɋA���Ă����̂��Ȃɂ��ł�����B
�@���������̂��Ă����̂ł�����H�ׂ܂��傤�B�����������Ŗ�蔭���I���j���u�A�T�����킢������A�H�ׂ��Ɏ����v�ƌ����o�����̂ł��B����͖������Ɛ������A�Ȃ�Ƃ���ɓ����Ă��������A�����Č��ɓ����Ă��������B���܂��I
�@���������̘b�A�L�ނ͑傫�����̂�菬���������f�R���܂��̂ł��B
�@�@
��159�b�w�������蔪���x
2008.7/26�f��
�@�������蔪���ŕ�����n���Ă���������ɂƂ��āA�^�C�g���̌��t�͈��̖J�ߌ��t���B�������X�Ƃ����Ζ��X�J�c�Ȃǂł悭�����b�ɂȂ��Ă��܂��B����͂��Ă����A�䂪�Ƃ̃t�@�[�u�����Ǝ��j�ƈꏏ�ɕʂ̔����A�w�n�b�`���E�g���{�x�����ɍs���Ă��܂����B
�@���āA���̃n�b�`���E�g���{�A���{�ɐ�������200��قǂ̃g���{�̒��ň�ԏ������g���{�ŁA�̒���Q�p�i��~�ʂƓ����傫���j�I�������肪�悭�A���ꂢ�Ȑ������荞�ސ��Z���`�̐[���̎��n�̂悤�ȏꏊ�ɐ����B�l�����{���甪����{�܂Ŕ�ь����p�������鈟�M�ѐ��̃g���{�ŁA�A�W�A�ɍL�����z�B���Q���������A�Z�݂悢�ꏊ�����߂����ʁA�ɓߒJ�ɂ����荞�悤�ł��B
�@����ώ@�ɍs�����ꏊ�́A��ɓߋ���s�̓슄�����A���v�X����ׂ̃g���{�r�B�����́A���������ԓ����݂̂��߂ɎR���������A�N�������o���Ƃ����ߑ�I�Ȏ��R�ώ@��B�g���{�r�̖ڂ̑O�̎Ζʂ���A�₦���N�������o�Ă��ăn�b�`���E�g���{�̐����ɓK���Ă���炵���A�ȍ~���̊Ԃɂ�����ɋ��������n�b�`���E�g���{�̐����n�Ƃ��Đ�������A���݂Ɏ���Ƃ����Ƃ���B
�@���̓n�b�`���E�g���{�ώ@��͍����ځB��N�u���쌧�Ńg���{�Ƃ����ΏH���낤�v�Ƌ㌎���o�|���Ă������Ƃ���A�O�q�̂Ƃ���G�ߊO��B�Ƃ̎���ɂ����ł���A�L�A�J�l�����ώ@�ł��܂���ł����B���̔��Ȃ��������A���N�͘Z���̏������ɏo�����Ă����܂����B
�@�g���{�r�ɓ�������ƁA�����Ȃ肽������̃g���{�̊��}���B�������A����̓i�c�A�J�l��V�I�J���g���{�̎p�B�i�g���{�r�͂������萮������Ă���̂ŁA�n�b�`���E�g���{�����łȂ��A�����̎�ނ̃g���{���������Ă��܂��B���̓����M�������}��C�g�g���{������������ł��܂����B�j
�@�u��~�ʂقǂ̏������g���{�Ȃ��ł��Ȃ����B�܂����N����U�肩�v�Ƃ�����Ȃ�����������r�����Ă݂�ƁA�����`�I�r�̒��ɐ�����X�M�i�̂Ă���ɐ^���ԂȈ�~�ʁB
�@�����t�@�[�u���搶�̊ώ@���J�n����܂��B�u����ς菬�����Ȃ��B�ł����̂̂�������~�ʂ��͑傫��������ȁB�v�u�������^���Ԃ��B�ڋʂ͂₪�����ăr�[�Y�ʂ������肾�B�������ɂ͈��F�Ɣ��F�̎Ȗ͗l�̂�����B����̓��X�Ő^���ԂȂ̂��I�X���ȁB�v�u�Ƃ܂����Ƃ��̉H�̔z�u���Ɠ������B�v�u����H�I�X�͂P���ȏ�͓����Ȃ����B���̏������͈͂��Ȃ��ȂȁB�v�u���S�̔����k�͌����邩�Ȃ��B�v�Ȃǂƌ����Ȋώ@�B
�@���j��A�n�b�`���E�g���{�͊m���ɒ������������������������ǁA������ɂƂ��Ă͂���ȂɏW�����������������藊���������O�̂ق����������Č������������������B
�@�@�@
��160�b�w�L�����v���z�C�x
2008.8/19�f��
�@�A�N�e�B�u�ȉ䂪�Ƃł����獡�܂ŃL�����v�Ȃlj�����s���܂����B�{�i�I�Ȗ��c�����������Ƃ�����܂��A�L�����v�����Ȃʒi�������̌��ł͂Ȃ��͂��ł��B����Ȏ��j���A�w�Z�̗ъԊw�K�ŃL�����v�ɍs���Ă��܂����B
�@�w�Z�̒��Ԃ����Ƃ̃L�����v�����́A�Ƒ��Ƃ͂ЂƖ�������������낳������A�����̌��ɂȂ�ł��傤�B����ɂ��������c�̂ł̃L�����v�ł����̌��ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B����̓L�����v�t�@�C�A�[�ł��B�Ƒ��ł̃L�����v�ł́w�����x���x�Ȃ�ł��܂����L�����v�t�@�C�A�[�܂ł͖����ł��B�����̃L�����v��ȂǂŁA�L�����v���Â̎��R�Q���t�@�C�A�[���s���邱�Ƃ�����悤�ł����A�m��Ȃ��l�����ƃt�@�C�A�[���͂�ł�����Ȃɂ͐���オ��܂���B�����ȃZ�����j�[��������A�t�H�[�N�_���X�������肷��̂͂�͂�c�̂ł̃L�����v�Ȃ�ł͂ł��傤�B
�@�o���̎����͉J�U�[�U�[�B�J�b�p�𒅍���ňꎞ�Ԕ��́g�����h�ɂȂ�܂������A���ٓ���H�ד����̂��낢������Ă��邤���ɁA�J�͂�������オ���Ă���܂����B�������ŗ[�H�̔�ᴐ�ईȍ~�̊����́A�S�ė\��ʂ���{�ł��܂����B
�@�[�H�̃��j���[�͒�ԃJ���[���C�X�B����ނ�����A��ނ������͊��ꂽ���́B�݂�ȂƗ͂����킹�Ă��������J���[�������ł��B
�@���͂�͂育�тł��傤�B��N�̉Ƒ��L�����v�Ŕ�ᴂł̂��т̐��������݂�����`�����܂������i139�b�Q�Ɓj�A��ؓ�ł͂����Ȃ��Ƃ��낪��ᴐ�ं̂������낳�B�݂�Ȃł��`�����`������Ă��邤���ɏł����Ă��܂��܂����B����������قǐ[���Ȏ��Ԃɂ͂Ȃ炸�A�����Ƃ����~���W�߂āA�Lj����̂��т͂��ƂȂ��܂����B
�@���Ȃ݂ɁA�����̒����͂�ł́A���т͊����Ȃ��̂������܂����B���������тɏW�����������������A���X�`�����̂��x���Ȃ�A�Q�Ăē��ꂽ���܂˂����قƂ�ǐ���ԂŁu�h���Đh���ă}�C�b�^�v�Ƃ������̂ɂȂ��Ă��܂��܂������c�B
�@��̓e���g���B��̃e���g�ɂT�l�Ŕ��܂邱�ƂɂȂ��Ă��āA���̃����o�[�ɂ���ăL�����v�̊y���������肷��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�����q���̍��͂����ƐQ�Ȃ��ł�����ׂ肵����A�B��ăg�����v���������A�e���g���甲���o���ăE���E�������肵�Ă��܂������A����͕ς�����̂��A���ʈ�����������搶�ɓ{����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��߂������悤�ł��B
�@�����A���������c�̂ł̃L�����v�ł����̌��ł��Ȃ��L�����v�t�@�C�A�[�̂��Ƃł����H���j�ɂ��Ɓu�����[�������Ⴍ�āA�ڂ��̐g�����Ⴉ�����v�B�y������������ǂ������낤���ǁA������Ǝc�O�Ȋ���������Ȃ��c�B
�@
��161�b�w�V�ɐ��n�ɉԉx
2008.8/27�f��
�@�Ă̖���ʂ镗���Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��ł��グ�ԉł��B����ȑł��グ�ԉ𑫉��Ɍ����낵�����Ƃ�������ł��傤���B
�@�����̂ڂ邱�ƂS�N�A2004�N�H�ɂ��̃v���W�F�N�g�͗����オ��܂����B�v���W�F�N�g���w�ԉ��ォ�猩�Ă݂悤�I�x�B
�@����͉Ƒ��ŏ����Y�x�ɓo�������̂��Ƃł����i��78�b�Q�Ɓj�B�����Y�x�R�����珼�쒬����]�����ہA�ڂ̑O�Ɂw�M�B�܂��퉷�����x��������ł͂���܂��B�u���������A���炭�O�ɐ������̉ԉΑ���������ˁB���̑ł��グ�ԉ��������猩����ǂ�Ȃӂ��Ɍ�����̂��ȁH�v���̈ꌾ�Łw�ԉ��ォ�猩�Ă݂悤�I�x����B
�@�������������ԉΑ��͉ċx�ݒ��̂��߁A�䂪�Ƃ͕s�݂Ȃ��Ƃ������A���N�܂Ŏ��{�ɂ�����܂���ł����B�����č\�z�S�N�A���ɔO��́w�ԉ��ォ�猩�Ă݂悤�I�x�����N�s�����ƂɂȂ�܂����B
�@�Q���҂́A���Ďҕ�����ƁA�l�N�O�̓o�R���قƂ�NJo���Ă��Ȃ����j�A�ȏ�ł����B�o�R�ɂ����v���o�̂Ȃ��ꂳ��ƁA���Ƃ����B�ꖪ�ł�������o�s���ɖ����������������j�͕s�Q���ł����B
�@�������ԉΑ��͌ߌ㔪������B���ł������珬���Y�R���܂Ŗ�ꎞ�ԁB�e���g�݉c�Ȃǂ̎��Ԃ����z���Čߌ�Z���ɏo���B�����悤�Ȃ��Ƃ��l����o�R�҂������ς������炢�₾�Ȃ��A�Ǝv���o���Ă����܂����B�K������Ȃ��Ƃ��l����l�͑��ɂ��Ȃ������悤�ŁA��l�����ŎR���V�~�Ɛ�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B���т�H�ׂāA�e���g�ŋx�e���ď������[�ԉ̑ł��グ��҂��܂����B
�@�u������������I�v�Ƃ������j�̐��B���炭�x��ăh�[���Ƃ������B���ɑł��グ���n�܂�܂����B����ł͑ł��グ�Ă���̂ł��傤���A��X���猩��Ɗቺ�y�����̂ق��ɗ����Ă��܂��B���j�́u���������v�Ƃ����\�������ɗǂ�������܂��B�ԉƉ�X�̊Ԃɂ���������͈̂����܂���A�S�̂��ƂĂ��N���A�ɂ��ꂢ�Ɍ����܂��B�X�^�[�}�C���Ȃǂ́A�ԉ�Ƃ̑z��O�̎��_���猩�Ă��܂�����A��ׂ���������������܂��B�ԉ����ĊX�̓��肪������Ƃ���́A�ƂĂ��s�v�c�Ȋ��������܂��B�����x��ĕ������Ă��鉹�́A����ɂ�����̉G�X�q���x�Œ��˕Ԃ�A���Ƃ������ʂ悤�ȋ�C�̉����ĂȂ�Ƃ����z�I�B�����ĂȂɂ��������܂܂ŁA���ނ��đł��グ�ԉ�����Ƃ����̂��V�N�ł����B
�@���̌�A�]�C�ɐZ��Ȃ���R���Ńe���g���A���ɂȂ��ĉ��R���Ă��܂��s�v�c�ȗ]�C����l�̐S�Ƒ̂��ݍ���ł��܂����B
�@�Ō�ɓ�l����̈����A�w�V�ɐ��@�n�ɂ͉ԉ́@�����Y�x
�@
��162�b�w�u�b�u�b�u�[�x
2008.9/4�f��
�@���N�q���Ƃ��̉ƒ��Y�܂��w�ċx�݂̎��R�����x�B���N���j�����g�̂́w���{�S���E�Ԃ̃i���o�[�v���[�g�T���x�ł����B
�@��w���ɍs�������C�n���ւ̎Љ�w�łs�n�x�n�s�`�Ԃɋ��������������ƂƁA�����_�́u�ċx�݂̎��R�����́A�w���ׂ����ĕʂɉ��̖��ɂ������Ȃ��ł��낤�Ƃ������ƁE�ł������̑̂��g���Ē��ׂȂ��Ɛ�ɂ킩��Ȃ��Ƃ������Ɓx���厖�Ȃv�Ƃ������t�ɏ]�����̂ł��傤�B
�@���ו��͂������ĊȒP�B�ċx�ݒ��A��Ƀf�W�J�������������A���{�S���̎ԗ��̓o�^�n�i���{�Ƃ�����Ƃ��̒n���̂��Ɓj�̃i���o�[�v���[�g���ǂꂾ���W�߂��邩���L�^�Ɏc���Ă����Ƃ������̂ł��B�i���o�[�v���[�g�����߂ė��s����̂ł͂Ȃ��A���j���ړ����钆�łǂꂾ���o��邩�ׂ܂��B����܂肶�낶��T���āA�ʐ^�ɎB���Ă���Ɖ������œ{��ꂻ���ȂƂ��낪��ԓ���Ƃ���ł��傤���B���ƈ��S�ɂ͖��S�������˂Ȃ�܂���B
�@�Ƃ���ŁA�S���ʼn���ނ̃i���o�[�����邩�����m�ł��傤���H�ߔN�����̗p����Ă����w�����n�i���o�[�x���܂߂ĂȂ��105��ނ�����܂��B���쌧�̒Z���ċx�ݒ��ɂǂꂾ���o��邩�B���N�̉Ă̂��o�����\��́A���e�̎��Ƃւ̋A�ȂƎዷ�ł̊C�����̂݁B���j�̗\�z�ł́u�����������������Ȃ��v�B������\�z�Łu���҂����߂�80��ށv�B��������105��ރR���v���[�g�ڎw���ă��b�c�S�[�I
�@�܂��͋߂��̂��X��{�݂Ȃǂ���B�ӊO�ɂ����Ȓn�悩�炨�q�����Ă���悤�ŁA�������Ȃ�20��ނقǂ��W�܂�܂����B���̕��Ȃ�R���v���[�g��������Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�ȂƊC�����̂��ߍ������H�ցB�r�`�E�o�`�̂��тɒ�܂莟�j�𒆐S�ɉƑ����o�ŒT���ĉ��܂��B�������ɍ������H�͉���������̎Ԃ������A��B�Ⓦ�k�̎Ԃɂ���������o��܂����B�ዷ�������_�Ŗ�80��ނ��Q�b�g�B
�@���������̂����肩��}�Ƀy�[�X�_�E���B�Ȃ��Ȃ��V�����i���o�[�ɏo��܂���B����Ɨ\�z���Ă��������n�i���o�[�ɂ͌��\�o����̂ł����A��͂�k�C���E���ꂪ�������B�����ė\�z�O�Ɏ��j���ꂵ�߂��̂�����Ƒ啪�ł����B�k���̕��䌧�ɍs���Ίm���Ǝv��ꂽ����͋��s�{�ɓ����Ă���Ȃ�Ƃ��Q�b�g�B�啪�͋�B�n�悪�S���W�܂����̂ɗB�ꌩ�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@���s���Ō�A����ŗ[�т̔����������ċA�낤�Ɨ���������X�łȂ�Ɖ��ꔭ���I��Ղ̈��ŗ��s����߂����邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���ljċx�ݒ��ɁA�\�z��傫������96��ނ��̃i���o�[�v���[�g�ɏo����Ƃ��ł��܂����B
�@���̒����A����Ă݂�ƌ��\�͂܂�܂���I
�@
��163�b�w������x
2008.9/28�f��
�@�Ă͂���ς�C�����ł��B�A�N�e�B�u�ȉ䂪�ƂȂ̂ɁA�������N�͊C�����ɍs���Ă��炸������ƕs��������Ă��܂����B�ŁA���䌧�ዷ�E���l���̊C�ɍs���Ă��܂����B
�@�䂪�Ƃ̊C�����͋��ł��B�i��V�b�Q�Ɓj�`���v�`���v���ƋY���̂ł͂Ȃ��A���[�̂���Ƃ���ł������āA�����l������A�L���̂����肵�Ċy���ނ��̂Ȃ̂ł��B�i�ώ@�y�щƑ��ւ̎����̂��߂Ɉꎞ�I�ɕ߂܂��邾���ł��̂ŁA�����Ȃǂƌ������܂���悤�Ɂj
�@�ዷ�E���l�̊C�ɗ���̂͂T�N�Ԃ�̂��ƁB�ȑO�������Ƃ����j�͊o���Ă��܂���ł����B�������f�r���[�ƂȂ鎟�j�́A�݂�Ȃɂ�������Ƃ�Ȃ��悤�ɂƔ閧�����p�ӂ��܂����B����̓V���m�[�P���B
�@�䂪�Ƃ̊C�����ł͑�X�V���m�[�P���͗p�����܂���ł����B�������ς��܂ł�����䂪�Ɨ��̓V���m�[�P���ɍ���Ȃ����߂Ȃ̂ł����A���j�͂܂������܂ł����邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�C�������\���邽�߂ɂ��L�����ƍl���Ă̗̍p�ƂȂ�܂����B
�@�g���ƌ��߂����̂́A�g������M���������ЂƂ��������j�́A�V���m�[�P���w������A�������C�Ńg���[�j���O���n�߂܂����B�������ŊC�ɍs�����Ƃ��ɂ͈�l�O�Ɏg�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���N�̊C�͂ʂ邩�����B���̗̂܂܂ɊC�������܂��Ă���A�������܂�Ɋ���Ă��܂���B������������x�̐[���i�R�����炢�j�܂ōs���Ƌ������܂��B���j�͂����ŃV���m�[�P���ŃX�[�n�[���Ȃ���v�J�v�J�������܂ܐ������̂����Ă��܂��B�������ŊC�����\�����\�ł����悤�ł����B�������\�Ȍ�������邱�Ƃɂ����킵�Ă��܂����B�R���܂Ő[���Ȃ�ƒ�܂ł�������Ċl����T�����Ƃ͂ł��܂��A��̐�����Ă��邭�炢�͂ł���悤�ɂȂ�܂����B�Q���قǂȂ炵������������ăT�U�G�ȂǑ{�����Ƃ��ł��܂������A���ۍ̂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���j�̃V���m�[�P�������Ă����܂��������͕̂ꂳ��B���j�����ȕꂳ��́u�������đ����ł����������j���邵�A�����Ƃ������I�v�Ƃ����̂ł��B���Ⴀ�؋��������Ă��炨���Ƌ}篃V���m�[�P��������{�w���B���������ʂ̂ق��́A�����ւŃv�J�v�J���Ă��鎞�Ԃ����������ƈȊO�͂��܂萬�ʂ͏o�Ȃ������悤�ł��B�܂�����ł�������`���Ă��鎞�Ԃ����������ƂŁA���܂ňȏ�ɊC�������y���߂��悤�ł͂���܂������B
�@���N�ő�̊l���͕����߂܂�������i�R�T�����j�B�j���ł���̂������Ȃ�߂܂����̂ł����܂����̂��Ǝv���Ă��Ȃ������̂Ŗ{�l���r�b�N���I����Ȃ�f��ŕ߂܂���Ȃ�Ă��͂�C���I�i�C�V��Ƃ�����������j
�@�@
��164�b�w���˂�x
2008.11/07�f��
�y���ˁE��z�����i�ܒi�j������Ђ˂邱�ƁB�܂�����ɂ���ĔP���Ȃǂ����邱�ƁB��:����
�@�ѓc�E���ɓߒn��ł͂��܂�Ȃ��݂̂Ȃ����t�ł����A���ق���ь����䂪�Ƃł͂��Ȃ��݂̌��t�B�����āA�ꂳ�悭���˂��Ă��Ă͑呛������̂łȂ�����ł��B
�@����ȂƂ��낪��`�����̂ł��傤���A���j���w�Z�̊K�i�ł��˂��ċA���Ă��܂����B���j�͕��������ތ�A�w�w�Z�̊K�i���x�Ƃ����̂�����Ɍ������A���X�K�i���삯�オ��삯����Ă���悤�ŁA�����͂��˂邾�낤�Ɨ\�z���Ă��܂����B���j���킭�A�u����������Ȃ������B�w�Z�̊K�i���͂����܂ł����S���B�v�Ƃ������Ƃ炵���ł����A����������𑱂���悤�Ȃ�����Ƒ傫�Ȏ��̂���������͎̂����̗��B�����C�Â��Ă��炢�������̂ł��B
�@���āA�s�o�ɂ����˂��Ă��܂����炳�����Ƃ��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�܂��͗�₵�܂��i�����ɂȂ�Ȃ����x�ɁI�j�B�����ė�₵�A��ꂪ���邩�ǂ������m���߂܂��B�ɂ������Ȃ���ɂ���A�s�̗̂�V�b�v�ő��v�ł��傤�B��ꂪ�������Ƃ�����ςł��B���Ă�����Ă��Ƃ́A�x�сi�ؓ���F�j���������Ă��邩�A����ό`���Ă��邩�A�����܂�Ă��邩�A�Ƃ����\������������ł��B�f�l���f�͋֕��A�a�@�ɍs���̂��m���ł��B�����ĕK�������g�Q�����B���Ă��炤�悤�ɂ��Ă��܂��B
�@����̒��j�́A�����Ɏ��オ���Ă����̂Ń����g�Q���R�[�X���ē��B�����g�Q���B�e�ō��ɂُ͈킪�Ȃ��A�x�ё����Ɛf�f����܂����B�����������ƊO���̗����̐x�т��������Ă���Ƃ������ƂŌ��d�Œ�B�A�C�V���O�𑱂��āA�����̂Ƃ��������ĉ��߂Ȃ��悤�ɂƒ��ӂ���܂����B����ɂ͏��t��܂Ŋ��߂��܂������A��������w�Z���A�x�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��f�肵�Ă��܂����B
�@�a�@����A���Ă�����A���Ƃ͗�₵�Ĉ��Âɂ��邵������܂���B�������a�C�̂Ƃ��̈��ÂƂ͈Ⴂ�A�ړ������ł�����Ƃ͕��i�ǂ��芈���ł��܂��A���������`����������B���˂������Ƃ𗝗R�ɁA�Ȃɂ��ƃT�{�낤�Ƃ��钷�j�ɐ�������̂��A�e�Ƃ��Ă̊ŕa�̈ꍀ�ڂƂ��ĕt���������܂����B
�@�����ȍ~�A�w�Z���v��x�Ȃ̂��������ƂɁu�����ɂ�����v�ƌ���������Ă�������Ȏl���Ԃ��߂����܂����B�q���R�q���R���Ȃ�������\���݂ɂ�����Ă����ɂ��ւ�炸�c�B���܂��ɘA�x�����̒��ɂ́u�w�Z�܂ŕ����Ȃ��v�ƕꂳ��ɎԂő��点�܂����B�i�ꂳ��͎������悭���˂�̂ŁA���˂����l�ɔ��ɊÂ��č���܂��B�j
������͂����܂ł��䂪�Ƃ̑Ώ��@�ł��̂ŁA�F�l�͂�������̐��㓙�ɂ����k����Â���܂��悤�����ӂ��������B
�@�@
��165�b�w�x�A�x�x
2008.11/19�f��
�@�H�^������A�M�B�̐_�����̘A�x�Ƃ�������ς�s�y�ł��傤�B�H�ׂėǂ��A���ėǂ��A�V��ŗǂ��I�Ȃɂ�����Ă��킵��������߂����邱�Ɛ��������ł��B�����10���̎O�A�x�A���j���M���o���ĐQ����ł��܂��܂����B
�@�Q���قǑO����u�Ȃ�ƂȂ��������炭�炷��v�Ƃ͌����Ă��܂������A�����ȏ�Ɍ��C�ɂ������炵�ĉ���Ă���p�ɁA�Ƒ��͂������肾�܂���Ă��܂����B���j�̖�A�Ԃ���Łu���ɂ��v�Ƒi���A����Ƒ̉��v�������o���܂����B�����Ă݂��37�x�S���B���������A�z�c���R����ĐQ�Ă������Ƃ��l�����킹��Ƒz��͈͓̔��B�܂��M������Ƃ����Ă��������M�Ȃ킯�ł��Ȃ��A�y�j���̌ߑO���������Q�����Ă����Ύ��邾�낤�Ƃ������������Ă��܂����B
�@�������A�����N���Ă݂�Ɨe�͈̂����B�M�͂�������38�x��ɏオ��A�H�~���K�N�b�Ɨ����Ă��܂��܂����B�����̂�������Ȗڗ͂��Ȃ��A���X�ɃR�^�c�ɂ����肱��ł��܂��܂����B
�@�����Ȃ�Ƃ����ǂ����悤������܂���B�X���Ɨ�p�V�[�g�œ����T���h�C�b�`�B������܂�����A�X�|�[�c�h�����N�A�o�i�i�Ȃǂ�p�ӂ��āA���ƂȂ��������邱�Ƃ����ł��܂���B�ł��A�����납�猳�C�Ȏ��j�̂��ƁA�[������ɂ͂������������o���A�����ɂ͂�������S�J�ɂȂ邾�낤�Ǝv���Ă��܂����B
�@�Ƃ��낪����͂����ȒP�ɂ����܂���ł����B��ɂȂ��Ă��M���ۂ���������܂܂������肵�Ă��܂��B�M������ɉ����炸38�x��㔼���L�[�v�B�H�~���Ȃ��A�o�i�i�ƃ��[�O���g��Q����܂܌��ɂ�����x�����H�ׂ��܂���B���ǂ܂����ꂵ�����ɐQ���܂܉߂����܂����B
�@���a����ځB���������ς荂�M���L�[�v�B�Ԃ���ł������肵�Ă��܂��B�������������Ȃ����j�Ɂu������Ƃ��炢�a�C�Ńp���[�̗����Ă�Ƃ��̕������ƂȂ����Ă����v�ƌ����Ă��闼�e�ł����u���v���H�v�Ǝv���n�߂܂����B�a�C�Ɏア�ꂳ��͕a�@�ɘA��čs�������Ďd���Ȃ��悤�ł����A�����͎O�A�x�̐^�A�d�Ăȏ�Ԃł��Ȃ��̂ɓ��Ԉ��~�}��ɂ������Ƃ͂͂����܂��B����ς肨�ƂȂ����Q�����Ă�����������܂���B
�@���a�O���ځB�������ɏ������M���������Ă��܂����B���ɂ͋N���オ���ĐH�����ۂ��悤�ɂȂ�A�݂�݂錳�C�ɂȂ��Ă��܂��B�ڂɂ͂�������Ȍ����߂�A���������Ȃ����낤��Ɠ����n�߂܂����B�����Ȃ�������v�I�����͊w�Z�ɂ��s����ł��傤�B
�@�����łȂɂ��B�Ƃ͌������̂́A�H�̍s�y�O�A�x��������Q���܂܉߂�����ĉƑ��͂������f�ł��B�������ɍs���\�肾�����̂ɁA����������������̂Ɂc�B���`���B
�@
��166�b�w��ɂ�ɂ����傤�x
2008.12/5�f��
�@���쌧���Ƀe�[�}�p�[�N�͏��Ȃ��A�V�т̖ʂł��w�K�̖ʂł����т������̂ł����A������Ɖ��o�����Ċy����ł��܂����B�s����̓��g�����[���h�B�������H���g���ēԂقǂ̓�M�n�悩��͂��Ȃ��݂̃e�[�}�p�[�N�ł��B
�@���g�����[���h�ł́u���E�T���h�E�B�b�`�I�s�v�Ƒ肵�A�e�p�r���I���䂩��̃T���h�E�B�b�`�E�n���o�[�K�[15��ނ𖡂킦���悪�s���Ă��܂����B���������̓��͏H����̐�D�̍s�y���a�B���Ȃ�̐l�o�ŁA�S�ĐH�ׂ�̂͂�����Ɩ��������ł��B�s��Ƒ��k���Ȃ���i��ł����܂��傤�B
�@�܂��͓��{�E����]�[���Łu�X�p���o�[�K�[�v�B�|�[�N�����`�����~�[�g�ɗ��Ă���Y�����n���o�[�K�[�ł��B�n���ɂ�����Ƃ�����������̂̂܂��Ƃɔ��������B
�@�����Ă̒����u�������o�[�K�[�v�ƃ��L�V�R�u�^�R�X�v�͂��܂�̍s��Ƀp�X�B��ڂł��łɃp�X�Ƃ����̂���Ȃ��̂ł����A�ŏ��̈���ƂĂ����������������߁u�݂�ȐH�ׂȂ��Ă������ł��������v�Ƃ̗\���̌��ʂł��B
�@�l�ڃC���h�l�V�A�́u�W���b�t���v�B�o�i�i�ƃ`���R���[�g���Ƃ낯�邨�������A������o�Ŏ��j�̈ꉟ���ł��B
�@���[���b�p�]�[���ł��h�C�c�́A�X���[�N�n���Ɛ��n�����ґ�ɂ͂����u�J�b�Z���[�T���h�v�ƁA���[�X�g�|�[�N�ƃ`�[�Y���h�C�c�p���ł͂����u���[�X�g�|�[�N�T���h�v�B����Ƀt�����X�̃I�[�v���T���h�u�N���b�N���b�V���v�ƃC�^���A�́u�T���T���G�b�g�v�B�����͂ǂ����s��B�������S�p�X�͉������̂łǂꂩ��c�A�h�C�c�r�[�������݂���������̓ƒf���u���[�X�g�|�[�N�T���h�v�Ɍ���I30���̍s����t�̃r�[���ʼn䖝���ĐH���܂����B�����ł����A�ꂳ��ꉟ���I
�@�A�t���J�]�[���ł́u�_�`���E�R���b�P�o�[�K�[�v�B���łɃ��j���̋��Ă����H�ׂāB�ؖ��������炢�܂����B
�@�C���h���i���Ŋ������u�T�u�W���[���v�A�^�C�k���̃s���h�\�[�Z�[�W�́u�T�C�E���h�b�O�v�ƐH�אi�߁A�u�T�C�E���h�b�O�v�͕�������^�̔��������ł����B
�@�؍��u�v���R�M�h�b�O�v�͔����A�������������������Ă��܂����B�Ȃ�Ƃ����ƈ���B���j���C�ɂȂ��Ă���A�R���b�P�����C�X�o���Y�ł͂��u�O���R���b�P�o�[�K�[�v���Ȃ�Ƃ��H�ׂ邱�Ƃ��o���܂����B���{�炵���e�C�X�g�Œ��j�ꉟ���ł����B
�@�Ȃ�����ӂ܂ŋ삯�������āA����ŁA�H�ׂ܂����āA���݂܂���������ɂȂ�܂������A���Ȃ����C�������喞���A�K���Ȉ���ł����B
�@����ɂ��Ă��A����H�ׂ��Ȃ���������ނ̃T���h�E�B�b�`���C�ɂȂ�c�B�������s���킯�ɂ͂����Ȃ��������̋@��ɐ�ΐH�ׂĂ��I
�@
��167�b�w�X�g���C�N�x
2008.12/27�f��
�@���w���Ƃ��Ȃ�ƁA�w���̐e�q���W�܂��Ęa�C�\�X�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ă��܂��B�e�̂ق��́A������������m���Ă���q���B����l���ۂ��Ȃ����p�ɂ�����ƌ˘f�����o���A�q���̂ق��ł́A�̂���̎�����m���Ă���C�p���������ŁA���ɂ�����Ƌ�����u���Ă��������Ǝv���W�Ȃ̂ł��B����Ȏ����A���w�Z�̐e�q���N���[�V�����Ƃ����Ɣ����ȋ������̂���Â����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ŁA���w�R�N���̒��j�N���X�̍��N�x�̐e�q���N�̓{�E�����O�ł����B
�@�䂪�Ƃł͂����T�N���O����q���Ƀ{�E�����O��̌������Ă��܂��B�ʂɏ����v���{�E���[�ɂ��悤�Ƃ��Ă���킯�ł͂���܂���B�w�������̌����厖�B��������ƂȂ��ł͏�Ȃ��x�Ƃ����䂪�Ƃ̎q��ĕ��j�ɏ]���đ̌����������̂ł��B������̎��Ƃ̋��s�ŁA���܂��܃{�E�����O��̑O��ʂ����Ƃ��u�{�E�����O���Ăǂ�Ȃ́H�v�Ƃ������j�̌��t�ł�������̌����肵�����̂ł��B����ȗ����x���{�E�����O��ɒʂ��A���j�͂�����j�����������o����悤�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����B
�@���Đe�q���N�ł��B����̎q���������ǂ̂��炢�{�E�����O�ɐe����ł���̂��H���̉ƒ�ł͐e�q�ł���Ă�����̂Ȃ̂��H�����������܂ǂ��{�E�����O�Ȃ�Ă���Ă���l�͂���̂��H�䂪�Ƃ̒��j�����āA���������o����悤�ɂȂ����Ƃ͌����܂����A���ꂪ���ΓI���x���ł����قǂ̂��̂Ȃ̂��H�����̃n�e�i��������܂܃Q�[���J�n�ł��B
�@�������ɂ������ꂳ��̒��ɂ́w�{�E�����O�u�[������x���������āA�����ł�130�_����悤�ȕ������l����������Ⴂ�܂����B����q���̕��͂Ɛ\���܂��ƁA�o���҂Ɩ��o���҂̍������ɂ͂������B�P�Q�[����50�_�قǂ����Ƃꂸ���イ���イ���Ă���q�������\���܂��B�e���Q�Q�[�������Đe�q���N�͏I���B��l�̕��D����350�_�قǁA�q���̕��D���҂�290�_�قǂŁA�D���҈ȊO�̐��т͌�����\�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�@����w�Z���琬�ѕ\���z���A�䂪�Ƃ͕��������T�ʁA���j���q���̕��Q�ʁi�����W�ʁE��͂蕃�ɂ͏��Ă��I�j�ɂȂ��Ă��܂����B�e�q���Ƀx�X�g�e�����肵���͉̂䂪�Ƃ����ŁA���Ă݂�Ƃ���ς�F����ȂɃ{�E�����O���Ă���ĂȂ��̂ˁc�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B���ꂵ�������肿����҂�p��������������c�B
�@�䂪�Ƃ̃{�E�����O���x�����������������Ƃ������Ƃ������������A���j�ɕ����܂��Ƃ��鎟�j��������Ă��܂��B���̎��_�Œ��j�ɏ����Ă����A���w���̒��ł��ʗp����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�����127�_���o���喞���Ŏ������ĉ���Ă��܂����B
�@
��168�b�w���͂�V�̊`�̂��ˁx
2009.1/1�f��
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N���q��ĕ�����ƁA���̉Ƒ�����낵�����肢�������܂��B
�@���쒬�ɏH���K��܂��ƁA�X�����������ɂɂ��₩�ɂȂ��Ă܂���܂��B���܂ŃV���b�^�[���~�肽�܂܂ɂȂ��Ă����X�悪�傫���J��������A�Ԃ�≩�F�̏��i���Ƃ��낹�܂��ƕ��ׂ��A�����̂��q����ł������������̂ł��B�����ł��A�ʕ��̒�����������ɃI�[�v������̂ł��B
�@�䂪�Ƃł��ʕ����������悭���p���܂��B�����\���I��K����쐅��V�i�m�X�C�[�g��ӂ��͖��N���p�����Ă�����Ă��܂��B
�@���āA�����̍w���͈ꉞ�����S���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A��l�Ŕ����ɏo�����邱�Ƃ͂܂�����܂���B�Ȃ��Ȃ�A�ʕ��������ɍs���ړI���w���ȏ�Ɂw���H�x�ɏd�_���u����Ă��邽�߂ł��B
�@�I�ʏ�ł�������x�͎��H�����Ă���܂����A�P�i��ł���ɃZ���t�ł��邱�Ƃ������A�i��□�̓����Ȃǂ̐����͂��Ă���܂���B����ɂ���ׂĉʕ��������ł͎��ɂ��܂��܂Ȏ��H�������Ă���A��������ɓ���ׂɓ���܂��B����A�S�Ẳʕ��������������ł���Ƃ͌����܂��A�䂪�Ƃ͂��������Ƃ������T���Ă����܂��B�䂪�ƂɂƂ��Ă����ʕ��������Ƃ͎��H�������ς������Ă���āA������ʔ����Ƃ���Ȃ̂ł��B
�@�ʕ��������ɍs���ƈꎞ�Ԃقǂ����Ă����Ȏ�ނ̎��H�������Ă��炢�܂��B������͂����Ɣ�������ōs���Ă��܂�����{�C�Ŗ��킢�܂����A���N�̏o���□�̓������������蕷���Ă����܂��B�ʂŌ����ƈ�l�œ����O���قǂ��������ł��傤���B���j�͂��̎��H�̂������Ń����S�̎�ނ□�̓�������������o���A���������S���ł���قǂɂȂ��Ă��܂��܂����B�����Ė��ƕi��ɖ����ł����Ƃ���ōw���ƂȂ�킯�ł��B���������ŐH�ׂ镪������܂����A�e���ւ̕t���͂��ɂ������Ԃp�����Ă�����Ă��܂��B
���́A�ʕ��������Ɍ��炸�䂪�Ƃ͎��H����D���ł��B���H�̗ʂ̑������������X�A�Ƃ����}�������m�����Ă���Ƃ����Ă����ł��傤�B
�@�f�p�[�g�Ȃǂł͏펞���H�R�[�i�[������܂����A����ȊO�ɂ���������A�����ՂƂ��������ɂ͂�����肽������̎��H�R�[�i�[������܂��B���������̂�������Ƃ���������Ɋ���čs���Ă��܂��܂��B
�@�ό��n�̂��y�Y�R�[�i�[�����H�}�j�A�ɂ͂��ꂵ���X�|�b�g�ł��B�����ł��������Ă��Ȃ��悤�Ȃ��َq��H�ނȂA����ς莎�H�Ȃ��ɂ͔����ɂ������̂ł��B�����m���߂Ă�������������u���������ȁH�v�B���������Ă��ǂ����ŐH�ׂ����Ƃ����肻�����Ɓu��[�߂��v�B�܂��������瓖�R�~�B�Ƃ��Ă����������Ă��l�D�����āu�Ƃ�ł��Ȃ����v�Ƃ������Ƃ�����܂����B�܂������ł����ό��n�Ƃ������Ղ��Ă��������ō��z�̕R������ŁA���������Ȃ��̂�H�ׂ�����肵���Ⴄ��ł����ǂ˥���B
�@
�w���͂�V�̊`�̂��ˁx
�V�t�ōP�Ⴂ��͂��邽����ҏo�T�B�Ӗ��݂͂�ȂŒ��ׂĂ݂悤�I
�@�@
��169�b�w�P�n�x
2009.1/21�f��
�@���쌧�̏��w�Z�ł́A�T�N���ł��č���̌�����w�Z�������悤�ł��B�����͐H�ׂ邾���ŁA���肪���݂����܂芴���Ă��Ȃ����̂ł��A��ςȋ�J�Ƒ����̐l�̎肪������āA����Ƃ����ɓ���Ƃ��������������Ƃ͔��ɏd�v�ł��B�Ƃ�����ɂ��ꂸ�A�䂪�Ƃ̂T�N���̎��j���č���̌����܂����B
�@�܌��ɓc�A��������Ƃ��납��\���̒E���܂łЂƂƂ���̌������Ă�������悤�ł��B�܂��A�w�N��120�l�ȏア�ēc��ڂ͂P���ł�����A����Ȃɋ�J����قǂ̑̌��͂��Ă��Ȃ���ł����c�B�Ƃɂ������ɂ�����Ȃ킯�Ő���Ō�̑̌���w���n�Ձx���s���܂����B���j�������A�����̂͂����ĂŁA���n�Ղł͂��݂����āA����𖡂키�Ƃ������Ƃł����B
�@���Ė��͖݂��ł��B�䂪�Ƃł����N�݂��͂���Ă��܂����A����͋@�B���ł��B�݂��@�ɂ��Ă��Z�b�g�����炠�Ƃ͂ق��Ƃ��Ă����݂��ł��܂��B�ł����A����͂����͂����܂���B�P�Ƌn�Ńy�b�^���y�b�^�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���j�͂���Ȃ��Ƃ�������Ƃ�����܂���B���͕��������������Ƃ�����܂���B��̎��ƂŖ݂����������Ƃ͂���܂����A�܂��c�t����������������`�����Ƃ͂���܂���ł������A�݉��ŃA���o�C�g�����Ƃ������̂͋@�B�i�@�B�Ƃ����Ă��P�Ƌn�ł����̂ł����j�����Ă��܂����B�ܔN�O�ɒ��j�̕Ă̎��n�Ղł��݂������܂������A��������������������́A���낢��Ȑ��b�����邾���Ŗ݂������Ȃ������̂ł��B�Ƃ����킯�ō��̌��A����������̎��n�Ղɂ͂�������̎Q�������Ȃ��A�N���X�̖݂������ɔC������A�قڑS�Ă�C�����Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�����������ݕĂ��^��Ă��܂����B�܂��͑̏d�������ĕĂ�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����͍��܂łɌ������Ƃ��������̂ł�����v���o���Ă���Ă݂܂��B�E�j�E�j����Ă邤���ɂȂ�ƂȂ�����Ă����̂Ōy�����Ă݂܂��B�y�b�^���y�b�^���A���������������B�����Ă���юU��Ȃ��̂Ŏ��������ƌ��B�q���B������邪���20���Ă����܂��B15�l�قǂ��I������Ƃ���ōŌ�̎d�グ�ɂ�������o��B�͂����߂ăy�b�^���y�b�^������ƁA���������ɂ����������B
�@���̂��Ƌ}���ł��ꂳ�����݂��ۂ߁A�q���B�����ȕ��E�S�}�E�����܂Ԃ��Ă����܂��B�������J��Ԃ��Ė݂����I���B���ꂳ���������Ă����������g���`�ƈꏏ�ɐH����ɂȂ�܂����B
�@�H�ׂĂ݂�Ƃ��܂��I���߂Ă����݂Ȃ̂Ƀf���V���X�I�e�q�Ƃ��ǂ��U�̖݂����H���Ă��܂��܂����B
�@������������N�����Ă����܂������̂��H
�@
��170�b�w���їg����܂����x
2009.1/29�f��
�@����̕�����̒a�����p�[�e�B�[�͂�����Ƙa���ł܂Ƃ߂Ă݂܂����B���̃��C���f�B�b�V���Ƃ��ĂĂ�Ղ�����]���܂����B�����ĉƑ����p�ӂ��Ă��ꂽ�̂͂Ȃ�Ɓw�Z���t�Ă�Ղ�x�ł����B
�@�Z���t�Ă�Ղ�Ƃ́A�H���ɃR�����ƂĂ�Ղ���p�ӂ��A�߂�������̏�ŗg������悤�ɐH�ނ���������Ă���Ƃ������̂ł��B�C���[�W�Ƃ��Ă͗��قŏo����鏬�������g��l�Ă�Ղ�h���K�͂ɂ������̂Ǝv���Ă�����������ł��傤�B��K�͂������đ����|����킯�ł͂���܂���B�H�ނ����ʂɁA��ʂɗp�ӂ���Ă���킯�ł��B����p�ӂ��ꂽ�̂́A���сE�L�X�E�Ȃ��сE���܂˂��E���ڂ���E�T�c�}�C���E�A�X�p���K�X�E������ȂǁB���ꂼ�ꂪ���X�̎O�l�O�قǗp�ӂ���܂����B
�@�H�ނ����Ɏh���A�߂ɂ���߂����ɂf�n�I�܂��͂��т��炢���Ă݂܂��傤�B�W���[�W���[�������Ƃ����ɂ�������������Ă��܂��B���������͂�����Ĉ����グ�āA�y�����������āw�J�v�b�x�B���A���܂��I���ꂪ�����Ŕ������P��39�~�̂��тƂ͎v���Ȃ��I������̂��X�Ȃ�R��800�~���炢�ŏo�Ă��邦�ѓV������ۂǂ����������I�����ĂȂ��т������Ă݂悤���B���܁`���I�ǂ����������g�����Ă͎��ɂ��܂��B
�@���@���ʼnƑ������Ă݂�ƁA�Ȃɂ��݂�Ȃ��낤�듮������Ă��܂��B�Ȃɂ��Ă���̂��ƌ��Ă���ƁA�H�ނɂ���Ă���߂�ς��Ă���ł͂���܂��B���j���������Ƃɂ́u�������̈߂̓T���T���ŁA�������̈߂̓g���g���Ȃ�v�ƁB�����Œ��j���u�A�X�p���₦�т̓g���g�������܂��ȁv�ƁB����ɕꂳ�u�Ȃ��₩�ڂ���̓T���T�������������ˁB�T�c�}�C���͂����ƃh���h���������������ˁB������ƍ���Ă����v�ƁB�Ȃ�قǐH�ނɍ��킹�Ĉ߂�ς���Ȃ�ĂȂ�ăc�E�ȂB�����̐H�����ŕ�����͂���Ȃ��Ƃ������ƂȂ����B����ɁA�V�䂾���łȂ��A�����E�������܂ŗp�ӂ��Ă���B�ǂ������������ȉ��o����`�B
�@�H�ނƈ߂Ɩ��t���̑g�ݍ��킹�͖�����B���j�H���u������P���͂Ă�Ղ�H�ׂȂ��Ă�����v�Ƃ������炢�A�Ƃ������Ђ��������܂��܂ȂĂ�Ղ��H�ׂ܂���܂����B
�@����`�\�͖�������B�����p�[�e�B�[���Ă����Ƃ������ނ𒆐S�Ƃ����m�H�ɂȂ��Ă��܂����ǁA�����a�H�������˂��c�A�ȂǂƎv�������ɒ݂��Ă������ǂĂ�𒅂Ă݂�ƁA�u��H�Ȃ����������v�B���C����Ȃ��_�C�j���O���[���łĂ�Ղ��g���܂������̂ŁA�����������炯�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B
�@�����A������͂Ƃ��Ă���ςȑ|���Ɗ��C�ŖZ�E���ꂽ���Ƃ͌����܂ł�����܂���B
�@
��171�b�w�̂��̂��x
2009.2/13�f��
�@��N���A�������p�̖叼��肪���쏭�N���R�̉ƂōÂ���܂����B���N���Q�����A�����Ȗ叼����ꂽ�̂ŁA��������j�ƕ����̂��̂��Q���������܂����B
�@���āA���̐��쌻��Ŏg�����̂�����̘b�����Ă����܂��傤�B
�@����A���퐶���̒��ŏ��w�����̂�������������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă����ł��傤�B�䂪�Ƃ̎��j����ɂ��ꂸ�A�قƂ�ǐG�������Ƃ�����܂���B�w�Z�̎��Ƃ�2�E3�傱���Ƃ�������Ƃ�����悤�ł����ƒ�ł͂���Ă����L��������܂���B���N�̖叼���̂Ƃ��Ɉꉞ��������Ƃ�����͂��ł����A�}�l���ƒ��x�ł��Ƃ͕����撣�����悤�ȋC�����܂��B�Ƃ������ƂŎ��j�́A�������̂�����f�r���[�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B
�@�f�r���[��ɂ��Ă͑ΐ푊�肪�育�킷���܂��B�|�̂������ߐ�ł��B�ۂ��܂܂̖��̂����ē���̂ɁA�@�ۂɕ����Ȃ��悤�Ɏ߂ɐ�̂ł�����B�������A�叼�p�̒|�ł�����O�{�̒|���p�x�ɐ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�i�����|��^�Ő��āA�Е����Ђ�����Ԃ������{�͓����p�x�̂��̂��ł������Ɏv���ł��傤���A��������Ƌt���|�ɂȂ��ĉ��N�������̂ł���Ă͂����܂���B�j
�@�q�����̂�������g���Ƃ��ɂ܂���Q�ɂȂ�̂��A�؍ނ̌Œ�ł��B��l���Ƒ��Ńh���Ɠ��݂��Ă����Α��v�ł����A�q���͑̏d���y���̂ł������艟���������܂���B�����ĕ���Ȗ؍ނȂ炨�K�̉��ɕ~���Ă��܂����Ƃ��ł��܂����A�ۂ��|�ł͂�����ł��܂���B������̑̏d��݂��Ă����邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�@���̏�Q�͐菏�ł��B�q���͑�l���r���Z���̂ŁA�̂�����̃X���C�h�����Z���A��n�߂̏����t���ɂ����̂ł��B�Ȃ��Ȃ��������Ȃ�������A�Ȃ����Ă��Ă��܂����肵�܂��B�ؖڂɐ^���������鎞�����ē���̂ɁA�߂ɉ��{�����낦��̂͑�ςł��B����͕�����̕��ƍ��킹�Čv�Z�{��`�����X������̂ŁA��r�I����������̂�I�ׂ�Ƃ������_���������ď�����ł����܂����B����ł������͂�����Ƃ��������Ƃ���ĂȂ�Ƃ��A���܂ɂȂ�܂����B
�@�O�Ԗڂ̏�Q�̓X�^�~�i�ł��B��{�̖؍ނ��I���܂ł͈�C�ɐ����ق������܂���܂��B�������̗͂ƂƂ��ɏW���͂ɗ��q���͓r���ł���ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł�������́A�|������ł��邱�Ƃł����Ƃ����Ԃɐ�I���A��Ȃ��N���A�ł��܂����B
�@�|���ꂽ��A���Ƃ͍��C�����Ă��˂��ɍ���Ă��������ł��B��Ǝ��ԘZ���ԁA���j���撣���č��グ���叼�́A�����̊ԉ䂪�Ƃ̌��ւ������ɏ����Ă���܂����B
�@�@�@
��172�b�w�c�C�X�g�x
2009.2/27�f���@
�@�~�ɂȂ�ƉƂɂ������āA�^���s���ɂȂ肪���ł����A���~�̉䂪�Ƃɂ͖����B���̗��R�́w�����h�T�[�t�x�I
�@�����h�T�[�t�Ƃ́A���E�Ώ̂̓̃{�[�h�𒆉��̃X�v�����O�����̂˂���_�Őڑ����A���E�̃{�[�h�����݂ɓ��ݍ��ނ��ƂőO�i����Ƃ����A�X�P�[�g�{�[�h�̐e�ʂ̂悤�Ȃ��́i�ʐ^�Q�Ɓj�B���̃{�[�h���x���Ă���̂͂�������̃^�C�������Ȃ̂ňꌩ������ł����A�Z���Ԃ̗��K�ŒN�ł��ȒP�ɏ�肱�Ȃ���悤�ɂȂ�A��l����q���܂ŒN�ł��ȒP�Ɋy���ނ��Ƃ��ł���X�|�[�c�A�C�e���ł��B�i���[�J�[�̉�������j�u���C�u�{�[�h�Ƃ������O�ŕʃ��[�J�[����̔�����Ă�����̂�����܂������̂Ƃ��Ă̓X�g���[�g�T�[�t�B���ƌ����邱�Ƃ������悤�ł��B
�@�����̃e���r�ŏЉ�Ă����̂��������j���A�u���N�̒a�����v���[���g�͂���ɂ��āv�Ɗ�]�B�����C���^�[�l�b�g�ł����A�a�����O�ɑ��掮�������Ȃ�ꂷ���ɒ���ƂȂ�܂����B
�@�w�Z���Ԃ̗��K�ŒN�ł��ȒP�ɏ�肱�Ȃ���x�Ƃ͂������̂̍ŏ��͂������Ȃт�����B�w�����b�g���܂𒅗p���ĕ�����̏�������Ă̒���ɂȂ�܂��B
�@�܂�����Ă݂܂��B���܂���B����Ⴛ���ł��B�^�C����������ɕ���ł��Ă��邾���ł�����A�ق��Ă�������|��܂��B
�@��������肷��ɂ��A������Ɛ��������i��ł݂܂��B�Q���قǂœ|��܂��B�T��قnjJ��Ԃ��ƃo�����X�͂Ƃ��悤�ɂȂ�܂����B
�@���͎��͂Œn�ʂ������ď�荞�݂܂��B��͂�Q���قǂœ|��܂��B�T��قnjJ��Ԃ��Ƃł���悤�ɂȂ�܂����B
�@���ɍ��E�̃{�[�h�����݂ɓ��ݍ���őO�i���Ă݂܂��B���ꂪ�����ς�ł��܂���B����ƃo�����X���Ƃ��悤�ɂȂ����̂ɁA���ݍ��ނ��߂ɂ͂킴�ƃo�����X������K�v������܂��B����ɁA���݂ɓ��ݍ��ނɂ́A���₭�c�C�X�g�_���X��x��悤�ɑ̂��Ђ˂�K�v������܂��B���|�S���������鐸�_�͂ƁA�S�g�̗̑͂��v������܂��B
�@������20���قǗ��K����������Ȃ�ƂȂ��`�ɂȂ��Ă��āA30���قǂłقڏ���悤�ɂȂ�܂����B���^�[���E�^�[���������ɂł���悤�ɂȂ莩�R���݂ɏ��܂����Ă��܂��B�����āu���̓A�N���o�b�g�ɒ��킾�v�Ƃ������Ă��܂��B
�@���R����������Ă��邾���ł͂��݂܂���B�������Ē��킵�Ă݂܂��B���j�̂��������܂Ō��Ă��܂�������v�A�����ɃX�C�X�[�C�Ɓc�����܂���B�������|���I�������\�z�ȏ�ɑ̗͂�����I
�@30����A�Ȃ�Ƃ�����悤�ɂȂ�܂������A100�����i�ނƑ����p���p���ɂȂ��Ă������߂ł��B���A���A����ǂ��A�Ԃ������A�Ɋ��A���܂����c�B
�@
��173�b�w�������邺�x
2009.3/11�f��
�@�R�[�q�[�ƍg���A�ǂ������D�݂ƕ������Ζ��킸�g���Ɠ����܂��B���тƃp���A�ǂ������D�݂ƕ������Ζ��킸���тƓ����܂��B�䂦�Ɏ����R�[�q�[�V���b�v�ɓ����āA�����`��H�ׂ�Ȃ�Ă��Ƃ͂��肦�܂���B
�@����ȕ����v�킸�R�[�q�[�V���b�v�ɍs���Ă��܂��Ƃ������Ԃ������B�����������̂��͂����肳���܂��傤�B
�@���̋N����͍�N11���ɖ��É��n�R�[�q�[�`�F�[���X���ѓc�ɊJ�X�������Ƃɂ����̂ڂ�B���É��E���C�n��ł͗L�����l�C�̂��̃R�[�q�[�X�̂��Ƃ͕�������ȑO���畷���y��ł����B�����������ŃR�[�q�[�V���b�v�ɂȂǓ���C�̂Ȃ��������ʋC�ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ������B���ꂪ���쌧���o�X�Ƃ������ƂŃ��f�B�A�Ɏ��グ���A������ɂ܂ł��̃��j���[��m�炵�߂錋�ʂƂȂ����B�����ĕ��ꂽ���j���[�̒��ɁA������̃X�g���C�N�]�[���ǐ^�ɓ����Ă������̂��������B���̖��́w�V���m���[���x�B�w�V���x�͓��{��̔��A�w�m���[���x�̓t�����X��ō��̂��ƁB�R�[�q�[�X���������Ƃɂ́A�u�����ۂ��f�j�b�V�����n�̃p���P�[�L�̏�ɁA�����\�t�g�N���[��������Ă��邩��v�������Ńl�[�~���O���X�g���C�N�B����Ɂu�����̃p���P�[�L�̏�ɗ₽���\�t�g�N���[�����悹��Ƃ�������������̂���ɂ���Ƃ����R���Z�v�g�v�Ƃ����̂��C�ɓ������B���A�s���Ȃ���c�B
�@�ƁA��������ŃR�[�q�[�V���b�v�ɓ����Ă��܂����̂ł��B
�@�R�[�q�[�X�Ƃ͂������̂̍g����\�t�g�h�����N���[�����Ă���Ђƈ��S�B�H�����j���[�͕Ĕьn�͈�Ȃ����̂́A�Ĕт������̂���������ۏ��邻�̑吷��Ԃ�͂����ς�B�p���H��D�����H�א���̒��j�ł�������i�Ŗ�������{�����[���Ɏ��j�̓m�b�N�A�E�g�B
�@�����������܂ł͐H���B�������炪�f�U�[�g�A�܂�u�V���m���[���^�C���v�ɓ˓��ł��B���߂͈�l��Ǝv���Ă����̂ł����A�����܂ł̑吷��Ԃ�Ɍv��ύX�B���������j�ƕꂳ�قƂ�ǃ_�E���̂��ߎl�l�ň�Ƃ������Ƃɂ��܂����B
�@���a15cm�̃f�j�b�V�����n�̃p���P�[�L�̏�ɁA�吷��\�t�g�N���[��������Ă���I�v�킸���Ƃ�Ă���Ǝ��Ԃ͋}�ρB�p���P�[�L�̔M�Ń\�t�g�N���[�����ǂ�ǂ�Z����B����͋}���ŐH�ׂȂ���I�p���P�[�L������Ń\�t�g�N���[��������߁A�Y�t�̃��C�v���V���b�v�������Ăق���B�X�g���`�C�N�I�p���P�[�L�̊Â��ƃ\�t�g�N���[���̊Â��ƃ��C�v���V���b�v�̊Â����������邱�ƂȂ������ȎO�d�t��t�łȂ�����o���h������B�܂������I
�@�������D���������Z���違���܂��A�ŗ��������Ė��킦�Ȃ��������Ƃ����Ɏc�O�ł������c�B���x�͐�Έ�l�ň�H�ׂĂ��B
�@�@
��174�b�w�P���Ȃ��x
2009.3/29�f��
�@���~�͍~��ʂ����ɏ��Ȃ��A�����ʂł͐Ⴉ���Ȃǂ��Ȃ��Ă��悭�ĂƂ��Ă�������܂����B���̑���Ƃ����Ă͂Ȃ�ł����A�J�͂悭�~��܂����B�J���~��ƕ��ʂ͎P�������ĊO������킯�ł�������B
�@���͕�����͎P�������̂����ɋ��ł��B�������炸���ƎP�������Ă���ɂ�������炸�A100���������Ɠ�����������Ƃ�ƔG��A���Ȃ��������ł��B�T�C�Y�̑傫�ȎP���g���Ă����߂ł��B�ǂ����ǂ������̂��m��܂��Ƃɂ����P�������Ă��G��Ă��܂��܂��B
�@���Ƃ��ƕ�����̏o�g�n�ł��鋞�s�ł́A���܂�P�������܂���B��ɂ͒n���X�����B���Ă���̂ŁA�J���~������݂�Ȓn���ɂ������Ă��܂�����B��ڂ́A���R�ȋ��s�ł͎��]�Ԃ��g���l�������A���]�Ԃɏ��Ȃ���P���������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���������P�����������Ȃ�����B�O�ڂɁA���s�ɂ͉��Đl�������K��邩��B���āi���Ƀ��[���b�p�j�ł͉J�̓U�[�U�[�~����̂ł͂Ȃ��A�T�^�T�^�������̂ŁA�P�͖��ɗ����Ȃ��̂ł��B���s�Ɋό��ɗ��鉢�Đl���K���ǂ���P�������Ȃ��̂ŁA����������ꂽ���s�l���P�������Ȃ��̂ł��B����Ȃ킯�ŕ���������܂�P�����������Ƃ��Ȃ��A�����������n�Ȃ̂ł��傤�B����ɍ��ł́A�u�ǂ��������Ă��G������A�P�������̂͂�߂悤�v�Ƃ����悤�ɍl���Ă��܂��B�J���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��͍��H�����p���Ă��܂��B
�@����ȕ���������Ĉ�����q���B�����܂�P���D���łȂ��悤�ł��B
�@���j�̎P�Z�p�͂܂��܂��B�G��Ȃ��悤�ɂ����ƎP��������悤�ł����A�A�N�e�B�u�ɑ����肽�����j�ɂƂ��ĎP�͓����𐧌�������̂ɑ��Ȃ炸�A�Ȃ�ƂȂ��Ȃ��܂Ȃ��悤�ł��B������~�J�̎��͎����ďo�܂����A�ꉞ�w�Z�ɂ��u���P�����Ă���A�������J���~���Ă��鎞�ɂ͎P�������ċA���Ă��܂��B������������Ƃ����J��A�~�������肷��悤�ȉJ�̎��͎P���������ɑ����ċA���Ă��܂��B�u���̂ق����G��Ȃ�����v�ƌ����Ȃ���G�ꂽ����C�������Ă��܂��B
�@���j�̎P�Z�p�͕�����قǂł͂���܂��ւ������ł��B�P�������Ă��Ȃ�ƂȂ��ǂ������炪�G��Ă��܂��ƌ������x�ŁA���܂藊��ɂ��Ă��Ȃ��悤�ł��B������J���~���Ă��Ă��A�U�[�U�[�~���Ă��Ȃ���u����ȉJ�Ȃ�~���ĂȂ��ƌ����Ă����ȁv�Ƃ������������˂ĎP�������Ă����܂���B����ɁA�܂��ݎP�Ȃlj��{�����Ă���Ă������ɉĂ��܂��܂��B����Ȗ�Őe������������ߏ���ɂ����Ă��܂��B
�@�ꂳ��͎P�D���ł��B�����̈ړ��ł��}���ɎP�������Ă��܂��B�����ĎP�����炷�W��S���Ă���Ă��܂��B
�@�@
��175�b�w����x
2009.4/22�f��
�@�C���^�[�l�b�g�̃u���O������Ƃ����j���[�X���b��ɂȂ�܂����B�R���s���[�^�ɏڂ����Ȃ��l�̂Ȃ��ɂ́u�p�\�R������������́H�v�Ǝv�����l�����Ȃ��Ȃ��悤�ł��B���ۂɂ͖��ӔC�ȏ������݁i�����݂����Ȃ��́j�ɂ���āA�킯���킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ۂ̂��Ƃ������̂ł����A�䂪�Ƃł����N���т��щ��㌻�ۂ��N����܂����B�������䂪�Ƃ̉��オ�N�������̂̓R���s���[�^�ł͂Ȃ��w�K�v�����g�̏�ł����B
�@���t���������j���A�Ɍ����Ė��������̂ł����A���ǂ����ǂ������ς�킯���킩��Ȃ��Ȃ�Ƃ������オ�悭�N�������̂ł��B����E�Љ�E���Ȃ͂���قNj��ӎ����Ȃ��R���オ�邱�Ƃ͂Ȃ��A�p������킩��Ȃ��������āA�ȍ~�̖��ɂЂт����Ƃ͂��܂肠��܂���A�ڂ�ł��݂܂��B���������w�̐}�`���͑O�₪����̐ݒ�����ɂȂ�܂������{�ŊԈႤ�Ƃ����h���悤������܂���B
�@���j�͉��シ���肪�o�Ă���ƁA������ɕ����ɗ��܂��B�Љ�Ɨ��ȂȂ�u�����ׂĂ݂�v�ƌ����Ƃ��ς݂܂����A����̓v���ł����A�p������w�̃��x���Ȃ�m�[�v���u�����ő����ł��܂��B���������w�̐}�`���͂����͂����܂���B�Ȃɂ���O�₪����̐ݒ�����ɂȂ�܂�������ڂ���m���ɉ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@������͈ꉞ�������w�܂ŏC�߂Ă��܂����A�������o�������Ȃ�ȒP�ł��B���������Z�̃��x���Ō�����藝�������Ȃ���Ƃ����ƁA�Ƃ��ɉ��シ�邱�Ƃ�����܂����B�����Ă��͎��Ԃ������āA������x�������Ă݂�Ƃ����ɒ�����̂ł����A����20�N�x�̒��쌧���Z�����̖�l�����͂ǂ����Ă������܂���ł����B
�@���͎ʐ^���́A���̓���Ȃ��Ɗ�V��Ȃقǂł��B��N�̍��i�҂̒��ʼn��l�����̖����������̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł����A�e�Ƃ��Ă͎q���ɕ�����ē������Ȃ��悤�ł͕s���i�ł��B�K���ōl���܂����B�l���ɍl���܂������ǂ����Ă����Ɏ�������������܂���B���lj���͎~�܂炸�A��Ύ��ɔ��W���Ă��܂��܂����B
�@������̖��_�̂��߂Ɍ����Ă����܂��B�ǂ����Ă����̖�肪�����Ȃ�����������͒��j�Ɂu�����ǂ����Ă���@���m�肽�����畷���ė������Č����܂����v�ƌ����Ē��w�̐��w�̐搶�ɕ����ė����ƌ������܂����B�A��㒷�j�̌��`�́u����͂Ƃ��Ă�����B�搶�������ɉ����Ȃ���������������������B�v�Ƃ������̂ł����B���ꂩ���J���A���Ǝ����I���A���j���������Z�����ɍ��i���܂������A���܂��ɉ�@�͋����Ă�����Ă��܂���c�B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
��176�b�w���^���w�����ҁx
2009.5/16�f��
�@���w���͌ߌ�B�ߑO���ɍݍZ���ɂ��n�Ǝ��������Ȃ��A�V������҂���Ƃ����l���ł��B�����̂͐V�����Ƃ��̕ی�ҁA��E�̂���ꕔ�̍ݍZ���������Q������Ƃ������̂ł��B�Ȃ�Ă������č��Z�ł����琶�k�������ɑ����B���j�����w���鍂�Z���P�w�N��360�l�̑及�сB�S�Z���k���Q���ł���͂�������܂���B����ŕ��ʂł��傤�B
�@������͂悭������w���ł��B�V��������A�����A�j���A��\�������Ȃǂ������A�Z�̂��̂��ďI���Ƃ������́B�܂����ꎞ�Ƀu���X�o���h�̐����t����������A�Z�̂��㋉����\���ꏏ�ɉ̂��Ă��ꂽ��Ƃ����A�g���N�V�����I�Ȃ��̂��p�ӂ���Ă���̂����Z�炵���Ƃ���ł��傤�B
�@�����ɂ��Ȃ�ƂȂ������ꂽ�������c�B���j�����w���鍂�Z�͐������Ȃ������o�Z�Ȃ̂ł����A���w���Ƃ������ƂŁA�قƂ�ǂ̐��k�����w�̐����𒅗p���Ă��܂����B���Z=�����Ƃ����C���[�W����������o���オ���Ă����̂ŁA�ǂ����Ă��A���A���H�Ƃ����������@������܂���ł����B
�@���㋳���ɓ����ď��z�[�����[���ł��B�S�C���琶����̒��ӂ�����A��������̗\����m�F������A���Z���Ƃ��Ă̐S��������ꂽ�肷�鎞�Ԃ��߂��܂����B
�@���āA������I�Ɉꌾ�ŕ]����Ȃ�u�e�����Ȃ����H���ꂶ�ᒆ�w�̓��w���݂��������v�B�����̍��Z���w�����v���o���Ă݂�ƁA���R����C�܂܂��Z���Ƃ���i����ɐ��k���������H���Ă��������ł����c�j���t�����Z���}�����䂪��Z�ł́A�o�Z������̈�قɏ���ɓ���i����Ƃ��Ȃ��j�B�������炢�͂������ł��傤���킸��10���قǂ̓��w���B�z�[�����[�������ɂȂ��i���������z�[�����[���ƌĂׂ鎩�������̋������Ȃ������j�A�J���L�������̑g�ݕ��̐��������������ꂽ���炢�ł��B�i�䂪��Z�̓J���L�����������Ɏ��R�ɑg�߂�w�Z�ŁA�R�N�ԂŕK�v�ȋ��Ȃ������C����A���N�ŁA�ǂ̐搶�̍u���ŗ��C���邩�͎��R�B���Ƃ��Ƃɋ���������ӂ��A��w�̍u�`�Ƃقړ����B���͑�w���w���ɑ�w�̃J���L���������č��Z���ȒP�Ǝv�������炢�ł��B�j�䂪��Z�͂�����Ƌɒ[������悤�Ȃ̂Ŕ�r�̑ΏۂƂ��Ă͉������ł����A���M�̂l�e���Z����]��������Œ��j�̒S�C�ɂȂ����搶���A��͂�e������Z���ɂ�����Ƌ^��������Ă�������悤�������̂Ŏ��̊��z�����Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ��悤�ł��B
�@�z�[�����[�����I���Ɖ��Z�ɂȂ�킯�ł����A�������炪���Z�����B���~�����o��Ə㋉���̐��炪�B�NJ��i�������j�̊��U�U���ł��B�I�݂ɂ͂��炩�����蓦���������c�B���������l�̊Ԃɂ��܂�Ȃ���R�N�ԁA�������Ă����Ă����̂ł��傤�B�撣�꒷�j�I
�@
��177�b�w�U�����`�x
2009.6/6�f��
�@���w�ƍ��Z�̈Ⴂ�������Ă����ΎR�̂悤�ɂ���A�����s�����ɂ͈�ӂ����肻���ł��B���w�Z���璆�w�ɂ��������Ƃ������ω����傫�����Ƃ͈٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł��傤�B����Ȓ��������グ��ƁA���H�ƕٓ��̈Ⴂ���傫�ȕω��ł��B
�@�����Ⴄ���ĉƒ�̕��S���Ⴂ�܂��B�������ٓ���A���S���Ăقǂ̂���Ȃ��ł���A�ƌ��������Ƃ���ł����A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�I�ȕ��S���傫���̂ł��B
�@�䂪�Ƃɂ͓��ނٓ̕����p�ӂ���Ă��܂��B���J�ł��ꂢ�ȕꂳ��ٓ��ƁA�h�{�o�����X�̕����蔲��������ٓ��ł��B�����̂��Ƃł������̖Z�������Ԃɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA������ٓ������߂��̂ł����A���j���ǂ����Ă��ꂳ��ٓ��������Ǝ咣�������߁A�ꂳ�ٓ����W�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�ȑO��l��b�ł������܂������A�ꂳ��͂��ٓ��Ƃ����͎̂���������w���̐H���x���Ǝv���Ă��܂��B���������H�א���̍��Z���ɃK�c�K�c�H�ׂ�����Ƃ����̂ɂȂ�Ă��܂���B�R�}�R�}�Ƃ��������������A���ꂢ�ɐ���t���Ă��܂����B�������������Ɉꃖ�������Ɣ��Ă����悤�ł��B�������͗Ⓚ�H�i�������i�ŋ߂̗Ⓚ�H�i�͓������܂ܕٓ����ɓ���Ă����ƁA�H�ׂ鍠�ɂ͂��傤�ǂƂ��Ă���Ƃ����֗����I�j�A�O��̂����������̂܂ܓ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�i������Ƃ��Ă͎��R�ȌX�����ƍD�ӓI�ɂƂ炦�Ă��܂����A�ꂳ�g�͂�����Ɖ������݂����ł��B�j
�@����ɕꂳ��͍l���܂����B���̕��S�����炷���߁A�T�Ɉ��w������ٓ��̓��x�Ƃ����̂𐧒肵�܂����B���j���͕�����ٓ��̓��Ƃ����L�����y�[�����X�I�ɌJ��L���A��R���钷�j�Ɂu������ٓ����A�����ō�邩�ǂ����������H�v�Ƃ�����������˂����A�Ȃ�Ƃ��R���Z���T�X�邱�Ƃɐ��������悤�ł��B
�@������͒����܂����B�ȂT�Ɉ���o�Ԃ��Ȃ��킯�ł�����A�A�C�f�A���i����Ԃ��Ƃ��Ă������B�u���T�̃e�[�}�͉��ɂ��悤�v�ȂǂƂ����R���Z�v�g�̐ݒ肩��i���Ȃ݂ɐ�T�̃R���Z�v�g�́w�����x�A��X�T�́w�ۂ��x�ł����j�A�H�ޏW�߂₨�����뒲�������̎��W�܂ł����ȃA�C�f�A����̂悤�ɗN���Ă��܂��B
�@�������������R���āi�y����Łj����̂Ɏc�O�Ȃ��Ƃ������܂��B��͕ꂳ��̗j�����o���ڂ��āA���j�Ȃ̂ɕꂳ��ٓ�������Ă��܂����Ƃ����邱�ƁB������͐H�ׂ钷�j������܂�y���݂ɂ��Ă��Ȃ����ƁB�J���Ăт�����ʎ蔠�A�H�ׂĂт�����ٓ����B�H�ׂ����ނ��ƂɃT�v���C�Y�I�Ƃ����̂�ڎw���Ă���̂Ɂc�B�������ޓ�����͋C�ɓ����Ă���悤�ł��B
�@
��178�b�w��s�����x
2009.7/5�f��
�@�S���A�������E���ŐV�^�C���t���G���U�����s���A�s��̐l���݂̂Ȃ��ɍs�����Ƃ��߈��̂悤�ɂ����߂��Ă��܂����B�i�����ɂ��Ă��܂�Ő��������Ȃ����Ƃ�A���Ԃ̉ߏ蔽���ɔz�������̂��u���ʂ̃C���t���G���U�Ɠ����Ή��ő��v�v�Ƃ������Ă��܂����j����ȑ����̐^���������̂U���Q������A���j�������ɏC�w���s�ɍs���Ă��܂����B
�@�����̒i�K����w�Z�͑呛���B�܂��́w���~�̉\���x�̘A������B�����ʂւ̏C�w���s���Ƃ��߂��w�Z������Ƃ���������̔h���Ȃ̂ł��傤���A���̍��܂��֓��ł͊����҂����Ȃ���Ԃł������炿����ƃr�b�N���B���ꂩ�琔���A���j�̓j���[�X�̓x�Ƀe���r�ɂ�������A�S���̃C���t���G���U�ɐ�X���X�Ƃ��Ă��܂����B
�@���Ɋ֓��ŃC���t���G���U�����҂���������ƁA���̑呛���w�}�X�N���D��x���N����܂����B����́u�}�X�N��10�`20���������ĉ������v�Ƃ������́B�ߗׂ̊w�Z�͑�̂��̎����ɏC�w���s�ł�����A���ɓߖk�����炠���Ƃ����ԂɃ}�X�N���p�������܂����B�}�X�N����ɓ�����Ȃ������ƒ납��̒ʕ�̂������ł��傤���A������ɂ́u�T�����炢�ł����ł��v�Ƃ������ւ肪�o����A�o�����O�ɂ́u�Q�E�R���p�ӂ��܂��傤�v�ɕύX����Ă��܂����B
�@�S�z�͂�����̂̂Ȃ�Ƃ����{�̕����łƂȂ��Ă���������͑����܂��B�w���w�n�̕��E����֎~�ɂ��\��̕ύX�x���b��ɏオ��܂����B�ł��܂�����͗��s�̈����Ȃ畽���ł��N���肤����ŁA�w�Z���Ƃ��Ă͂������̈Ă𗷍s�Ǝ҂Ƙb�������Ă��܂��B�����������w�n�̊w�K��i�߂Ă����q�������ɂƂ��Ă͎c�O�ł��傤���A����ȂɐS�z����قǂ̂��̂ł͂���܂���B
�@����ɘb��́w���������̕ی�E�u���E�����Ƃ�x�Ɋւ��鎖���Ɉڂ�܂��B���s���ɐV�^�C���t���G���U�Ɋ��������ǂ��������͉ƒ�Ŗʓ|���Ă���Ƃ������Ƃł��B���������݂�Ƃ��������Ƃ̂悤�ł����A���͂�������s�����ɂ͏�ɗp�ӂ���Ă��鎖���Ȃ̂ł��B���ڂ��w���������x�ƂȂ��Ă��邩�A�w���s�𑱂����Ȃ����ԂɂȂ��������x�ɂȂ��Ă��邩�̈Ⴂ�����ł��B
�@�����������̂́w�����Ҕ����ɂ��v��ύX�x�ł����B�ň��̏ꍇ�A�S�����u������A���Ă����Ȃ����Ԃ����肤��Ƃ������ƁB�Œ���T�Ԃ̑ދ����s�ɂȂ�\��������A����͂���ł����v���o�ɂȂ邩������܂��A�C�w���s�Ƃ��Ă͔߂����B�ł���ΑS�s�����a�Ɋy����ł��������̂ł��B
�@���āA����ȕs��������o�����Ă��������j�͂��ߏC�w���s���A�����s���Ă���ꂽ�̂��A�A���Ă���ꂽ�̂��H����ɑ����B
�@
��179�b�w��s�����x
2009.7/14�f��
�@�V�^�C���t���G���U�����ŏo������Ԃ܂ꂽ���j�̏C�w���s�ł����A�����������}���A�E�L�E�L���N���N�ŏo�����Ă����܂����B
�@����ڂ̗\��́A����c�����E�����Ȋw�����فE�����^���[�̌��w�ł��B
�@����c�����̓R�[�X�Ƃ��Ă͕��}�ł����A�C�w���s�łȂ���Ȃ��Ȃ������Ȃ��ꏊ�ŁA��l�ɂȂ��Č��ɍs�����Ǝv���Ă������悤�ɂ͌����Ă���܂���B�������茩�w���Ă��Ăق����ꏊ�ł����A�w�K�J���L�������̊W�ŁA�܂������̕����n�܂��Ă��܂���B�w�Ȃ��悭�킩��Ȃ����ǂ������ꏊ�x�Ƃ��ċA���Ă�����̂Ǝv���܂����B24�N�x�{�s�̐V�w�K�w���v�j�Ɋ��҂��܂��B
�@�����Ȋw�����ق͒j�̎q�ɂƂ��Ă͔��ɋ����[���Ƃ���ŁA�n�D�ɍ��� ���Ă܂��������Ă�����茩�w����قǂ̉��l������ꏊ�Ȃ̂ł����A�c�̍s������{�̏C�w���s�ł͂��܂������肵�܂���B�w��l�ɂȂ��Č��������̂����܂����������藈�Ăˁx�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B���j�̊��z�ł��قƂ�Ǐo�Ă��܂���ł����B
���Ă܂��������Ă�����茩�w����قǂ̉��l������ꏊ�Ȃ̂ł����A�c�̍s������{�̏C�w���s�ł͂��܂������肵�܂���B�w��l�ɂȂ��Č��������̂����܂����������藈�Ăˁx�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B���j�̊��z�ł��قƂ�Ǐo�Ă��܂���ł����B
�@���j�́g������^�|�C���g�h�͓����^���[�ł����B���ԂƗ\�Z�̊W�œ��ʓW�]��܂ł͂����܂���ł������A��W�]��ő喞���������悤�ł��B�ቺ�Ɏ�s�����߁A�����E�o�ς̒��S���������A�l�Ԃ̖��W�������A�ӊO�ȗ̑����ɋ������悤�ł��B
�@�����^���[�ł̂��y���݂Ɂg���������h������܂����B����͊w�K�i�K�ŁA�y�Y�����X�g�ƒl�i�\���z���A���O�ɉ������\�Z���Ă����Ĕ������ɗՂނƂ����A���̂��������ƂɂȂ��Ă܂����B���������Ƃ����̂́A���̏�̕��͋C���y���݁A���������������Ă܂���āu�������̂܂イ�̕����������������ȁA�ł��������̂���ׂ��̕������ł��炦�邩�ȁv�ȂǂƉƑ��̊���v�������ׂȂ���E���E������̂��y�����̂Ɂc�B���������������̃R���Z�v�g���w�Ƒ��ɔ����ċA��x�Ȃ̂ŁA�q���̎��R�������͂ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������䂪�Ƃ̎��j�ւ̃��N�G�X�g�́u�Ђ悱�����B���Ƃ͎����̍D���ȕ����Ă��Ȃ����B�v�ł����B�܂��\�Z��4000�~�ł����炻��Ȃɂ��낢�딃����킯�ł͂���܂���B����Y��œ����o�i�i�ƃL�[�z���_�[�Ɠ����^���[�I�u�W�F���Ă��܂����B�A���Ă��đ厖�����ɂ��y�Y�������Ă���p�����āA����ς蔃�����͂����łȂ�������Ɗ����܂����B
�@�����Ō�̂��y���݂̓G���h���X�B�h�ɂł͂��F�B�Ƃ̘b���ɉԂ��炫�܂���A�������̂͌ߑO�O���A�ڊo�߂��̂͌ߑO�������������ł��B����Ȃ�œ���ڂ͑��v�Ȃ̂��H�f�B�Y�j�[�V�[���y���߂�̂��H�s�����c������ɑ����B
�@
��180�b�w��s�ό��x
2009.8/4�f��
�@�V�^�C���t���G���U�����ŃR�[�X�̕ύX�����肦��Ǝv��ꂽ���j�̏C�w���s�ł����A��������ڂ̗\����I���܂����B
�@�ŁA����ڂł����A�����łȂ�ƃR�[�X�ύX�̃A�N�V�f���g�I���������̗��R�̓C���t���G���U�Ƃ͑S�����W�B����ڍŏ��̌��w�n�f�B�Y�j�[�V�[�̊J�������͌ߑO10���Ȃ̂ɁA�f�B�Y�j�[�����h�̊J�������̂X�������������Ƃ����v��ɂȂ��Ă�������ł��B���ʂɈꎞ�ԉ߂����̂͂��������Ȃ��̂ŁA�c���̌��w���g�ݍ��܂�܂����B�o�X����~��A��d���̂Ƃ���܂ōs���L�O�ʐ^���B���Ă��邱�Ƃ��ł��܂����B�\��ɂȂ��������ߎ��O�w�K�͑S���Ȃ���Ă��܂���ł������A�s��ɂ���̂ɖL���ȗƁA�������������͋C�ƂȂ�ƂȂ��Y���������𑶕��ɖ��킦���悤�ł��B
�@����10���B�{���́A���⍡��̏C�w���s�̑�ڋʁA�f�B�Y�j�[�V�[�ɓ���ł��B�ǂ��Ƃɕ�����ĉ��ɂƋ삯�o���܂��B�ꉞ���ĉ��v��𗧂ĂĂ����������ł����A���ꂵ�Ă��܂����̋���Ȋy�����U�f�ł���Ȃ������ł��܂��ɂ��܂��Ă��܂��B���j�̔ǂ��������ɂ��ꂸ�A������߂ȃA�g���N�V���������э���ł����������ł��B
�@���č���A���j�͏C�w���s�܂łɐ�ɂ���Ă����������Ƃ�����܂����B����́u�g����140cm�ȏ�ɂ��Ă������Ɓv�B�Ȃ��Ȃ�A�f�B�Y�j�[�V�[�ōł��������A�g���N�V�����Ƃ�����w���C�W���O�E�X�s���b�c�x�̗��p�������g��140cm�ȏゾ����B�t�̐g�̑���̌��ʂ́I138cm�B�c�O�Ȃ��瓋��s�\�A���̃A�g���N�V�����Ŋy����ł��炢�܂��傤�B(����Ȏc�O�Ȏ��j�ɘN��I���̂V���P�����g���������������A117cm������邱�ƂɂȂ�܂����B���[��ނ���c�O�����A�b�v����Ȃ��B)
�@�L���p�[�N�����܂Ȃ����͎̂���̋Ƃł����A�����̓E�B�[�N�f�C�B�������A���Ƃ͋A�邾���̍s���ł�����A���Ȃ肢�낢���ґ�ɉ�ꂽ�悤�ł��B���j�̈ꉟ���́w�^���[�E�I�u�E�e���[�x�B�f�B�Y�j�[�V�[���ł����Ƃ��V�����A�g���N�V�����ŁA�O��Ƒ��ōs�����Ƃ��ɂ͂Ȃ��������̂ł��B���������^�̃A�g���N�V�����ł����A�X�g�[���[���������A�T�X�y���X�̕|�������������ł��B
�@���H��H�ׂ�̂����������Ɂi���H�オ���Ȃ������ɐH�ׂ��Ȃ������Ƃ������z��������܂������c�j�A�����ȃA�g���N�V�����ɉ�������A�����Ղ芬�\���ċA�H�ɂ��܂����B
�@�s���邩�ǂ����S�z���ꂽ�C�w���s���牽�����Ȃ��A���Ă������j�B�u�������܁v�̐�����Ɂu�������납�������v�ƕ����A���̌ウ��ƈ�P���ȏ�������̖ʔ�������葱���Ă���܂����B
�@
��181�b�w���ɐ�����`�O�{�x
2009.8/29�f��
�@�ċx�݂͖Z�����B�ƂŎq�ǂ��ƗV��A�C�Ŏq�ǂ��ƗV��A�R�Ŏq�ǂ��ƗV��c�B
�@���N�̉ċx�݂́w���ɐ��Q��x�Ƃ���ꂱ��ł݂܂����B���ɐ��Q��Ƃ��������āA���R�ɐ��_�{�ɍs�������ł͂���܂���B����ڎw�����̂́A���ɐ�������{�A�O�{�A�ʋ{�I�[���R���v���[�g�B���H�����فA�V�[�p���_�C�X�A���Y�B�����Ĉɐ��̂��܂�����i�ɐ��C�V�E�������E�A���r�E���y�E���㋍�j�R���v���[�g�B�ǂ��܂Ŏ��Ԃ������̂��H�ǂ��܂ō��z����������������̂��H�ꔑ����ɐ��̗��A�Ƃ肠�����o���i�s�I
�@�܂��͍���̃��C���ɐ��_�{�������܂��B���R�������������ĊO�{����B
�@�����ɂ�������炸�J�オ��̃����������钆�A��̑升���ɕ�܂�Ȃ���̎Q�q�B�����{�Q�q��A�{����̕ʋ{�ɂ��Q��A����Ɍ��錩�{�܂ő����̂��A�������ɂȂ�Ȃ���O�{���e�B�������Ɠ��{�ֈړ��B
�@���j���Ƃ������Ƃ�����A���{�̒��ԏ�͂��łɖ��ԁB�\��쉈���̗Վ����ԏ�ɒ�߂������A�P�����قǂ̓����������܂����B�������œ��{�ɒ����ƁA�S�N��̎��N�J�{�ɂ��킹�H�����̉F�����ɑ����āA������n���Ă����܂��B������ʂ�邱�Ƃ�20�N�ɔ��N���炢�����Ȃ����������ƂȂ̂ł����A��͂萳���ȋ���n�肽���Ƃ����̂��S��A�q���B�͕���������Ă��܂����B����ɍ�闈�̍~�J�ɂ��\��삪�����A����ꂪ�g���܂���B����ł��T���_���Ƒ��͌\���܂ōs���A�葫�����Ă͂��܂������s���̈���������Ƃ���ł��B�����������Ȑ_�{�̓m������A�����Ȃ����{�܂ŗ���ƁA�������Ɍ��l�ȕ��͋C�ƂȂ�A�M�S�Ɏ�����킹�Ă��܂����B
�@���ɐ��Q��ƌ����Ă������̕����V�R�ɂȂ�Ȃ��̂��䂪�Ɨ��B�����̂��Ƃ��A�����N�`���[���W�J����A��肾������̎Q�q�ɂȂ�܂��B������ɂƂ��č���̂��ɐ��Q��͌܉�ځB���w�Z�̏C�w���s�ł��K�ꂽ���炢�ł�����A���O�w�K�̓o�b�`���ł��B������������̈��Ǐ��̌w�ɓ���̂��Î��L�ł�����A�V�Ƒ�_�͓��Ӓ��̓��ӁB�Ɏדߊ�E�Ɏדߔ��̍��Y�݂���A�V�F���̖��̂�����܂ŃX���X���ƃX�g�[���[��瞂�܂��B
�@����Ȃ���ȂŌ�椋{�Ȃǂ̕ʋ{�Q����ς܂��A���҂����ˁw���͂炢���x�U��ƂȂ�܂����B�����ł͂������ŐH���ĂƂ����͂��������̂ł����A�����Ɛl���݂Ń_�E���B�ԕ��݂Ɨg���V�͂Ȃ�Ƃ��N���A�������̂́A���Ƃ͗₽�����̂Ƃ���̂݁B���ɉ����̎c�邨�͂炢���ƂȂ�܂����B
�@�d�����Ȃ����炱�̌�̓ł����ς��H���Ă��B�C����������ɑ����B
�@�@�@
��182�b�w���ɐ�����`���{�x
2009.9/8�f��
�@�ċx�݂͖Z�����B�ƂŎq�ǂ��ƗV��A�C�Ŏq�ǂ��ƗV��A�R�Ŏq�ǂ��ƗV��c�B���ɐ��Q��͑O��̑����B
�@�ł́A�V�[�p���_�C�X�Ɠ��Y�i�v�w��j�����āA��قǂł��Ȃ������C�̍K�H���܂��������\��B�������A���͂炢���ł����������ݐH�������Ă��Ȃ��̂ɃE���E���������A����Ɂw�Ԃʂ���x�Ȃ�m�b�̗ւ�30���ȏ���Y�ݑ����i�����A30�������ł͂���܂���B���s�I��������܂��ɔY�ݑ����A�₯�ɖ�X�Ƃ������Ԃ��₳��Ă��܂��B�j�A�\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ������Ă��܂������ߓV�[�p���_�C�X�ɒ��������_�Ōߌ�O�����B�����A�b�J���x�[�A�U���V�̃V���[�͂��łɏI���B�ق܂œԂ�����A���ĉ��̂������肬�肭�炢�ł��B
�@�܂������闷�ł��Ȃ��A�����Ă��܂��Ί��\���܂��B�Ȃ�Ƃ��Ԃɍ������C���J�ӂꂠ���^�C���ŁA�������E�F�b�g�X�[�c�݂����ȃC���J�̂Ђ�ɐG�ꂽ��A�J���E�\�̈���^�C���ŁA�L�̓����̉�݂����ȃJ���E�\�̎����������A�A�V�J�V���[�ŁA���炵���A�V�J�̂������ɘa�܂��ꂽ�肵�ď\���Ɋy���݂܂����B
�@���A�ق̕����ɉ����o�����悤�ɊO�ɏo�A���݂̓v���U�ň��ݐH�����悤�Ǝv�����炻�������فB������ĕv�w��Ɍ������܂��B
�@�V�[�p���_�C�X����v�w��͕����ĂP���B������̔��X�������X�ł�����A������͊ՎU�Ƃ��Ă��܂��B�������ŕv�w����o�b�N�ɂ������v�w�Ŏʐ^���B������A���݂�������������n�ǂ�����ł��܂����B
�@����̂��h�͐H�����E���̊C�����̏h�I�Ƃ����Ă�����̓X�|���T�[�Ȃ��̕n�R���s�ł�����A�����͗����B���܂ł̌o���セ��ȂɊ��҂͂ł��܂���B�����͌Â��͂Ȃ����ǁc�A�����͂��ꂢ�ɑ|���͂��Ă��邯�ǁc�A�i�F�͑��̌������Ȃ�������c�A�����C�͉���ꂶ��Ȃ�����˂��c�B���҂��Ȃ��H���ցB�����`�������I�C�̍K�Ă���I�h�g�͏M����A�ɐ��C�V�m�F�A�T�U�G�m�F�A��m�F����܂ł��Ȃ������ς��B��������i�A���㋍�m�F�A��A�T���m�F�A�z�^�e�m�F�I�ɐ��C�V�̏Ă���������B����ɐ��ɗ�����H�ׂ����Ǝv���Ă������̂��قƂ�ǖԗ�����Ă���I�������ʂ������Ղ�I����͑f���炵���I�������������i�F�������C�������ǂ��ł������B���܂Ŕ��܂����h�̒��Ńg�b�v�N���X�̑f���炵�����I
�@�H����ł����܂ŕ^�ς��ǂ����Ǝv���܂������̂��炢�������Ė���ɏA���܂����B�����ė����A���т�H�o������܂ł��̍K���͑����܂����B
�@�������s�ŏI���A�c���ۑ�͒��H�����قƃA���r�ƈɐ����ǂ�B���ׂĖ����ł����̂��H�Ԃʂ���ł�����₵�Ȃ��玟��ɑ����B
�@
��183�b�w���ɐ�����`�ʋ{�x
2009.10/22�f��
�@�ċx�݂͖Z�����B�ƂŎq�ǂ��ƗV��A�C�Ŏq�ǂ��ƗV��A�R�Ŏq�ǂ��ƗV��c�B���ɐ��Q��͑O�X��̑����B
�@�������s�ŏI���A�c���ۑ�͒��H�����قƃA���r�ƈɐ����ǂ�ł��B�܂��͒��H�����قցB
�@���H�����ق͊F���܂������̃��b�R�A�X�i�����A�W���S���A�}�i�e�B�[�Ȃǂ̊C�b�[���̐����فB�䂪�Ƃ̑��ړI�����b�R�̂��H���^�C���ł��B
�@�܂����b�R�̈��炵�����ƁI�����ĉa��H�ׂ���A��яオ���ĉa���Ƃ�����A���邭�����ĉj���ł݂���A�A��A���Ă����C�Ŏ����������炢�ł��B
�@�܂��C�b�ǂ��̑傫�����ƁB�}�i�e�B�[�͒W���̐������A�V����ɂ���Ȃ̕�����ł���r�b�N���ł��B�C�ɂ���W���S����A�U���V���A�C�����ɍs���ĕl�ӂŐQ�Ă��炠��Ăē�����ł��傤�B����������������������Ɍ���ɂ͎��ɂ��킢�炵���B�Z�C�E�`�̑O��30����������Ă��܂��܂����B
�@��Ԏ��Ԃ��₵���̂́A����̐G�ꍇ���R�[�i�[�B���i�����̌������ɂ���^�R�E�i�}�R�E�A�i�S�E�q�g�f�E���W�i���p���H�݂����ȂƂ��ɕ�����A�G�����ɂȂ��Ă��܂��i�{���͐G�����ł͂Ȃ��A�w�ł��Ă˂Ə����Ă���܂����j�B���j�͂����Ń^�R�����ݏグ�A�i�}�R�����ɃA�i�S�̍ĕ������Ƃƍr�Z�̘A���B����܂ł��ƂȂ������Ă�������̎q���B�̊Ԃɂ����[�u�����g���L���A�呛�����N�����Ă��܂����B�K���ɂ��W������ɓ{���邱�Ƃ��Ȃ������ފقł��܂������B
�@���w�n�͂���ŏI���B���ƃA���r�ƈɐ����ǂ��H�ׂċA�邾���ł��B�A���r��H�ׂ悤�Ɨ���������������A�Ȃ�ƃA���r��4000�~�I���A������߂܂����B
�@���]�ŖK�ꂽ���X�g�����ňɐ����ǂ��H�ׂ܂��B��t350�~�A�����i�����Ƃ��������̂��Ƒz�����Ă������j�ɂ͔��q�ʂ����A���j�ɂ������Ă͂��ǂ�Ȃ�ĐH�ׂ����Ȃ��Ƃ܂Ō����܂������c�j�B���y�Y�Ɉɐ��C�V�`�b�v�X�E�ɐ��C�V���Ђ��A���㋍�ӂ肩���E���㋍�`�b�v�X���A�H�ցB
�@�������������̃A���r���S�c��B�c�O�����ȕ�����Ɏq���B�����܂��́u�A���r�H�ׂ�����Ȃ珼�⋍�������H�ׂ���ˁv�̐����B�i�H�ύX�A�}篏���s���Ɋ�蓹�B���܂�~���̍���������Ȃ��X��T���E��œ��X�B�C���傫���Ȃ��Ă���A����𒍕����܂��B�u���A�������܂��b�I�C�Y�������܂����ǂ���ϓ��ō��I�A���r�͐H�ׂ��Ȃ��������ǂ���Œ������喞�����I�v
�@�q������l���S�����Ȃ����喞���̂��ɐ��Q��ɂȂ�܂����B�������H�ו��̍����ɖڂ�����݂����āA�ɐ��_�{�̂��肪�������Ȃ�������Ă܂����H
�@�@
��184�b�w�o�b�N�E�g�D�E�U�E�t���[�`���[�x
2009.11/1�f��
�@�ċx�㔼�A�䂪�Ƃ̓o�b�N�E�g�D�E�U�E�t���[�`���[���u�[���B�T�E�U�E�V�ƘA�����ă����^�����A��T�Ԃقǂ����Đ��e���܂����B���炭�́A�����Ɖߋ����s�����藈���肵����ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ����c�_�����킳��A�w�`�L���x���������t�ɂȂ����肵�Ă��܂����B
�@������͂��łɃX�p�C�_�[�}�����V�܂Ő��e���A�^�[�~�l�[�^�[���S�b���悤�Ǝv�����̂ł����A�܂��h��̏I���Ȃ����j�Ɏ~�߂��܂����B
�@���āA�Ȃ�����ȉf��u�[��������Ă����̂ł��傤���H�q���g�A�����̉f��̔z�����͂��ׂă��j�o�[�T���ЁB�����͉ċx�ݒ��Ƀ��j�o�[�T���X�^�W�I�W���p���ɍs���Ă�������ł��B
�@���s�̕�����̎��Ƃɍs�������łɁA�Ԃňꎞ�Ԕ��قǂ����Ă݂�Ȃōs���Ă��܂����B������͂Q��ڂ̂t�r�i�A�ꂳ��͂S��ځA�q���B�͏��߂ĂɂȂ�܂��B
�@���߂Ă̎q���B�ɂƂ��Ă͂����Ȃ�̃A�g���N�V�����͂Ƃ����������܂���B�����i�r�Q�[�g���܂��B�u�����O�������ɂ̓X�p�C�_�[�}���͂܂��Ȃ���������A����̓X�p�C�_�[�}������X�^�[�g���I�v
�@������̂��E�߂̓E�H�[�^�[���[���h�B�Ă̏������ɗ������R�͂����ɂ���܂����B�E�H�[�^�[���[���h�Ƃ��������炭���{��̂т���ʂ�A�g���N�V�����B���ւ��ꎮ��p�ӂ��A�C���p���c�ɂ͂������A�S�[�O�����p�A�G��G���A�ɐw���܂��B�V���[���n�܂�Ɗ��҂Ɉ��ʂт���ʂ�Ԃ�B�o�P�c�̐��𗁂сA�{�[�g�̔��A��s�@�̔������ɐg���܂����܂��B�m���̈������j�͎l��ڂɂ����̂Ŋ��\�������قǂł������A�őO��ɂ������j�ƕ�����͂���ł����Ƃ����قǔG��܂���A�V���[���\�ł��܂����B�V���[���I���A�������蒅�ւ�������Ă̏�����Y���قǂ̑u�����I����ł������E�߂����b�オ�������Ƃ�������ł��B
�@���̌�A�W�����V�b�N�p�[�N�ł܂��G�ꂽ��A�^�[�~�l�[�^�[�Ŕ�������A�W���[�Y�Ńr�b�N��������ꂽ��A�o�b�N�g�D�[�U�t���[�`���[�ő勻��������Ɗ��\���܂���A�A�H�ɒ����܂����B
�@������߂��ʎԓ��ł́A�����̂��ƂɂȂ��Ă���f���m���Ă�������Ɗy���߂�ɈႢ�Ȃ��Ƃ������_�Ɏ���A�ƂɋA�������ʂ茩�Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�������ꂳ��́u�C������������v�Ƃ�����ĂŃ^�[�~�l�[�^�[�͍̗p���ꂸ�A�W�����V�b�N�p�[�N�ƃX�p�C�_�[�}���͌������Ƃ�����Ƃ������ƂŖv�B�E�H�[�^�[���[���h�͖ʔ����Ȃ��Ƃ������R�ŕs�̗p�B�o�b�N�g�D�[�U�t���[�`���[���W���[�Y�̂ǂ��炩�ɂ��悤�Ƃ������Ƃ���A���j���u�|������v�ƌ����ăW���[�Y�����d�ɋ��ۂ��܂����B
�@���O�A�`�L�����ȁB
�@
��185�b�w�Y�����Y�x
2009.11/17�f��
�@�������C�K����G��@��Ȃ�Ă���������Ⴀ��܂���B����������܂ň�x���G�������Ƃ�����܂���ł����B�܂��Đ��܂ꂽ����̃R�K���Ȃ�āA�e���r�Ō��邱�Ƃ͂����Ă��A���������邱�ƂȂ�Ă��Ԃ�Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂������A�G���Ȃ�Ă��Ƒz�����ɂ��܂���ł����B�Ƃ��낪���N�̉āA����ȋ@��Ɍb�܂ꂽ�̂ł��B
�@�����d�͂̎q���̌����ƂƂ��āA�l�����q�͔��d�������w���A���̂��ƊC�K���̕���������Ƃ����Â����̂��������̂ł��B�q�������̎��Ƃł�����A���w���̎��j�Ɉē��������̂ł����A���������������́A���j�ɕ����������ɐ\�����݂܂����B�����Đ��܂ꂽ����̊C�K���̐Ԃ����������̎�ŕ����ł���̂ł�����B
�@���Ƃ��玟�j�ɕ����Ƃ���u����A�s���Ă�������Ȃ��v�Ƃ����������Ȃ��Ԏ��B���̂̒��������܂��킩���Ă��Ȃ��悤�ł����A���I�ŎQ���҂����܂�悤�ł�����A�����ő��т���Ăʂ���тɂȂ��Ă�����Ƃ������Ƃ��l�������Ȃ���ł悩�����̂ł��傤�B
�@�\�����̂��Y�ꂩ�����������{�A���d���瓖�I�̂͂������I���т̕�����̗l�q�Ɏ��j�������Ԓ��������킩�����̂����҂��ӂ���܂��ē�����҂��܂����B
�@8��29���A��D�̊C�K�����a�i�H�j�̒��A�ѓc���̃`���[�^�[�o�X�ŏo�����܂����B
�@�O���̕l�����q�͔��d���͂���Ȃ���ł��B���H�̂��ƐÉ����l���s���c�����u�Ɍ������܂��B���c�����u�͓��{�ł͐����Ȃ��A�J�E�~�K���̎Y���n�B��������㌎�ɂ�����K����500���炢�̗����O��ɕ����Y���ɗ��邻���ł��B�����Ă����ƓV�Аl�Зl�X�ȗ��R�łقƂ�Ǜz�������A�܂��z�����Ă��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ی�c�̂̕����ی삵�A�������ěz�������A�����܂ł��Ă���̂������ł��B�ŁA�������͂��̕����̂���`��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�@�������������̂��Ƃ�C�K���̐��Ԃ�A��芪�����̂��Ƃ�����āA���悢������ƂȂ�܂����B�������u��l�ӂ܂ŕ����A���悢��C�K����n����܂��B���̓��̒��z����������̂T�p�قǂ̏����Ȏq�K���B�b����D���������Ă��Ǝ葫���p�^�p�^�����Ă��킢�������炠��Ⴕ�܂���B�����ċA���Ď��������Ȃ�܂����A���������ƌ\���~�ȉ��̔����B���������R�N�łQ���ɂ��Ȃ�A�J�E�~�K����������͂�������܂���B
�@���c�ɂ����g�ł��ۂɒu���Ă��ƃs���R�s���R�ƊC�Ɍ������ĕ����Ă����܂��B�܂����킢�������炠��Ⴕ�܂���B�g�Ԃ��瓪���o���ĉ��֏o�Ă����̂�{���ɖ��c�ɂ���������܂����B�����ĐS�̒��Łu�傫���Ȃ����痳�{��֘A��čs���Ăˁv�ƂԂ₢�Ă��܂����B
�@�@
��186�b�w��x
2009.11/27�f��
�@�ċx�݂Ƃ����Έꌤ���B���܂ł����j�̕������ׂ�A���j�̃i���o�[���ׂȂǂ̖ʔ��i���e�͂��܂�Ȃ��j����������Ă����䂪�Ƃ��A���ɍ��N���ŏI��i���j�����N�ŏ��w�Z���Ƃł��j�B�L�I�̔��Ɏ��j�͂������������������Ă����̂ł��傤���B
�@���j���I�̂́w�X�C�J�̎풲�ׁx�B�X�C�J�̒��̂ǂ̕ӂɁA�ǂ̂��炢�̎킪���z���Ă���̂��ׂ�Ƃ������́B�X�C�J�����ɗ�ɂ��Ȃ���A���z�ʒu�ƌ����`�F�b�N���Ă������@�Œ������܂��B�����A�����̂悤�ɉƑ�������Ē����J�n�ł��B
�@�܂��͒��a��15�����A�d����1.5�����̏��Ԃ�̃X�C�J�Œ��ׂĂ݂܂����B���j�͂��̏��ʂ̃X�C�J�̒��ɓ����Ă����̐���200�Ɨ\�z���܂����i�\�z�̍����́u�Ȃ�ƂȂ��v�ł������c�j�B���ʂ�286�B���������ɗ\�z�������ɂ́A���Ȃ�߂������ƌ����Ă����ł��傤�B
�@���z�̕��́A�c�̈ʒu�Ō���ƁA��[�Ɖ��[�ɂ͏��Ȃ��A���������ɑ����̂͂�������\�z����Ƃ���ł����B
�@���ڂ��ׂ��͉������̕��z�B�J�ɗ��z����\�ł́A�w���ܖ͗l�̍��������Ɏ킪����ł���x�Ƃ��A�w�w�^�̃C�{�C�{�̉�������Ɏ킪����ł���x�Ƃ��������̂�����܂��B����̒����Ŏ��j�����������̂́A�܂��A���g�͒[�������Q���܂����悤�Ȓ��S�p120�x�̐�`�ŎO��������Ă��܂��B�����Ă��̐�`�̒������E�V�����g���[�ɂȂ��Ă��āA���̊e�����̒���������Ɏ킪���W���Ă��܂��B�܂��͘Z�����ɏW�����Ă���Ƃ������ł��B���̈ʒu�ɂ��ẮA���ܖ͗l��A�w�^�̃C�{�C�{�Ƃ͓��ɊW���Ȃ��悤�ł����B
�@����͑唭���ł��B���A��������̒����Ō��߂��Ă��܂��̂͑��v�ł��B���͒��a��30�����A�d����10�����̑傫�ȃX�C�J�Œ������Ă݂܂��傤�B
�@�d�ʔ�ōs����1200�قǂ̎킪���肻���ł����A��̐��͂Ȃ�Ƃ�������557�B�킸���ɓ�{�قǂ����Ȃ��̂ł��B
�@������z�̕��́A��͂肱����̃X�C�J�����l�̌��ʂ��B�ނ����ʂ̕��������ł����B���̌��ʂ����܂��܂Ƃ߂���ƌ����Ƃ��Ă��ꗬ�Ȃ̂ł��傤���A�c�O�Ȃ��炻���͂܂����j�̗͕s���ł����B
�@���Ă��̒����A���ɂȂ���ςł����B�ȂƑ��l�l��11.5�����̃X�C�J��H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł�����B����������Ƃ��������X�C�J���̂ĂĂ��܂��Ȃ�Ă��Ƃł���͂�������܂���B�������������Ȃ��@��o���Ȃ���Ȃ�܂���B�̉��ʼn��������X�C�J��H�ׂ����A�������J�E���g���܂����B���܂�̂炳�ɁA���N�͂��̓�����X�C�J��H�ׂ��ɂ������܂����B
�@�@
��187�b�w�V�����[�x
2009.12/13�f��
�@�w�L�u���̖�c���L�����v��֏オ���čs���r���̈���k�J�́A�܂��Ɂg�G�������h�O���[���h�̐����ł��B���̈�т́u�喾�_���v������k�J�ŁA�����ł��ő勉�A���a�Vm�̃|�b�g�z�[���i�����M���m�������n�j������܂��B����́A�����̗͂Ő���]���A�����N���ɓn���ĉ͏��̌E�݂��@�荞�ނ��Ƃɂ��ł������̂ł��B
�@�L�u���ł́A����k�J�̃G�������h�O���[���̐����ő̌����Ă����������߂ɁA����21�N�W���X���i���j�Ɂu�L�u������k�J�V�����[�E�N���C�~���O�̌��v����悵���Ƃ���A�ߑO�̕��E�ߌ�̕������킹�āA�����O�����50�����Q������܂����B
�@�E�F�b�g�X�[�c��C�t�W���P�b�g�A�w�����b�g�𒅗p�̏�A�C���X�g���N�^�[�̈ē��̉��A�����������̘A������u�喾�_���v�̖�200m�̋�Ԃ��A���ɐZ����Ȃ���Q���Ԃ����ēo��܂����B�r���A��ꂩ�狐��|�b�g�z�[���̑�ڂɑ�W�����v����̌����s���܂����B�x
�@�Ƃ����̂ɉ䂪�Ƃ͎Q�����Ă��܂����B
�@�V�����[�E�N���C�~���O�Ƃ����̂́A���{��ł͑�o��ƌ����A��̒���G��Ȃ���k�サ�Ă����n�C�L���O�̈��ł��B���܂Ńe���r�ȂǂŌ��āA��x����Ă݂����Ǝv���Ă����Ƃ����̃j���[�X��m��A�����\�����Ƃ�����ł��B
�@�����A�Ȃ�ƈ�Ԋy���݂ɂ��Ă������j�����M�B�Ƃ͂������������̃`�����X�B���̋@������炢�܂��V�����[�E�N���C�~���O��̌��ł��邩�킩��܂���B���M�̎��j����l�ƂɎc���A�O�l�ŎQ�����邱�Ƃɂ��܂����B
�@�O���̉J�̂����ő������A����������߂ł������A����k�J�͂܂��ɃG�������h�O���[���̐����B�L�u������ŃE�F�b�g�X�[�c�ɒ��ւ��A�o�X�Ō���ɓ���������X�͂����쒆�ցB�������[���A�ł��C�������`�B�����㗬�ցB
�@��̒�������A�������j���A����o��A���[�v�ɓ`����Ĉ���������B�����̂����ł������V�����[�E�N���C�~���O�̑�햡�𖡂킦���悤�ł��B�������A�c�O�Ȃ��Ƃ���B�r���̋����M���Ŋ����V�т�̌�����͂��������̂ł����A�����̂��ߒ��~�B���������̂������ő�ڃW�����v�����ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂������B
�@����̃��C���C�x���g�Ƃł������ׂ���ڃW�����v�B�����S���قǂ̂��������ڂɌ������Ĕ�э��݂܂��B���\�̍���������܂����A���V�͑u�����̂��́B���C���X�̕�����͂������A�������Ȃт����肾�����ꂳ����A�N�[���Ȓ��j����͂��Ⴌ�Ŕ�э��߂܂����B
�@����[�y���������B�������j��A���N���̌������݂���������A���x�͈ꏏ�ɍs�����ȁB����ς茒�N�����I
�@
��188�b�w��M�}�c�J���@��12�����E10���̏́x
2010.1/1�f��
�@���̃^�C�g�����������̓y�^���N�̘b��ł��B�P���`�X���̏͂́A��N�O�������{��\�Ƃ��ăA�W�A���ɏo�ꂵ�����ɁA�A�ڂ����Ă��������܂����B�����č���A���j���W���j�A�̓��{��\�ɑI��A�W���j�A���E�I�茠�ɏo�ꂷ�邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�܌��ɑ�ꎟ�\�I��A���͐�t�A���͉��R�܂ł�17�Έȉ��̑I�肪�ꓰ�ɉ�s���܂����B�����ł͊e���̋Z�\�̃X�L�����e�X�g����A��ʋ㖼����\�I�ɐi�݂܂��B���j�͂ǂ̋Z�\������Ă��ˏo�����X�L���͂Ȃ��������̂́A���ς����͂��������\�I�i�o�̋㖼�Ɏc��܂����B
�@��\�I��͎����B���s�㖼�ł̑�������e�^�e�b�g��i�V���O���̎����j�B���я�ʎl�������{��\�I��ɂȂ�܂��B
�@�l��ł�����A����삯�����͈�l�ōl���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����Ă��̐�p�����s����Z�p�����R�v������܂��B�܂��A����łW���������Ȃ��̂ŁA�Z�p�����łȂ��A�̗͂�_�͂��[�����Ă��Ȃ��Ə����c��܂���B����Ȓ��Œ��j�͂Ȃ�Ƃ��l�ʂɐH�����݁A������\�ɑI��܂����B
�@���j���o�ꂷ���12�E�W���j�A�y�^���N�I�茠���́A�Ȃ�ƃA�t���J�嗤�̃`���j�W�A�ŊJ�Â���܂��B�u�ǂ��H�v�ƌ����̂���ꐺ�B�������E�n�}�������o���Ē��ׂ܂��B�A�t���J�ƌ������̂́A�n���C�ɖʂ����k���̍��ŁA�X�e���I�^�C�v�Ŏv���悤�ȃA�t���J�ƈႤ�悤�ł��B�܂��A�C���^�[�l�b�g�ȂǂŒ��ׂĂ݂�Ə㉺�����~�ݗ��͂ق�100���A�\�h�ڎ���K�v�Ȃ��A���������ɗǂ��A�C�X�������̃A���u�l���命���̍��̂悤�ł��B����ɑ����̓��i�X�e�B�[���Ƃ����n���C�ɖʂ��������̃��]�[�g�n�B�l�G���͂����肵�A�~�͐Ⴊ�~�邱�Ƃ����邻���ł��B
�@�����A�܂��͏������n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B�́H�N�́H���j�ƁA���������̂ł��B�����A�ŏ�����s���C���X�������킯�ł͂Ȃ���ł����B���j�͂������Z���ł����A�`�[���ɂ͊C�O�o���L�x�ȊēE�R�[�`�����Ă����܂��B��l�ő��v���Ǝv���Ă����̂ł����A���̑I�肽���ɂ݂͂�Ȑe�����Ă����Ƃ����̂ŁA���j������l�ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��A�Ɓg�a�X�h���Ă������Ƃɂ����̂ł��B
�@���j�͊C�O���s���S�҂ł�����A�������낢�닳���Ă��܂��B�܂��V�тɍs���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�y�^���N�̓���ƃ��j�t�H�[���A���ۃ��C�Z���X�A�p�X�|�[�g�������OK�ł��B�������ł�����������ł����Ĕ������͂�����ł��ł��܂��B����ł��A�h�o�C�X�Ƃ��āu�ו��̓R���p�N�g�ɁA�����ɂ܂Ƃ߂�v�A�u�Ƃ��ɕK�v����Ȃ����̂͌������Ŏ̂ĂĂ������ŗp�ӂ���v�A�u��s�@�̒��͂Ƃ肠�����ɂ�����A�ɂԂ��p�i�͂��������Ă����v�A�u���]�[�g�n�Ȃ����v�[��������A���������Ă����v�Ƃ������܂������c�B
�@�o����10���P���B���c���牄�X18���Ԃ̗����B�C�������Ȃ�Ȃ���A����ɑ����B
�@
��189�b�w��M�}�c�J���@��12�����E11���̏��x
2010.1/19�f��
�@�`���j�W�A�y�^���N�I�s�͑O��̑����B
�@���c�����s�@�ɏ�邱��12���ԁA����ƃp���E�V�������h�S�[����`�ɂ��܂����B�����s�@���̌��̒��j�́A�h�L�h�L���Ă͂����悤�ł����A����Ă݂Ďv���̂ق����肵�����S�n�ɂ���������S�����悤�B���Ȃ��������ߕ�����Ƃ͗��ꂽ�Ȃł������A�`�[���̃����o�[�Ƙa�₩�ɉ߂����Ă����悤�ł��B
�@���p���ꎞ�Ԃō��x�̓`���j�W�A�E�`���j�X��`�܂łR���Ԃ̃t���C�g�B��قǂ�肸���Ԃ��Ȕ�s�@�ł����A�t���J�嗤�ցI
�@����ɍ��x�͋�`���玎�����̂��郂�i�X�e�B�[���܂Ńo�X�łQ���ԁB���X18���Ԃɂ��킽��ړ��ŁA�z�e���ɒ������̂��[��O�B���̓��̌ߌォ����͎n�܂�܂��B������̂悤�ɐ��������R�ɕς�����҂Ȃ炢���m�炸�A�������̑I��c�ɂ͂��܂�ɂ��ߍ��B�ߑO���̗��K�ł́A�݂�ȃ{�[���Ƃ�����ł����Ƃ��Ă��܂��B���܂���35�����̏����Ŋ��S�O���b�L�[�B���H�Ƌx�e�łȂ�Ƃ��������Ă��炢�������̂ł��B
�@���͌ߌォ��n�܂�܂����A�ŏ��̓V���[�e�B���O�R���e�X�g����n�܂�܂��B�y�^���N�̋Z�\�̒��́A�e�B�[���Ƃ��������ڑ���̋ʂɓ��Ă͂����o���Ƃ����Z�p�̃R���e�X�g�ł��B�e�`�[���̃e�B�[���[�Ƃ����e�B�[�����̑I�肪�o�ꂵ�܂��B���j�̓e�B�[���[�ł͂���܂���̂ŁA������x�̂�т肷�鎞�Ԃ�����܂����B���������j�́A�l�I�蒆�O�l�Ŏ��������郁���o�[�Ŏl�Ԗڂ̈����ŁA��]�w����̐����������Ȃ��A�u������������o�Ă��炤���玩���Œ������Ƃ��Ăˁv�Ƃ��������ł��B�Ȃ�ƍ���̉����̉B��ړI�w�n���C�ʼnj���x�����s���܂����B
�@�ŏ����j�͉j���Ȃ��ƌ����Ă��܂������A����ȋ@��͂߂����ɂȂ��Ƃ������ƂƁA�S�g�ɓ����𗁂т�Ǝ����ڂ���������������邱�ƁA����ɂ��܂�ʏ����������Ēn���C�ւf�n�I
�@�n���C�܂Ńz�e�����������15�b�B�����������l��˂����Đ����C�ɓ���܂��B���{�̊C��肸���Ԃh���A�Z���ȊC���̖������܂����B����قljj���ł͋t���ʁA20���قNJ��\���Ă����Ɛ�グ�đ��ɗՂ݂܂��傤�B
�@�e�B�[���R���e�X�g�ł͓��{�̑I��͈ꎟ�\�I�͓˔j�������̂́A�\�I�Ŕs�ށA�c�O�Ȃ��猈���g�[�i�����g�ɂ͐i�߂܂���ł����i�ނ̎��͂͂���Ȃ���ł͂���܂���ł������A�ߍ��Ȉړ��̂������A�����̂������A�\�������ɂ���炵�Ă��܂�������͂������ł���͂�������܂���j�B���Ƃ͎����Ŋ��Ă��炢�܂��傤�B
�@�����J�n�͌ߌ���B���j�͗\�z�ʂ�T�u����̃X�^�[�g�B����͂ł���̂��H�������������ɏo����̂��H����ɑ����B
�@
��190�b�w��M�}�c�J���@��12�����E12���̏́x
2010.02/7�f��
�@�`���j�W�A�y�^���N�I�s�͑O�X��̑����B
�@�������͏o�Ԃ��Ȃ��A���͓���ڂɓ���܂����B�\�I�T��������R�����܂ł͂P���Q�s�B���j�͂����܂ŏo�ꂵ�Ă��Ȃ��̂ŏڍׂ͂ق��Ƃ��āA�\�I�˔j�ɂ͂��ƂQ�����Ƃ����K�v������܂��B�����ł���ƒ��j�o��I�s���̃e�B�[���[�ɑ����ăn���K���[��ɏo��ł��B
�@���j�͂قڎ��͂ǂ���̊��҂��ꂽ�����������A���M���������W�J�ɍv�����܂��B������Ŏ��͈ȏ�̗͂������ł�����M�����[����Ȃ�ł��傤���A�����͂ł��Ȃ��Ƃ��낪���̎��́B������12��12�̑�ڐ�B�����Đɂ������ŏI���[�k��Ɏ��ꕉ���Ă��܂��܂����B
�@����ŗ\�I�˔j�͓���Ȃ�܂������A�Ⴂ�ނ�Ɏ̂Ď����͂���܂���B�o����ςވӖ��ł��^���ɍŏI�����ɗՂ݂܂��B�Ǝv�����璷�j�͂܂��T�u�ɉ�Ă��܂��܂����B�܊p��M��������A�C��������Ă郁���o�[�Ő킦�����Ǝv����ł����A�����Ȃ�ƌ����Ă�����Ȃ����Ƃł��B
�@���ǍŏI�����ɂ������\�I�����B���O���ڂɁA�\�I�������������m�Ő키�l�C�V�����Y�J�b�v�Ƃ����g�[�i�����g�ɉ�邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�l�C�V�����Y�J�b�v����͑g���R��B���j���o�ꂵ�A����13�O�ň����I�悩�����I��������͂�����ƕ��G�B������͑O��A�W�A���Ō����햢�����A���ۑ������평�����j�ɐ���z����Ă��܂����Ƃ������Ƃ��������Ƃ���ł��B�ł��܂��A�t���J�܂ŗ��Ė������ŋA���Ă͖ʖڂȂ��̂őf���Ɋ�т܂��傤�B
�@����͑��i�R��B���j�͂܂��܂��o��I���ς�炸���Ȃ��s���Ȃ����͂����܂������A�ɂ�����10��13�ŕ����Ă��܂��܂����B
�@����ɂđ��͂e�h�m�B���Ќ��Ă�������������ƕ�p�[�e�B�[�܂ʼnɂɂȂ��Ă��܂��܂����B�Ƃ������ƂŐ���j���Ȃ������e�B�[���[�̑I��Ɗē������čēx�n���C�ւf�n�I�n���̎q���ƒ��悭�Ȃ�A�R����_�C�u�ɂ�����A�n���C���\�B
�@�z�e���̃v�[���ł������̑I��ƌ𗬂�����A����������ɉ��ɍs����������A���ӂ́u�f�B�X�J�E���g�E���A���A�v�œy�Y�̔������ɂ����킵����B�ʔ������Ԃ��߂����܂����B
�@�����̓C�^���A�t�����X�B�j�㏉�̃t�����X�ȊO�̗D�������Q�Ō��߁A�u�����͂������Łv�̎v�����������܂����B
�@��p�[�e�B�[�ł��e���̑I��ƌ𗬂��܂���B�L�O�i������������A�܂�߂���������A�Ƃ��Ă��[���������Ԃ��߂����܂����B
�@���̌o�������A���j�ɂ͂���Ȃ����ڎw���Ă��炢�����Ƃ���ł����A�A����A�R���ɔR���Ă���̂͂ǂ����Ă�������̕��ł��B
�@
2010.2/19�f��
�@�q���B�͂����ꂱ�̉Ƃ��o�A�ǂ������ꂽ�Ƃ���Ő��������������ł��傤�B����Ȏ�����̐l�B�Ɂu���O�̐��܂������Ƃ���͂ǂ�ȂƂ���H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��傤�B�����������ƁA�悭�m��Ȃ�������Ȃ̂ɋC�t�����Ƃł��傤�B�Z��ł��鎞�ɂ͉��Ƃ��v���Ă��Ȃ������ӂ邳�Ƃւ̋������N���Ă���̂͂����������ł��B
�@��������A���s�o�g�ł����A�Z��ł��鎞�ɂ͂���Ȃ̓�����O�Œn���̎���[���w�ڂ��Ȃ�Ďv�������Ƃ�����܂���ł����B�Ƃ��낪�n���𗣂�Ă݂�Ǝ��������s�̎���m��Ȃ����Ƃɂт����肵�܂����B��w���E��������ɂ��낢�닞�s�̎����w�сA���ɂȂ��Ă���Ɛl���ē��ł���قǂɂȂ�܂����B
�@����Ȃ킯�ŁA�q���B�ɂ����y�̂��Ƃ𑼏��̐l�ɘb����قǂɂ͂Ȃ��Ăق����Ǝv���A���ɓ߂��ے�����悤�ȗ��s���v�悵�܂����B
�@�u���ꂼ���ɓ߁I�v�Ƃ����Ƃт�����̓c�ɂ�̌����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�������A�R�̒�������̂Ȃ�S���ǂ��ł��̌��ł��܂��B�c�ɓ�������̂������̏��ő̌��ł���ł��傤�B�����ō���v�悵���̂́w�ѓc���e�w��ԁE�鋫���l�w������x�̗��ł��B�ѓc���ɓߑ哇�w���A�I�_�L���w�܂ł������������邾���̗��s�ł����B
�@�ѓc���قǐl�̂��Ȃ��S���͓��{���w�Ƃ����Ă����ł��傤�B�S���t�@���ɚ������w�鋫�w�����L���O�x�ł������̉w���x�X�g�e��������ʂ����Ă��܂��B�l�̐Ղ�����Ȃ���l�����Ȃ��A�l���������ɂȂ����Ȃ̂ɐl������B���ꂱ�����ɓ߂̔鋫���鏊�ȁI���������u���ɓ߂��Ăǂ�ȂƂ���H�v�ƕ�����Ă������ł���ł��傤�B
�@�����o���B�ѓc�s�X��ʉ߂��A�V����������܂ł͖��l�w�������ł����A�l�̏�~�����蕁�ʂ̒n���H���ƕς�肠��܂���B��������������10����̉w�͐��܂����B�q�̏�~���Ȃ��B�i�q���\������x�ɒ�Ԃ��A�J�������Ǝv�������u�̌�ɕ��B�w�͂��邯�nj�����͈͂ɉƂ͂Ȃ��B�w����ʂ��铹���Ȃ��B�w�����s���ɂȂ�قǂ������ȏ����Ȃ��B�w�ǂ��납���H���~�݂���Ƃ��낪�Ȃ��n��Ȃ��̂ɓS�����n���Ă���c�B
�@���͂��̗��s�A��掩�̂�10�N�ȏ�O�A����ɋ����\����������l���Ă��܂����B�������ӂ肪���Ȃ��Ƃ������A�Ȃ�̂��߂ɍs�����A��̑���ł����̂ł��B�q���B�̂��߂Ɏ��{�Ɏ���܂������A��������Ԋy����ł����͕̂�����ł����B
�@����A�y����ł����Ƃ������t�ł͕�����Ȃ��B���ɓߐl�̈Ӓn�Ɛ�l�̓w�́A�l�������čs���Ƃ��������ƍ��ɂӂꂽ�悤�ȋC�����܂��B���߂ɂȂ������A���ɓ߂Ƃ����ꏊ����w�C�ɓ��������s�ɂȂ�܂����B
�@�@
��192�b�w�n���ŗ��x
2010.3/5�f��
�@�n���ɂ͍��܂ŏ��Ȃ��炸�����Ă��������Ă��܂������i��48�b�Q�Ɓj�A���N�̏t���n���ɂ����b�ɂȂ�܂����B
�@�����b�ɂȂ����̂́A�����炭�����̐l�ɂƂ��ē��{�ň�ԍs���Ă݂����n���A�ʕ{����n���߂���ł��B�啪�E��B�̂Ƃǂ܂炸���{�L���̉���n�ł���ʕ{����ɍs���Ă��܂����B
�@�ʕ{����̒n���߂���Ƃ����A���r�n���E�S�R�n���E���܂ǒn���E�R�n���E�C�n���E�S�ΖV��n���E���̒r�n���E�����n���̔���������́B���R�S���s���˂Ȃ�܂��܂����A�����s�������ł͉䂪�Ƃ炵���Ȃ��B����̃e�[�}�́w�n���ŗ��E���H�ׂ܂���c�A�[�x�B
�@���r�n���ł͓����F�̂��ꂢ�Ȃ����ƁA����M�Ŏ��炵�Ă���M�ы��������܂����A�{�ݓ��ɉ��͂���܂���B�^�}�S�|�C���g�i�ȉ��s�o�Ɨ��j���O
�@�S�R�n���ł͖җ�ȓ��C�ƃ��j�Ɍ}�����A�ʕ{�����w�n�������x�ɂ�鉷���H�ׂ��܂����B�ƒ�ŐH�ׂ�䥗��Ƒ卷�Ȃ��A�s�o��40
�@���܂ǒn���ł͂ق�̐����[�g���ׂɂ��邾���Ȃ̂ɑS���Ⴄ�F�̂�������̒r�ɂт�����B�����̉��͂����̐����̂������������ۂ��Ɠ��̖��B�����Q���H�ׂĂ��܂��A�s�o��85
�@�R�n���ɂ̓J�o��]�E�����܂��B�����������̂��܂����r�͂Ȃ��A���C�������o���Ă��邾���B��������܂���ł����B�s�o���O
�@�C�n���ł̓I�I�I�j�o�X�ɏ�邱�Ƃ��ł��܂����~���͂���Ă��܂���B�R�o���g�u���[�̂����ł�ł����̓v���b�v���̔��g�ɂ����Ƃ艩�g�B�Q�H�ׂĂ��܂��H�ב���Ȃ��C���łs�o��100�_���_�I
�@�S�ΖV��n���̓{�R�b�ƕ����o���D�̖A�����������ɁB�c�O�Ȃ��牷�͂���܂���ł����B���̓D��䥂ł��炨���������Ȃ̂Ɂc�s�o���O
�@���̒r�n���͌��̂悤�Ȑ^���ԂȒr���L�����Ă��܂��B�y�Y���͏[�����Ă��܂������͂���܂���B�N���̐^���Ԃȗ����H�ׂĂ݂��������̂ɁA�s�o���O
�@�����n���͊Ԍ���B�z�K�̊Ԍ����������Ă���䂪�ƂɂƂ��ẮA������ƕ�����Ȃ����̂ł����B�����Ă����ɂ����͂���܂���ł����A�Ƃ������������ʼn��͍��Ȃ������c�B�s�o���O
�@���̑����يX�ɂ��锄�X�Ȃǂł��n�������ɂ�鉷�������Ă��āA���ǎq���B�ƕꂳ��͂Q�`�S�A������͍��v�U�����炰�܂����B�������A�����������Ⴄ�̂ł��ꂼ��Ɋy�������������H�ׂ��܂����B
�@���������������ǃR���X�e���[���͂��܂�܂��肾��ȁB����Ȑ����𑱂��Ă�����A�����Ƃ����Ԃɖ{���̒n���ɍs���Ă��܂������ł��B
�@����ł��{���̒n�����ʕ{�݂����Ȃ�c���������B
�@�@
��193�b�w�v��I�����x
2010.4/1�f��
�@���N�����Z�����̋G�߂�����Ă܂���܂����B���j�̓�������A������N���������̂��ȂǂƉߋ���U��Ԃ��Ă���ꍇ�ł͂���܂���B���Ɠ�N�������獡�x�͑�w�������}���܂��B���ꂪ���ōςƂ��Ă��A���̗��N�ɂ͎��j�����Z�������}���܂��B�w���X�������x�Ƃ�����قǃe�X�g�̘A���Ȃ̂ł��B
�@�����قǑ�C�x���g�ł͂Ȃ��ɂ���A���w�E���Z���Ƃ��Ȃ�ƁA���ԁE�����̃e�X�g�͔N���s���B���̒���e�X�g�ɒ��j�͉E���������Ă��܂��B
�@�e�X�g��T�ԂقǑO�ɂȂ�Ƌ}�ɏł�n�߁A��́i����C�t���[�N���A�ނ��낱�ꂪ�{�E���H�j�y�^���N���K�����L�����Z������Q�ĂԂ�B���̂����������ďW���ł��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Q�V���Ă݂���A�������Ə̂��Ă͎��j�ƈꏏ�Ƀe���r�����������肵�Ă��܂��B����ȕ��ł��̂ŁA���ʋy�т���ɘA�����鐬�т��ǂ��Ȃ��Ă��邩�́A�����Ŏ����q�ׂ�K�v���Ȃ��ł��傤�B
�@���āA���т͂��̍ە����Ă����܂��傤�B���͈�T�Ԃł͌��ʂ��o�Ȃ��ƕ������Ă���̂ɁA���ł킸����T�ԑO�ɂȂ�܂ŏł�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�d���ɑ��āi���������j���܂����킹��ɂ͂Q�p�^�[������܂��B��͋��ٓI�Ȓǂ����݂ƏW���ł��肬��Ŏd�グ��^�C�v�B������͒����I�W�]�ŗ]�T�������Ďd�グ��^�C�v�B�ǂ������������͐��i�ɂ���邵�A�d���̓��e�ɂ���邵�A���ʂ��o����ΐl���ꂼ��ǂ���ł��n�j�ł��傤�B
�@������͓T�^�I�Ȍ�ҁB���܂łɉ����d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����]�T�������Đݒ肵�A�v��I�ɏ����������ɐi�߂Ă����^�C�v�ł��B����������A�ʒm�\�Ȃǎ茳�ɂ������������쐬���n�܂�܂��B���X������L�^���L�����A�z�z���̈�T�Ԃ��炢�O�ɂ͊��������Ă��܂����B���̕����́A���������ɐi�����Ă����̂ō�Ƃɂ�Ƃ肪����A�w��ς����x�Ƃ�����Ԃ��K��܂���B�Ȃ̂ŁA����̐l�i�Z���⋳���j����w�撣���Ă���x�Ǝv���Ȃ��̕s���ȏ��ł��B
�@����ȕ�����Ɍ��킹��ƁA�u���̓��Ƀe�X�g�����邱�Ƃ͎l���ɕ������Ă��邱�ƁB�����܂ʼn������������Ă��Ȃ��������O�������B�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���j���O�҃^�C�v�łȂ����Ƃ͐Q�V�ƒ��`�����������ؖ����Ă��܂��B��T�ԑO����ł������Ăł���킯������܂���B�䂦�Ɂw��������x�Ƃ������t�͖ƍߕ��ɂȂ炸�A�`����`����V�тɋ����I�ɎQ�������܂��B
�@���̂����Ő��т������Ȃ�ƌ�����������܂��A�������������l���ł��邱�Ƃ͂��̉ƒ�ɐ��܂ꂽ�����番�����Ă��邱�ƁB�����狃�������Ă������܂���B���̂ւ������όv��I�ɂ����Ȃ�������I
�@�@
��194�b�w�E�E���w���x
2010.4/14�f���@
�@�������̂ł��̘A�ڂ��n�܂����Ƃ��A�܂��I���c�����Ă������j���A���w�Z�𑲋Ƃ��Ă��܂��܂����B���X�ڂ��Ă���Ɛ������Ȃ��Ȃ������܂��A�v���Ԃ�ɂ��̘A�ڂ�U��Ԃ��Ă݂�Ƃ����Ԃ����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�����A����͂��������Ƃ������t�ł͂Ȃ��A�ʂ̂��̂ɐi�����Ă������ƌ���������������������܂���B
�@�O�q�����܂������A�I���c�����Ă������j�ƁA���̎��j���r���邱�Ƃ͂����ł��܂���B���̍��̎��j�ɉ����ł������A���̎��j�ɉ����ł��邩���r����Ӗ��͑S���Ȃ��ł��傤�B���ꂩ��̐����E�l���ɕs�����Ă�����̂��A�ǂ̂��炢�����Ă���������ɐ������Ƃ炦�Ȃ�������Ȃ��ł��傤�B
�@����ȂƂ��ɋ����́A�w�����q�Ƃ̔�r�x�������o�������ł��B��ʉƒ�ɂ����Ă͐e�ށE���ҁA�ߏ��̎q�Ƃ̔�r�������o�������Ȃ�܂��B�ł�����͈Ӗ����Ȃ����Ƃ��ƕ�����ł��傤�B�����Ă��ꂩ��̐����E�l���ɕs�����Ă�����̂͊e���̃S�[���i�ڎw�����́j���Ⴄ�̂ł������r�̂��悤������܂���B�i���������Ӗ��ł́A���w���܂ł͑��l�Ƃ̔�r�ɂ���Ďq�ǂ��̐������Ƃ炦�悤�Ƃ����̂͊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��傤�B����������͑������x�����̔�r�ł����āA�D��͂����܂���B���w���܂ł̐����͎��Ԃ̍���������قڑS�������B�ł���i�K�Ȃ̂ł�����B�j�{�l�̊�]����i�H��K���A�ƒ�Ō���Ă���͂��̖]�ނׂ��l�ԑ��E�����l�Ɍ������āA����g�ɂ��Ă������炢���̂���T��o���A�l���A���s���Ă����̂����ꂩ��̐����𑪂��ɂȂ�̂ł��B
�@�����Ă��ꂩ��̐����́A���܂ł��������Ȃ������Ƃ������Ƃ��ł���ł��傤�B��]��i�H���ς�����琬�����ׂ������͕ς�邵�A���z�̐l�ԑ��Ȃǂ���Ӗ����B���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ł�����B�ނ����]��i�H���߁A�]�ނׂ��l�ԂƂ͔@����Ƃ������Ƃ�Nj����邱�Ƃ����������Ƃ����Ă������̂�������܂���B�ꐶ�C�s�ꐶ�����Ƃ������Ƃ���ł��傤�B
�@���āA�����ʼn䂪�Ƃ̎��j�ɂ��ĐU��Ԃ��Ă݂܂��傤�B�����ڂŌ�����]����C�͂���悤�Ȃ̂ł����i���`���ۂ��ł����j�A�����̉߂��������Ȃ��Ă��܂���B��������Ƃ����Ē��܂ŐQ�Ă�����A�h�肪�Ȃ�����Ƃ����āA���Ɍ�����Ȃ�������A�߂�ǂ�����������Ƃ����ďo�s���ɂȂ��Ă�����c�B
�@�R�N��A���w���Ƃ̎��ɍ���̋L����U��Ԃ��Ă݂���A�ʂ����Đ�����������̂ł��傤���H�����Ƃ����Ԃ̂R�N�ԁA�{�l�ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȏ��Ԃɂ��Ă��炢�����Ɗ肤����ł��B�܂��������������Ė{�l����Ȃ�ł����ǂˁB
�@
2010.4/28�f��
�c���c���Ǝv���Ă��܂������A�����𒅂Ă݂Ă������̎��j�͒��w���Ɍ����܂���B����Ȏ��j�̒��w�Z�̓��w�����h�L�������g���Ă݂܂��傤�B
11��40���@���j�̒��w�̓��w���͌ߌ�ɍs���܂��B���o���o�Ȃł���悤�ɂƂ������Ƃł����A���k�ɂƂ��Ă����H���ς܂��Ă���������ƒg�������ɏo������ꂤ�ꂵ�����̂ł��B���w�Z�͏��w�Z�ׂ̗ɂ���̂ŁA�ʊw�H�͏��w�Z�̂Ƃ��Ɠ����B10���قǂ̓����A������ƈꏏ�ɕ����܂����B���Z���Ă���ߏ��̏��w���ɉ�ƁA�p�����������ɂ��Ă��܂����B
12��00���@���w�̌��ւŃN���X���\�����܂��B���j�͎O�g�B���w�Z����̒��悵�͂��Ȃ��悤�ł����A�ނ��낻�̂ق����i�������������N���Ƃ������̂ł��傤�B�e����t���ς܂��ċ����ɓ���܂��B
12��30���@�ی�҂͍T�����őҋ@���Ă���ԁA���k�����͊e�����ʼn��S�C���炢�낢��Ȏw�����܂��B���w���̒i��肩��A�����̒����Ȃ��̃`�F�b�N�A����̏��Ԃɕ��ԗ��K�Ȃǂ����Ă��܂��B�����ɗ���͓̂���܂Ŗʓ|���݂鉼�S�C�B��u�́u���̐l���S�C���v�Ǝv���܂����A�����ȒS�C�����\�����Ɠ�b�ŖY�ꋎ���鑶�݂ł��B
12��50���@���悢����w�����n�܂�܂��B�ݍZ���E�ی�ҁE���o�̏��ɓ��ꂵ�A�V������҂��܂��B�V�����͈�g����g�����ɓ��ꂵ�܂��B���j�͎O�g�B�g�����Ȃ̂őO�����ԖځB�����Ԃ����悤�Ɏv���܂����A�������w�Z�ɓ��w���������傫�����Ƃ�������������Ƃт�����B�������Ȃ�ɂ��e���čs���Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃ���˂Ȃ�܂��܂��B
�@�����͕̂��ʂł��B�����E�����E�j���E���}�̌��t�ȂǁA���w���炵���l�R�Ɛi�ݖ������w�����I�����܂����B
13��55���@���x�~���͂���ň��������n�Ǝ����s���܂��B�V�C�E���̏Љ��A�Z���搶�̘b�ɑ����āA�{���ő�̃C�x���g�A�S�C���\���s���܂����B���j�̊w�Z�ł͈�N�����N�ɐi������Ƃ��ɃN���X�ւ�������̂ŁA���̒S�C�Ƃ͈�N�Ԃ̂��t�������B����ł����w�Z�Ɋy�����Ȃ���ł����邩�̑傫�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��̂ŋ����ÒÁB���j�̒S�C�̓A���t�H�[�̎Љ�ȒS���̒j���搶�B�ݍZ�O�N�ڂƂ������Ƃŗ������������͋C�̃N���X�ɂ��Ă����Ă��ꂻ���ł��B
14��30���@�����ɓ����ĒS�C�̎{�����j���܂��B�ǂ̐搶�������b�������ł����A���w�ْ̋��ł��܂�L���Ɏc��Ȃ��̂�����ł��B�V�������ȏ������炢����ڂ͏I���ł��B
�u�܂�������Ȃ��v�����j�̊��z�B���ė�������ǂ�Ȋw�Z�����𑗂��Ă���̂��́A�܂�����ȍ~�ɁI
�@
��196�b�w�𗧂��̂��x
2010.5/12�f��
�@���j�����w�Z�ɓ��w���Ă͂��P���B����Ɋw�Z�����ɂ�����A�����̃��Y�����o�Ă��܂����B�܂����������{�i�����Ă��Ȃ��̂ő����͂̂�т肵�����̂ł͂���܂����c�B
�@�̂�т�Ƃ͂����Ă��A�w�K�̕��͑҂��Ă���܂���B�V�����n�܂����p���A���Ȃ��Ƃɕς��搶�̓����Ɋ����̂ɂЂƋ�J�̖����ł��B���ɖ����̏h��ł���w��o�m�[�g�x�Ƃ�����ɋꂵ��ł��܂��B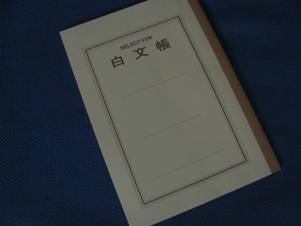
�@���āA���̒�o�m�[�g�A�{���ɖ𗧂̂ł��傤���B�����w���t�ŁA��o�m�[�g�������Ɉ����Ă��邩�n�m���Ă��镃����Ɍ��킹��ƁA�Y�o���w���ɗ����܂���x�B
�@�܂����k�̗��ꂩ��\���܂��傤�B�������o����Ƃ����̂́A�ӎ�����_���ɏW�����A���`����{���Ƃ������ƂȂ̂ł��B��ƓI�ɉ�����������o����Ƃ������Ƃ͂��蓾�܂���B�������ʂ�����Ȃ珑�����̃}�X�^�[���炢�ł����A���ې��k�������ǂ�Ȃӂ��ɏ����Ă��邩�Ƃ����ƁA�ォ�牺�܂ł��ׂẴ}�X�ɂ܂��w���x�̎����������ɏ����܂��B�����āw���x�����ׂẴ}�X�̉E�㕔�ɏ����A�Ō�ɂ��̉��Ɂw�y�x�����ׂẴ}�X�ɏ����Ă����B�������āw���x�Ƃ��������o���オ��܂��B�܂��ƂɊ���ł�������Ȃ��Ƃ����\����̂ł��B�ǂ����Ă������Ċo�������Ȃ�ѕM�Ńf�J�f�J�ƈ�����A���^�����O�Ŏd�グ��������ʓI�ł��B
�@���t��������Ԃ����m�点���܂��傤�B�搶���͂قƂ�nj��Ă��܂���B����͖̂��O�Ɨʂ����B�ԃy���Ŋۂ����Ă�����܂��������B�n���R�����|���Ƃ����l��A�W�̐��k�ɖ��O�����`�F�b�N�����ďI���Ƃ����l�����܂��B���܂ɓY�킵�Ă���̂́A���R�J�����y�[�W�ɂ����������A���̎q���}�[�N����Ă������B���̂������̃m�[�g�̒�o���u����̊w�K�_�v�Ƃ��Ēʒm�\�ɔ��f���܂��B���ׂĂ̐搶���������Ƃ͌����܂��A�قƂ�ǂ������ƌ����ĉߌ��ł͂���܂���B����Ȃ̂�����A���w�A�p��ƎO���Ȃ������ł�����c�B
�@���������̒�o�m�[�g�Ƃ������K�́A���쌧�����̂��̂��Ɓu�閧�́����V���[�v�Ƃ����e���r�ԑg�Ŏ����ꂽ���炢�ł��B���ʂ̈��Ƃ���2009�N�x�S���w�̓e�X�g�̏��ʂŌ���ƁA���Z�ł�17�ʂȂ̂ɁA���O�ł�26�ʁB���w�̋�����j�ɖ�肠��ƌ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���O�l�̎����猩��ƁA���쌧�l�́A�ς�������Ƃ��n�߂�͓̂��ӂł����A������U�蕥���̂����������ł��B�����A�����̒��ň�����l�i���̍��͍Ő�[�������̂����H�j���������ƋC�t�����A�`���Ƃ������̂��ƂɌp������Ă����̂ł��B
�@���낻��{���͒E�����āA�܂��́w�X�^���_�[�h�x��ڎw���ׂ����Ǝv���̂ł����c�B
�@
��197��w�𗧂Ă悤�x
2010.5/19�f��
�@�O���o�m�[�g�����ɗ����Ȃ����Ƃ��������Ƃ���A���\�����̕����犴�z�����������܂����B���̒��ň�ԑ��������̂́u�������`�B�܂�����Ȃ��Ƃ���Ă�B�w�Z���ĕς��Ȃ��ˁ`�v�Ƃ������́B���ꂪ�����Ăقߌ��t�łȂ����Ƃ��A�w�Z�W�҂͂�������ƐS�ɂƂǂ߂�ׂ��ł��傤�B
�@�u���Ⴀ�ǂ�Ȃ��������ɗ��́H�v�Ƃ�����������������܂����B��͂���ʓI�ȕ��@��m�肽���Ƃ����̂͐l��B���������Ă��������B�Y�o���\���グ�܂��傤�B�w�킩��Ȃ��I�x
�@�u�H�I�H����Ȗ��ӔC�ȁv�Ǝv��Ȃ��ł��������B�킩��Ȃ��ƌ����̂́A���@���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���ʓI�ȕ��@�͏\�l�\�F�A�S�l�S�F�Ȃ̂ł��B���������A�����ɓK�������ʓI�ȕ��@�������������Ƃ��A���w�Z�̊w�K�̎��ƂƂ炦���ق��������̂ł��B
�@���ʓI�Ƃ������t�́A���ʂɂȂ���ƌ��������Ă����ł��傤�B���w�Z�̋�̓I�Ȋ����Ō����Ɓw�e�X�g�̓_������x�Ƃ������Ƃł��B�u����ȓ_��蒎�Ɉ�Ă����Ȃ���B�e�X�g�̂��߂ɐ����Ă��Ȃ�����v�Ǝv���邩������܂��A���z���Ⴂ�܂��B�e�X�g�͂��ꂪ�Ȃɂ��e�X�g�����ł��傤���H�u�搶�����k���v�́~�B�u���k�������̕����@���v�����B�e�X�g�œ_����ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���ʓI�ȕ��@���g�ɒ������Ƃ������ƂȂ̂ł��B�t�ɓ_�����������Ƃ������Ƃ́A���ʓI�ȕ��@���Ƃ�Ă��炸�A���ʂȓw�͂����Ă����Ƃ������Ƃł��i�w�͂��ĂȂ��킯���Ⴀ��܂���j�B���̂�����ς��A�����ɍ��������@��V���ɒT���K�v������̂ł��B
�@���Ȃɂ���āA�P���ɂ���āA���ڂɂ���Ă��ꂼ��Ɍ��ʓI�ȕ��@���Ⴄ���Ƃ����Ă���܂��B�������@�ł���Ă�̂ɁA����͂������ǐ��w�������Ȃ��A�Ƃ��A�P�N�̎��͂ł����̂ɂQ�N�ɂȂ��Ă����ς�A�Ƃ����̂����ނ̕ω��ɁA���ʓI�ȕ��@�����Ă����Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�l�X�ȃV�[���ɍ������l�X�ȕ��@���A�ӂƂ���[���������g�ɂ��Ă����̂����w�Z�ł̊w�K�Ȃ̂ł��B
�@���w�Z�ł͂��̌��ɂȂ�w�K�̏K����������Ă���܂��B���X���Ɍ��������̎��Ԃ����B���̂��߂ɏh�肪�o�܂��B���Z��������́A�o��ҁi�w�Z��A��Ђ�Љ�j���猩�āA�K�v�Ȕ\�͂�������Ă��邩�ǂ���������܂��i�܂��Ƀe�X�g�����j�B�\�͂�������Ă��Ȃ���o�b�T������^�������ł��B�K�v�Ȕ\�͂��l��������@���g�ɂ��Ă��Ȃ���A���ʂȓw�͂��������ʃo�b�T���Ɛ��ďI���B
�@�����̔\�͂ƁA���C�t�X�^�C���ƁA�ڕW�ɍ��������ʓI�ȕ��@��T���Ă�����̂͒��w�̂R�N�Ԃ����Ȃ��̂ł��B�����Ă��̂R�N�Ԃ̈Ӗ��̑傫���Ƃ�������c�B
�@
��198�b�w���������x
2010.6/9�f��
�@��������A�e�����̌ږ₪�W�܂������Ɂw�ǂ̕���������Ԃ�����������Ȃ����낤�H�x�Ƃ������Ƃ��c�_�������Ƃ�����܂����B���̎��̓o���[�{�[��������Ԉ����Ƃ������ʂɂȂ�܂������A���j�̏o������ލ��A�Č����Ă݂܂��傤�B
�@�������H���A��Ô�Ȃǂ́A�ǂ̂��炢�����c��A�M�S�Ɋ������邩�ɂ���Ĉ���Ă���̂ŁA�����ł͏��O�i���O�ł����ꉞ�m�����Ƃ���ł́A�N��20���~�߂�����A�قƂ�ǂO�~�܂ł���悤�ł��j�B����Ɋw�Z�̎���ɂ���āA�����p���j�t�H�[�����ǂ��������ɈႢ������悤�ł��B�����ł͓���̊����ɕK�v�Ȍl�̎������Ƃ������Ƃōl���Ă݂܂��傤�B
�@�܂��O�҂��o���[�{�[���@�ǂ����Ă�����̂̓V���[�Y�ƃ\�b�N�X5000�~�B�Ђ����āA�Ђ����Ă܂Ŕ����Ă�10000�~���炢�B���j�t�H�[���������Z�ɔ�ׂĈ����̂����͂ł��B
�@�싅���@�O���[�u�A�o�b�g�A�X�p�C�N�ɗ��K�p���j�t�H�[���X�q����C���܂ňꎮ�i���肱�ނƔj��邽�ߖ싅���ɂ͗��K�p���j�t�H�[���͕K�g�j�B���悻30000�~���B�A���_�[�V���c�Ȃǂ͉������K�v�ł��B
�@�T�b�J�[���@�X�p�C�N�A�X�g�b�L���O�A�V���K�[�h�͕K�v�B�ŋ߂̃Q�[���p���c�͉����ƈ�̌^�������Ă���̂ł�����l�����B10000�~�قǂŎ��܂邩�B
�@�o�X�P�b�g�{�[�����@�V���[�Y�ƃ\�b�N�X�i���̃V���[�Y�������I�o���[�͍����i��10000�~�Ȃ̂ɁA�o�X�P��10000�~���͕��ʁj�B�Ƃ������ƂŖ�10000�~�B
�@�e�j�X���@���P�b�g�i�K�b�g�܂ށj�A�V���[�Y�A�E�F�A�B�l���Z�Ȃ̂ŃE�F�A���l�����Ȃ̂��A�������e�j�X�̂������Ȃ̂��A30000�~�قǂɂȂ�܂��B
�@�싅���@���P�b�g�i���o�[�܂ށj�͌l�����B�V���[�Y�ƁA�E�F�A���w�Z�̑̈畞�ōς܂����5000�~�ȉ��B
�@�����E���p�n�@�E�F�A�͂��ׂČl�����B�����Ēi�ʔF��Ȃǂ��A�K�{�Ȃ̂Ő����~������܂��B
�@���㕔�@�g���b�N�E����n�̓X�p�C�N�B���[�h�n�̓V���[�Y�B������ڂ͐�p�V���[�Y������܂��B�C�ۓ�������ŌC�͉��ł��悯��O�~���\���I�i��p�V���[�Y�͌��\�����j
�@�o�h�~���g�����@���P�b�g�i�K�b�g�܂ށj�A�V���[�Y�B20000�~�قǂɂȂ�܂��B
�@���̑��̋��Z�@�܂��܂������ς����͂���܂����A���Z�l���̏��Ȃ����Z�قǓ�������Ȃ�͎̂��{��`�̊�{�B���Z�p����������10000�~�͉���܂���B
�@����͂����܂ł��Œ�̋��z�ŁA���ۂɂ͈���ᑫ��Ȃ����̂�A�`�[���ő������肵�Ă���Ƃ����܂��������Ă��܂��܂��B�ɂ����Ȃ����Ă����E�\�ɂȂ�܂����A�ɂ����Ȃ��قNJ撣���Ă����܂��ǂ��Ƃ��܂��傤�B
�@
��199�b�w�_�̖��l�̖��i�l�ҁj�x
2010.6/19�f��
�@������̎��Ƌ��s�{�F���s�ɁA�p�i�������j�_�ЂƂ���������܂肵���_�Ђ�����܂��B��Ղ́w�Èł̊�Ձx�Ƃ�������̂Ȃ̂ł����A��Ղ��̂��̂����w���{�ꂽ������̖�X���o�邨�Ձx�Ƃ��ĎR�����т̒���ȂǂŗL���ɂȂ������Ղł��B
�@������ɂƂ��Ă͎q���̎�����w���Ձx�Ƃ����������Ղł�����A���ꂪ���ʂ��Ǝv���Ă��܂����B������ɏ]���u�������Ղ͓��ʂ��v�ƒm��A���̋K�͂����{�ꂾ�����ƕ������ꂽ����ł��B���ʂœ��{��ƂȂ�ƁA����͂�͂�q���B�ɑ̌������˂Ȃ�܂��܂��B�������A�������Ղ͗j���ɊW�Ȃ��U���T���ƌ��܂��Ă��܂��B�q���B��A��Ă����ɂ́A���傤�Ǔy���ɂ�����A�������w�Z�s�����������Ă��Ȃ��N������̂������Ƒ҂��Ă��܂����B���N�͌����r���S�I���������łɐe�ʂ̖@�����������̂ő���U���Ă����Ă��܂����B
�@��N�͎����ɂȂ����Qkm�̎Q����1500�قǂ̖�X���o��̂ł����A��N�C���t���G���U�����ŏo�X�����~�ɂȂ������Ƃō��N�͏o�a�肪�����A�X���͔����ȉ������������ł��B����ł����������{��Ƃ����K�͂ł��B�q���B�ɂƂ��Ă͌������Ƃ��Ȃ��悤�Ȃɂ��킢�B�R��������������点���߂Ă�����X�ցB
�@���Ղ̉���Ƃ����A�^�R�Ă��E�Ă����E���D�ݏĂ��Ȃǂ̒�ԐH�ו����B��������������܂��B�q���B���m��Ȃ������̂͂��D�݊����E��₵�t���[�c�E�^�R����ȂǁB�ӌ�т�����Ȃ��قǂ�������H�ׂ܂����B
�@�X�}�[�g�{�[����֓����E�˓I�̗V�Y���B��������������܂��B�q���B���т����肵���̂͂��Ă��̉��i���������j�̑����B���̂悭�Ȃ邨�َq�⎆�����̑��ɂ��A���܂��܂ȍH�v���Â炵�������������ς��B������Ȃ��ƕ������Ă��Ă���������Ă��܂����̂Ȃ̂ł��B
�@�q���B����Ԃ͂܂��āA���������̂͌��Ƃ��Ȃ���B���쌧�ł͂��܂�Ȃ��݂��Ȃ��悤�ł����A��Ԃ̖�X�B��������q�ǂ��̍���Ԃ͂܂������̂ł����B�ނ�Ƃ����Ă��a�Œނ�̂ł͂Ȃ��A����̕����Ƀt�b�N�݂����Ȑj�������|���āA�ނ�グ����́B���Ȃ���40cm�قǂ����M�����[�T�C�Y�B�u�ނ��킫��Ȃ��v�Ǝv��������Ă��܂����̂Ȃ̂ł��B�i���X�ނ��l�����邩���߂��Ȃ��I�j���͌��\�ނ�܂��B10cm���炢�Ȃ畡���C���\�ł��B15cm���������̂��ǂ���B�����̂ƈ���āA�w�ނꂽ��݂�Ȃ����x�킯�ł͂Ȃ��w�����A���C�x�̐���������܂�����A�����������₷���ł����i�ނ�Ȃ��Ɓw���܂��ň�C�x�͂���܂���j�B
�@�s���R�������q���B�ƕꂳ��̓_�E���B������������͖�ɂ��ړI���I����͈�́H����ɑ����B
�@
��200�b�w�_�̖��l�̖��i�_�ҁj�x
2010.7/3�f��
�@������̎��Ƌ��s�{�F���s�́A�p�i�������j�_�Ђ̗�Ղ͑O��̑����B
�@�w���{�ꂽ������̖�X���o�邨�Ձx�Ƃ��ėL���ł���������ɂƂ��Ă͎q���̎�����w���Ձx�Ƃ����������Ղł�����A���ꂪ���ʂ��Ǝv���Ă��܂����B�ł����A�U��Ԃ��Ă݂�ƁA��X���o��̂����ՂƂ������Ⴂ�����Ă����悤�ȋC�����܂��B�_�Ђ̂��Ղł����瓖�R�_�����s���A���ꂱ�����Ղ��̂��̂ł���͂��ł��B�����ŁA�e�މ��ҁA�F�l�m�l�Ɂu�������Ղ̖{�Ղ��Č������Ƃ���H�ǂ�Ȃm���Ă�H�v�ƕ����Ă݂��Ƃ���A100���ʼnm�n�܂����B����͗R�X�������Ԃł���B�{�Ղ��������čՂ葛������������Ƃ����̂͂������Ȃ��̂��B�����̐��܂�̋��̍Ղ��炢�������茩�Ƃ��K�v������B�Ɣ��Ȃ��A�Èł̊�ՂƂ�����{�Ղ����ɏo�����܂����B
�@�{�Ղ͖�11��30������n�܂�܂��B11���߂��ɏo�����Ă����ƁA��قǂ܂ő���킢�����ĎQ���͖�X�����ׂĂ����܂�A�w���Ƃ̍Ղ�x��ԁB�l�Ԃ����������̂��̐���搉̂����c�[�����ɐ���������ł��B
�@�����ɓ���Ƃ����ɂ͐l���т�����ƁA���Ȃ��c�B����ق�ƌ�����Q�w�҂́A�������ς����Ă�300�l�قǁB���̂���100�l�͎��q����B�ł��傤�B��X�̐l�o��15���l��0.2�������{�Ղ����Ȃ��̂ł�����A�e�މ��ҁE�F�l�m�l���������ƂȂ��Ƃ����̂��[���ł��܂��B
�@�{�Ղ͂قڒ荏�Ɏn�܂�܂����B���������w��Ձx�Ƃ����Ă���̂ł�����A�����Ŏ������e�����\����͍̂T���܂����A�_���Ƃ��ĂƂĂ��ǂ������̂��̂��Ǝv���܂����B�������_�Ђ͈��Y�E�o�Y�E�lj��E�q��Ă̎��_�w���̂͂Ȃ�����Ђ߁x���Ր_�ł�����A�Èłł��闝�R��G���e�B�V�Y�����Y�����Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��ł��傤�B���������ڂ�������J���I�ȕ��͋C�͈�Ȃ��A�Î��L��_�K�ɂ��Ƃ��l�ɂ͂����́w����オ��Ȃ��Ձx�Ɍ�����Ǝv���܂��B�킩���Č���ƁA���ɃX�g�[���[�L���ŁA�V�������ꂽ�l�������`����Ă��܂��B
�@�����w�ÈŁx�ɂ��Ă͂����L�������ł��B�ꉞ�_���̐ߖڂł͏������Ăт����A�X���Ȃǂ͏�����܂����A����J������r�f�I�̉�ʂ͌������B�߂��̐M���@���_�ł��Ă��܂��B���܂��ɂ��̓��͉����̔����B��Ղ̈ꕔ�n�I�͂�������ی����ł����B
�@�{�Ղ��I�������̂͌ߑO1���B�Гa�ɕ�[���ꂽ���V����䕼�����������A�O�X�܁X�Q�w�ҒB�͋A���Ă����܂����B
�@�����A�ڊo�߂��q���B�͂܂����Ղ�C���B���̖�X�̂ɂ��킢�Ƌ����͂܂��܂����������ł��B
�@�ʂ����č���n���̏����Ȃ��ՂŐ���オ���̂��S�z�ł��B